 |
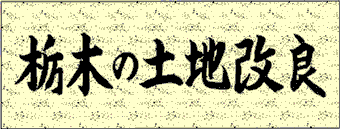 |
『水土里ネットとちぎ』は本会の愛称です

−主な内容−
 |
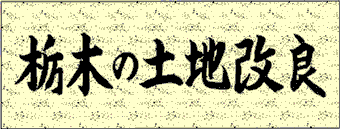 |

| 平成19年度農業農村整備事業費概算要求 |
農林水産省は、8月31日、平成19年度農林水産予算の概算要求書を財務省に提出した。平成19年度の概算要求基準では、平成19年度予算が今後5年間の新たな改革に向けた出発点となる重要な予算と位置づけ、これまでの財政健全化の努力を今後とも継続していくため、引き続いて歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、歳出の抑制と所管を越えた予算配分の重点化・効率化を実施するとしている。このため公共事業関係費に関しては、総額を対前年度97%の範囲内に抑制するとしているが、各省庁の要望については、各所管ごとにその額の1.2倍の額を上限として認められている。さらに、経済成長戦略推進要望として経済成長戦略大綱に掲げられたもののうち、新規性の高い事業・技術開発・地域経済の活性化効果の特に高い事業などについて2%まで加算することができることなどから、概算要求総額は、対前年度比13.4%増の3兆1,514億円とし、うち公共事業費が同17.9%増の1兆4,258億円、非公共事業費が同10.0%増の1兆7,257億円を計上した。
農業農村整備事業費については、対前年比18.5%増の8,622億8,000万円。うち「経済成長戦略大綱」に基づく「経済成長戦略推進要望」として136億円、また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に基づく「新重点5分野」には7,107億円を要求した。
なお、地域再生基盤強化交付金措置額に対する概算要求基準に基づく要望額を含むと、9,025億円(対前年度比118.5%)の要求額となる。
概算要求においては、新たな「食料・農業・農村基本計画」の実現に向けた農業農村整備の推進や1.構造改革のための基盤づくりの新たな展開、2.地域の活力を活かした農山漁村づくり、3.地域資源を活かした潤いある国民生活の実現に重点を置いている。2.においては、平成18年度の実験事業の経過をふまえて新規に農地・水・環境保全向上対策事業に303億円を計上した。
なお、概算要求の基本的な考え方等については、次のとおり。
平成19年度 農業農村整備事業概算要求の概要
[1].平成19年度 農業農村整備事業 概算要求額
(9,025億円(対前年度比 118.5%))
8,623億円(対前年度比 118.5%)
(7,509億円)
うち「重点5分野」7,107億円
(注)上段( )書きは、地域再生基盤強化交付金措置額に対する概算要求基準に基づく要望額を含む。
[2].農業農村整備事業における重点分野等への対応
(1)経済成長戦略推進要望への対応 136億円
経済成長戦略大綱(平成18年7月6日財政・経済一体改革会議)に基づき、農林水産業の国際競争力強化に資する以下の事業について要求。
1.経営体育成基盤整備事業 【51億円】
2.畑地帯総合農地整備事業 【74億円】
3.農業生産法人等育成緊急整備事業(新規) 【10億円】
(2)新重点5分野への対応 7,107億円(重点化率82.4%)
経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(平成18年7月7日閣議決定)に基づき、安全・安心の確保と柔軟で多様な社会の実現のための取組を推進。
1.再チャレンジ支援 【5億円】
2.生活におけるリスクへの対処 【7,102億円】
○災害対策(1,404億円)
大規模水害・土砂災害対策、津波・高潮対策や防災情報の伝達体制の整備等を通じた安全で安心な国土づくり
○安全性・信頼の再構築(5,001億円)
国民への食料の安定供給を確保するための農地・農業用水等の食料供給力の維持・向上
○地球環境の保全・循環型社会の構築(698億円)
自然エネルギー及び有機性資源等のリサイクルによる循環型社会の構築
[3].平成19年度 農村振興局予算概算要求の重点事項
1.構造改革のための基盤づくりの新たな展開
【ポイント】
農業の構造改革の加速化を図る観点から、農業生産法人等の育成を緊急的に支援するなど、基盤整備を契機とした担い手の育成・確保や農地の利用促進を図る。
農業生産の基盤となる基幹的な農業水利ストックを効率的に更新・保全管理するための仕組みを整備する。
○基幹水利施設ストックマネジメント事業【公共】〜新規〜
重点1 水利ストックの有効活用
4,000(0)百万円
○国営造成水利施設保全対策指導事業【公共】〜拡充〜
1,800(873)百万円
○農業生産法人等育成緊急整備事業【公共】〜新規〜
重点2 農業の構造改革の加速化に資する基盤整備
1,000(0)百万円
○段階的基盤整備等実証事業【公共】〜新規〜
1,000(0)百万円
○土地改良負担金総合償還対策事業【非公共】〜拡充〜
○食の安全・安心確保基盤整備推進対策【公共】〜新規〜
重点3 安全な食生活を支える基盤整備
150(0)百万円
○耕作放棄地防止適正管理実証化事業委託【非公共】〜新規〜
重点4 耕作放棄地対策の一層の推進
50(0)百万円
○農業生産の基盤の整備のうち遊休農地再生活動緊急支援【非公共】〜拡充〜
(元気な地域づくり交付金)40,643(41,526)百万円の内数
2.地域の活力を活かした農山漁村づくり
【ポイント】
農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と先進的な営農活動を実施する地域等を支援する交付金を創設する。
自ら考え行動する意欲あふれた農山漁村を実現するため、情報基盤や生活環境基盤の整備を推進すると共に、ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策を推進し、自助、共助、公助による安全で安心なくらしを実現する。
○農地・水・農村環境保全向上活動支援事業【公共】〜新規〜
重点5 農地・水・環境保全向上対策の本格的実施
25,588(0)百万円
○営農活動支援交付金【非公共】〜新規〜
2,986(0)百万円
○農地・水・環境保全向上活動推進交付金【非公共】〜新規〜
1,712(0)百万円
○「立ち上がる農山漁村」推進事業委託【非公共】〜継続〜
重点6 自ら考え行動する農山漁村の新たな取組の推進
40(0)百万円
○農村地域IT化推進支援事業【非公共】〜新規〜
40(0)百万円
○元気な地域づくり交付金【非公共】〜継続〜
40,643(41,526)百万円の内数
○国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク構築事業【公共】〜新規〜
重点7 農村地域における防災・減災の取組
300(0)百万円
○農村災害支援体制強化事業【公共】〜新規〜
25(0)百万円
○ため池等整備事業【公共】〜継続〜
29,931(24,559)百万円
○中山間地域等直接支払交付金【非公共】〜継続〜
重点8 中山間地域等直接支払制度の確実な実施
22,146(22,146)百万円
3.地域資源を活かした潤いある国民生活の実現
【ポイント】
多様な主体が参加して都市と農村の共生・対流に取組む広域連携プロジェクトや、都市部での体験農園等の拡大、生産緑地等の保全等の先導的取組を支援する。
また、バイオ燃料の導入やバイオマスタウン構築の加速化を支援すると共に、農業水利施設を小水力発電として一般利用することを支援する。
○広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】〜新規〜
重点9 都市・農村の共生・対流の新たな展開
300(0)百万円
○広域連携共生・対流等整備交付金【非公共】〜新規〜
500(0)百万円
○元気な地域づくり交付金【非公共】〜継続〜
40,643(41,526)百万円の内数
○グリーン・ツーリズム情報発信機能強化事業【非公共】〜継続〜
89(89)百万円
○広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】〜新規〜
重点10 都市農業の新たな展開
300(0)百万円
○都市農業の振興のための条件整備への支援【非公共】〜拡充〜
(元気な地域づくり交付金) 40,643(41,526)百万円
○バイオ燃料地域利用モデル実証事業【非公共】〜新規〜
重点11 バイオマスの利活用の推進
8,547(0)百万円
○地域バイオマス利活用交付金【非公共】〜新規〜
16,005(0)百万円の内数
◯農業用水の自然エネルギーの活用支援事業【非公共】〜新規〜
重点12 農業用水の自然エネルギーの活用支援事業
40(0)百万円
(別表)事業別概算要求額(国費) (単位:百万円、%)
注1:百万円単位に四捨五入のため、計が合わない場合がある。
事 項 H18年度
予算額
(1)H19年度
概 算
要求額
(2)対前年
伸 率
(2)/(1)農業農村整備事業
(うち農村振興局)(761,829)
727,829
710,116
(902,514)
862,280
841,294
(118.5)
118.5
118.5
(農業生産基盤整備)
1.かんがい排水
うち国営かんがい排水
うち基幹水利施設ストックマネジメント事業
2.経営体育成基盤整備
うち農業生産法人等育成緊急整備事業
3.諸土地改良
うち農地・水・農村環境保全向上活動支援事業
4.畑地帯総合農地整備
5.国営農用地再編整備
6.機構事業
7.その他
444,537
229,223
197,483
−
80,010
−
9,812
−
50,189
19,423
27,457
28,423
543,616
272,997
230,623
4,000
96,050
1,000
34,980
25,588
63,845
12,675
31,960
31,109
122.3
119.1
116.8
皆増
120.0
皆増
356.5
皆増
127.2
65.3
116.4
109.5
(農村整備)
8.農道整備
9.農業集落排水
10.農村総合整備
11.農村振興整備
12.中山間総合整備
13.その他
155,872
36,127
20,940
9,427
37,695
40,555
11,128
172,856
41,009
24,284
7,017
45,845
43,328
11,373
110.9
113.5
116.0
74.4
121.6
106.8
102.2
(農地等保全管理)
14.防災保全
(1)直轄地すべり
(2)国営総合農地防災
(3)農地防災
(4)農地保全等
15.土地改良施設管理
16.その他
127,421
109,413
1,800
44,290
43,159
20,163
13,451
4,557
145,807
127,754
2,160
45,256
54,055
26,283
13,230
4,824
114.4
116.8
120.0
102.2
125.2
130.4
98.4
105.9
注2:上段( )書きは、18年度予算額には地域再生基盤強化交付金措置額、19年度要望額には
同措置額に対する概算要求基準に基づく要望額を含む。
| 第29回全国土地改良大会が京都で開催 |
去る、10月10日に第29回全国土地改良大会(京都大会)が国立京都国際会館(京都市)において、野中広務全土連会長をはじめ、佐藤昭郎・段本幸男両参議院議員、国井正幸農林水産副大臣のほか農水省幹部や全国の土地改良関係者など、およそ4,200人を集め、盛大に開催された。

主催者挨拶をする野中全国水土里ネット会長

来賓祝辞を述べる国井正幸農林水産副大臣
今回の大会は『おこしやす 歴史育むふるさとへ〜いにしえの時空を超えて今伝えたいことがあります〜』をメインテーマに掲げ、農業・農村の多面的機能の発揮、農業の持続的な発展など、農業・農村の重要性、農業農村整備の役割等をアピールするとともに、環境との調和に配慮した農業農村整備事業の展開を図ることを目的に開催された。
式典は、記念行事として祇園甲部芸妓衆による“手打廊の賑い”が行われ「七福神」と「花づくし」の二曲を披露し来場者を出迎えた後、京都土連の片山茂代表監事が大会の開会を宣言し、まず野中全土連会長が主催者代表の挨拶、山田啓二京都府知事と桝本頼兼京都市長がそれぞれ歓迎の挨拶を述べ、国井副大臣が農林水産大臣の代理として来賓祝辞を述べられた。
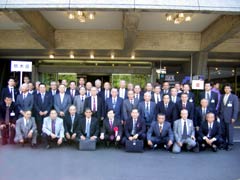
本県参加のみなさん
続いて沢田敏男京都大学名誉教授の文化勲章受章が披露された後、土地改良事業功績者表彰(6名)、農村振興局長表彰(17名)、全土連会長表彰(47名)、21世紀土地改良区創造運動大賞(12団体)の表彰式が執り行われ、本県からは齋藤源憲理事長(塩谷南部土地改良区)が全土連会長表彰を受けた。
この後、インターミッションとして竹取物語を表現した“日向かぐや太鼓”の勇壮な演奏をはさみ、優良活動事例地区の紹介、中條康朗農村振興局次長による基調報告、京都府立桂高校3年の西山勝将さんと京都府立木津高校3年の川西香さんによる「我々の財産である農地や水や農村を、地域や都市住民とともに守り、この豊かで美しい自然景観に育まれた農村を次世代に伝えていくことを宣言する。」などとの大会宣言が行われた。
大会も終盤を迎え、次期開催県である三重大会のPRビデオを上映後、大会旗の引き継ぎが京都府土連の田中英夫副会長から野中全土連会長へ、さらに服部忠行三重県土連会長へと引き継がれたところで服部会長が次期開催地の挨拶を述べ、会場の盛り上がりも最高潮に達したところで吹田全土連副会長の発声で万歳三唱が高らかに行われた後、藤原秀夫京都土連副会長の挨拶で大会は幕を閉じた。
この後本県参加団は、11〜12日にかけて京都府内の農業農村整備事業等の視察を実施した。
全国水土里ネット会長賞
齋藤 源憲 氏の略歴
昭和18年2月22日生まれ、63歳。塩谷郡塩谷町大字大久保在住。昭和57年12月の塩谷南部土地改良区の設立と同時に理事長に就任し、現在に至る。平成17年7月から塩谷町農業委員会委員、平成17年9月塩谷町農業振興地域整備促進協議会委員、また昭和63年8月から本会圃場整備部会員を務める。

| 平成18年度第1回農業農村整備部会を開催 |
本会は、去る9月26日、宇都宮市内において農業農村整備部会の平成18年度第1回会議を、来賓に大久保幸雄栃木県農務部技監、粂川元一同農地整備課長を招き開催した。
農業農村整備部会は、平成17年度までの開発整備、圃場整備、水利防災の三部会を統合し組織強化を図ったもので、新たな農業農村整備事業の積極的な推進を図るための諸対策の検討及び推進のための諸活動を行うことを業務としている。
会議に先立って、後藤伊位本会会長から部会改編に伴う新部会員の委嘱状交付を行ってのち、千保一夫部会長の開会挨拶に続いて後藤会長が挨拶を述べ、大久保技監から来賓挨拶をいただいた後、千保部会長の議長で議事が進められた。
議事は、第1号議案「副部会長の互選について」では、姿川土地改良区理事長加藤一克氏、小山用水土地改良区理事長山中政博氏を互選し、第2号議案「平成17年度活動報告について」、第3号議案「平成18年度活動計画について」の2議案を原案どおり承認、議決した。
その後、協議事項に入り「平成19年度県農業等施策並びに予算編成に関する建議要望について」を審議し、貴重な意見等をいただいた。
その他、平成19年度農業農村整備事業費概算要求については、粂川農地整備課長から国の概算要求内容の説明を受け、また、本会からは、国への陳情並びに農業農村整備事業の集いへの参加について及び平成18年度新規事業の水土里情報利活用促進事業についての説明を行い閉会した。
なお、新たに委嘱された部会員は次のとおり。
◆農業農村整備部会(敬称略)
部 会 長 千 保 一 夫(大田原市)
副部会長 加 藤 一 克(姿川土地改良区)
〃 山 中 政 博(小山用水土地改良区)
部 会 員 猪 瀬 成 男(上三川町)
〃 吉 澤 新 市(鬼怒川右岸土地改良区)
〃 阿 部 和 夫(鹿沼市)
〃 手 塚 信 作(黒川東土地改良区)
〃 伊 藤 直 樹(行川流域土地改良区)
〃 藤 田 忠 義(二宮町)
〃 小 坂 利 雄(真岡市中央土地改良区)
〃 黒 崎 健(芳賀町土地改良区)
〃 日向野 義 幸(栃木市)
〃 田 邊 豊 吉(壬生町土地改良区)
〃 遠 藤 忠(矢板市)
〃 古 口 雄 久(高根沢土地改良区)
〃 長 島 雄一郎(氏家土地改良区)
〃 加 藤 昌 男(黒磯土地改良区)
〃 高 橋 勇 丞(大田原市土地改良区)
〃 川 崎 和 郎(那珂川町)
〃 佐 藤 勉(小川第一土地改良区)
〃 郡 司 昭 三(小白井用水土地改良区)
〃 吉 谷 宗 夫(足利市)
〃 寺 嶋 勝 豊(吾妻土地改良区)
〃 小 沼 勝 重(三栗谷用水土地改良区)

| 平成19年度県農業等施策・予算に関する 建議・要請を実施 |
栃木県農業会議並びに栃木県農政対策協議会は、去る10月16日、宇都宮市内において、平成19年度の栃木県農業等施策並びに予算に関する建議・要請を実施した。
当日は、五味仙衛武栃木県農業会議会長、伊澤茂栃木県農業協同組合中央会副会長、野澤章浤本会専務理事等県内農業団体代表者が出席し、須藤揮一郎栃木県副知事、野中英夫同農務部長他関係幹部職員と面談し、各農業団体から提出された建議・要望をまとめて要請した。
なお、土地改良関係の要請内容は次のとおり。
平成19年度県農業等施策建議・要望事項
1.農業農村整備対策
1)農業農村整備事業の 計画的な推進について
農業・農村は、現在、国内外ともに一段と厳しい環境におかれておりますが、「食料・農業・農村基本法」と「食と農の再 生プラン」に基づき、新しい視点に立った施策の展開が期待されているところであります。このような中で、安全で安心な食料を生産、供給する農業の 持続的な発展と、豊かで活力ある農村社会の確立を図るためには、その基盤となる農業農村整備事業の着実な推進が不可欠であります。
本県の農業農村整備事業は、これまで概ね順調に進展してきており、圃場の整備率は約70%に達し、また、農業集落排水など生活環境に係わる事業も着実に推進されております。
しかしながら、圃場整備につきましては、近年、未整備地区に加えて、再整備の要望が出てきている状況にあり、また、農村地域の環境整備、とりわけ生活排水処理施設の整備が大幅に遅れている現状であります。
つきましては、本県農業・農村の発展の基礎をなしております生産基盤の整備と、生活環境基盤の整備を積極的に推進されますよう要望いたします。
2)土地改良施設維持管理に関する予算の拡大について
土地改良施設は、農業生産を支える基本的な施設としての役割のほかに、地域の排水機能や良好な環境維持等の多様な役割を果たしておりますが、施設の老朽化が進行する中で、機能維持を図るための適正な管理と整備補修の必要性が益々増大しております。
また、土地改良区が行う適正な管理と整備補修には、施設台帳の整備が必要となりますが、必ずしも充分とは言えないのが現況であります。
つきましては、土地改良施設等の本来の機能と国土・環境保全等の多面的機能が充分に発揮できるよう、次の事項について要望いたします。
(1)土地改良施設維持管理適正化事業予算の拡大
(2)施設台帳整備等のための予算の確保
3)県単農業農村整備事業予算の拡大について
食料・農業・農村基本法に即して、農業の生産性向上と農業経営の合理化等を図るには、地域の実情に応じたきめ細かな農業基盤の整備が緊要となってきており、土地改良区等から多くの要望が出ている状況にあります。
つきましては、県単農業農村整備事業予算の拡大を要望いたします。
4)土地改良区育成強化事業予算の拡大について
土地改良区は、食料供給力の確保のほか公共・公益的機能を有する土地改良施設の中心的な管理主体として、重要な役割を担っておりますが、本県では、運営基盤の脆弱な小規模土地改良区が多いため、これらの役割を適切に果たしていくためには、組織の再編整備等による運営基盤の強化や土地改良区の活性化を図ることが緊急の課題になっております。このため、近年、急速に統合再編に関する活動が盛んに行われております。
つきましては、土地改良区育成強化事業予算の拡大を要望いたします。
5)21世紀土地改良区創造運動に対する支援制度の創設について
21世紀土地改良区創造運動は、「水と土」の管理者として土地改良区が果たしてきた役割・機能を改めて見直すとともに、その存在意義について関係者が誇りを持ち、地域住民に期待される新たな土地改良区の役割に対し、今後どのように取り組んでいくかを地域住民と一緒になって考えることを提案する運動であり、現在、地域と連携した様々な取り組みが全国的に展開されているところであります。
つきましては、土地改良施設の公共・公益的な役割を考慮し、その維持保全に係る運動であります21世紀土地改良区創造運動を行政施策として位置付け、運動に取り組もうとする土地改良区等に対する支援制度を創設するよう要望いたします。
6)農地・水・環境保全向上対策の推進について
本対策は、品目横断的経営安定対策と車の両輪に位置付けられ、農業・農村における生産資源や環境資源の維持・保全に大きく寄与することが期待されております。
つきましては、これらの資源が県民共有の財産として、良好な形で将来に引き継いでいくため、本対策を推進されますよう要望いたします。
2.県より国に対して要望されたい事項
1)農業水利施設の保全管理に対する支援制度の拡
充について
農業水利施設の大規模化や公益性、安全性の確保等のため構造が複雑化し、高度な管理を要する施設が多くなっており、これら農業水利施設の管理主体である土地改良区の管理費が増加し、農家負担が増大しております。
つきましては、土地改良区の管理体制の整備強化に極めて有効であります国営造成施設管理体制整備事業(管理体制整備型)の対象施設を県営造成施設まで拡充した管理費補助制度の創設について、国に対し働きかけられますよう要望いたします。
2)環境に配慮した農業基盤整備を推進するための
支援制度の創設について
近年、環境に配慮した農業施策の重要性が強調されております。こうしたことから農業農村整備事業においても、今後は、生態系に配慮した工法での水路建設や自然環境を保全するための用地の確保等、さらに、その後の管理などに新たな経費が必要になってまいります。
つきましては、このような環境配慮に伴う事業費や管理費の増加分に対する助成制度の創設について、国に対し働きかけられますよう要望いたします。
3)土地改良区組織運営強化対策の拡充について
土地改良区統合強化対策の一環として実施いたしました土地改良区統合整備体制強化事業は、平成15年度で完了いたしましたが、その後についても、食料供給力の確保のほか公共・公益的機能を有する土地改良施設の中心的な管理主体としての土地改良区の事業運営基盤を強化するために、統合整備を強力に推進する必要があります。
つきましては、土地改良区組織運営基盤強化対策を拡充して、統合整備を推進するための継続的助成制度の創設につきまして、国に対し働きかけられますよう要望いたします。
4)農村環境計画策定事業に関する予算の拡大について
近年、環境に対する国民の関心が高まる中で、農業農村整備事業におきましても、総合的かつ効率的な環境配慮対策を講じることが重要となってきております。
また、適切な環境への配慮や、地域住民の多種多様な意向に機動的に対応するためには、環境に対する総合的な調査を行い、事業上の対応策や各種環境整備メニューの選定を行う必要があります。
つきましては、農村環境計画を策定するために必要な予算の充分な確保と新規採択枠の拡大を国に対し働きかけられますよう要望いたします。
5)農地・水・環境保全向上対策について
本事業は、平成19年度に「農地・水・環境保全向上対策」として本格的に導入される予定となっておりますが、県内の市町におきましては、市町単独の調査費等を計上して新規地区の掘り起こしに取り組んでいるところでありますので、これら調査費等に対する補助制度の創設を国に対し働きかけられますよう要望いたします。
| 農業集落排水の整備促進を知事に要請 栃木県農業集落排水事業連絡協議会 |
栃木県農業集落排水事業連絡協議会(会長:高橋森一下福岡農業集落排水管理組合長)は、去る10月3日、福田富一栃木県知事に対して、農業集落排水事業の整備促進を求める提案書を手渡した。
本県における農業集落排水施設の整備地区は、平16年度末までに、86地区、普及人口で約8万人、普及率43%と低い水準にあり、栃木県農業農村整備推進計画の「とちぎ水土里づくりプラン」では、平成22年度までに供用可能人口を11万人にまで引き上げる計画となっているが、県・市町とも厳しい財政事情の中で、思うように事業が進まない状況となっている。
このようなことから、栃木県農業集落排水事業連絡協議会の役員会において、栃木県に対して計画的に整備促進を図るよう要請することとなったものである。
以下は、提案書の概要である。
農業集落排水事業の推進について
農業・農村は、食料の生産はもとより国土の保全、水源のかん養、自然生態系の保全など数多くの役割を担っております。
しかしながら、農村集落は、混住化の進展に伴う生活様式の多様化により、農業用水の汚濁の進行による農産物への生育障害など、多くの課題が発生しております。
また、農業用水の水質保全や農村生活環境の改善、公共用水域の水質保全など、活力ある農村社会の形成には、農業集落排水事業が最も効果的でありますが、近年では、市町の財政悪化に伴い、新規地区の減少傾向が続いております。
本県の農業集落排水処理人口の普及率は、生活排水処理構想の最終目標人口である183,400人に対し、44.8%の達成率で、これまでの取組により改善されてきたものの、未だ充分とは言えず今後も積極的な整備が求められています。
本協議会としても、設立目的達成のため、各種研修会等で啓発活動を行っておりますが、まだまだ遅れている状況であります。
つきましては、栃木県の重点施策に位置付けされている生活排水処理施設の整備・普及に向けて、農業集落排水施設のさらなる整備の推進について、特段のご配慮をお願いいたします。

| 農業農村整備事業推進に関する提案要望 関東一都九県水土里ネット協議会 |
関東一都九県土地改良事業団体連合会協議会は、去る10月23日と25日の両日に、平成18年 度秋季総会において決議した平成19年度国の農林施策に対する「農業農村整備事業推進に関 する提案・要望」を、それぞれ関東農政局及び農林水産省、財務省、総務省並びに関係国会 議員に対して行った。
なお、提案書は次のとおり。
提 案 書
[1] 現状と課題 (略)
[2] 事業推進に関する提案
1 農業農村整備事業の予算の確保と土地改良制度の確立
・ 農業構造改革の加速化、安全安心な食料供給
基盤の確保と地域づくりの推進を通じて、わが国農業の国際競争力の強化、国民生活の安 全安心の確保、環境の保全向上を図るのは国の責務であり、そのためこれらに直接裨益する 国営事業をはじめとする農業農村整備事業の必要な予算を確保されたい。
・ また、国民への食料の安定供給や食料自給率の確保に鑑み、農地の確保や基盤整備の推 進については、公的関与の拡大と国営事業制度の維持強化を図られたい。
・ 農業情勢の変化に沿って、農業農村の整備が円滑に図られるよう適切な土地改良制度の 確立を図られたい。
2 農業構造改革のための基盤づくりの推進
(1)担い手育成確保の契機となる農業生産基盤整備事業の重点的・計画的な推進
・ ほ場整備事業、かんがい排水事業、畑総事業等の推進
・ 低コスト整備手法の導入や、住民参加型手法の活用等、画一的な整備から弾力的整備へ の転換の推進
(2)地域資源の多面的機能を活かした総合的基盤づくりの推進
・ 地域の個性、創造力を生かした農業戦略や地域づくりを実施する元気な地域づくり交付 金の確保と拡充
3 地域の活力を活かした農村づくりの推進
(1)農業集落排水事業の推進
・ 農業用用排水の水質保全や農村生活改善及び地域資源循環の積極的な推進
(2)質の高い居住空間を形成するための田園空間整備事業の積極的な推進
・ アメニティ豊かな居住文化の創造は農村固有の特性であり、農村整備の技術的手法の確 立が必要である。
(3)都市交流を促進する農村環境保全整備の推進
・ 地場産品の販売、農業体験や自然環境を手段とする経済活動を興すため、生態系の保全 や農村景観さらには、歴史的風土を保全する取り組みを推進されたい。
4 土地改良施設の更新・管理に対する支援
(1)ストックマネジメントの技術的確立と予防保全対策の実施
・ 基幹水利施設から末端施設に至る一貫した保全管理シスムの構築のためには、施設劣化 の将来予測や予防保全対策に係わる仕組を早期に整備されたい。
(2)土地改良施設維持管理適正化事業の推進
・ 本事業は、土地改良施設の定期的な整備補修を行い、土地改良施設の機能の保持と耐用 年数の確保に資するものであり、事業予算の一層の確保や事業制度の拡充を図られたい。
5 農地・水・環境保全向上対策の推進
(1)地域共同活動組織に対する支援
・ 地方が長年に渡り要望してきた本事業が効率的・円滑に実施されるよう、地域協議会活 動の運営に対する支援や経理事務の簡略化さらには、対象活動項目の多様化と、実践活動に おける事業管理の簡便化を考慮されたい。
(2)地方負担に対する地方財政措置の実施
・ 本事業の実施に当たり、本事業が広範囲かつ円滑に実施できるよう地方負担分に対する 十分な財政措置を要望する。
6 土地改良事業団体連合会(水土里ネット)の体制強化の推進
(1)水土里ネットの特性を活かした体制強化への支援
・ 市町村、土地改良区等を会員とする水土里ネットは、行政と一体となって農業農村整 備を推進してきており、その計画、実施、施工、管理に必要な農業土木技術のみならず、農 業経営の改善、農地の利用集積、農村環境資源の保全、地域コミュニティの活性化など、多 数の分野にわたる技術や行政ノウハウを総合的、系統的に有しており、農業の発展、農業農 村の振興を図る上で不可欠な公的技術集団である。
・ 水土里ネットのこのような特性は民間に求めることができないことを事業の実施にあた り十分配慮されたい。
(2)水土里情報利活用促進事業の推進とGISシステム運用への支援
・ 本事業は農地の利用集積計画、施設の保全・更新計画、地域防災計画等の策定など、水 土里ネットの新たな展開方向を築くものであり、その予算確保と事業制度の拡充に努められ たい。
・ GISを利活用するためのメニューの創設
農地利用集積推進対策等すでに実施されている既存ソフト事業への導入や、ストックマ ネジメントが行なうデータ収集の管理等、新たな取り組みメニューの創設を図られたい。
(3)ストックマネジメントに対応する新たな土地改良施設管理センターの構築と支援
・ ストックマネジメントの効率的運用を図るためには、水土里ネットを地方の拠点とする 、土地改良施設管理センターとして構築することがより効果的である。ついては、土地改良 施設機能更新等円滑化対策事業の展開等、将来に対処する取り組みを推進されたい。
・ ストックマネジメントの推進のためには、施設状態の将来予測、予防保全対策工法の検 討、ライフサイクルコストの算定、最適運用計画の策定などが必要となることから、土地改 良事業団体連合会や土地改良区、市町村がこうした技術を修得することに対する支援を図ら れたい。
(4)農業農村整備事業に関する発注者支援機関の認定に対する支援
・ 公的な機関としての認定を推進するとともに、発注関係事務を円滑に進められるよう、 支援業務に対する支援策を講じられたい。
・ 市町村に対する品質確保法の啓発に努められたい。
| 県営土地改良事業換地業務感謝状贈呈式 |
県営土地改良事業の換地業務が完了した土地改良区に対する感謝状の贈呈式が、去る10月17日に栃木県公館において開催され、土地改良事業の円滑な推進に尽力並びに換地業務を地域の実情に応じて合理的に行うなど、他の模範であると認められ、換地業務を完了した次の13地区12土地改良区に対し、栃木県知事よりそれぞれ感謝状が贈呈された。
平成18年度感謝状贈呈の土地改良区の概要
※記載は管内順で、同一管内は採択年度順。敬称は略。
土地改良区名 理事長名 事務所
所在
市町村事業名 地区名 換地
区名面積
(ha)換地
処分
公告
年月日小倉北部
(現)上河内町
土地改良区長 島 義 明
(現)鈴木利光上河内町 県営圃場整備 小倉北部 − 185.1 H18.3.14 上田西芦沼
(現)上河内町
土地改良区高 木 和 善
(現)鈴木利光上河内町 県営圃場整備 上田西芦沼 1
2
3
427.6
78.7
186.1
32.7H14.9.10
H15.10.1
H18.7.4
H18.7.4永 野
土地改良区植 山 光 三 鹿沼市 県営圃場整備 永野 1
2
3
43.7
17.9
16.6
98.3H11.3.26
H13.12.4
H15.3.18
H17.10.11岩崎地区
土地改良区佐 藤 昭一郎 日光市 県営圃場整備 岩崎 − 107.5 H18.3.14 下沢引田
土地改良区福 田 三 男 鹿沼市 県営圃場整備 下沢引田 − 62.5 H17.6.7 山前中部
土地改良区日下田 圭 治 真岡市 県営圃場整備 山前中部I期
山前中部II期−
−125.5
239.7H17.9.20
H18.3.7市貝町
土地改良区小 塙 健 一 市貝町 県営圃場整備 桜川沿岸 − 104 H18.8.22 野 木
土地改良区荒 川 勝 夫 野木町 畑地帯総合土地改良 野木 − 127.2 H18.2.14 若佐南
土地改良区柿 沼 榮 進 野木町 県営圃場整備 若佐南 − 106.1 H17.6.14 船 生
土地改良区高 橋 孝 二 塩谷町 県営圃場整備 船生西部 1
218.5
75.3H17.10.19
H16.12.7金田北部
土地改良区渡 邉 好 男 大田原市 県営圃場整備 金田北部 − 174.2 H17.12.9 田沼町
土地改良区出 居 要 一 佐野市 中山間地域総合整備 田沼 1
2
310.1
10.2
5.8H18.9.5
H17.2.4
H18.9.5
小倉北部土地改良区
上田西芦沼土地改良区
永野土地改良区
岩崎地区土地改良区
下沢引田土地改良区
山前中部土地改良区
市貝町土地改良区
野木土地改良区
若佐南土地改良区
船生土地改良区
金田北部土地改良区
田沼町土地改良区
| 足利市の6土地改良区が合併予備契約書に調印 |
足利市の渡良瀬川左岸に位置する「足利市柳原用水」、「七ヶ村堰」、「足利市坂西用水」、「富田」、「尾名川沿岸」、「小俣」の6土地改良区は、去る9月15日、足利市民会館別館ホールにおいて、吉谷宗夫足利市長、金子友昭栃木県安足農業振興事務所長の立会いのもと、合併予備契約書の調印式を挙行した。6土地改良区は、それぞれ大規模な工事は完了し、土地改良施設の維持管理に移行しているため、組織のスリム化と事務経費の節減を図ろうと、平成17年3月に統合整備推進協議会を設置して合併を検討して来た。
調印式には、各土地改良区の役員等、約50名が出席。統合整備推進協議会長で七ヶ村堰土地改良区の鴇田光男理事長が、「合併により一層事務の合理化、経費の節減を図って行きたい」と挨拶した。続いて、出席者が見守る中、6土地改良区の理事長及び立会人により合併予備契約書の調印が行われた。続いて、来賓である吉谷足利市長、帆足章足利市議会議長及び金子所長並びに本会会長(代理:篠h総務部長)が祝辞を述べた。
今後6土地改良区は、それぞれ総(代)会において合併を議決し、同総(代)会において選任される14名の設立委員によって県知事あて認可申請が行われ、来年4月1日付けで「足利市わたらせ川左岸土地改良区」が誕生する見込みである。

統合整備の概要
旧改良区名 面 積 役員数 総代数 組合員数 事業概要 足利市柳原用水 39.4ha 11人 30人 252人 維持管理 七ヶ村堰 50.6 15 30 200 維持管理 足利市坂西用水 23.7 18 − 174 維持管理 富 田 231.8 24 55 546 維持管理 尾名川沿岸 94.7 19 30 273 維持管理 小 俣 31.8 10 − 134 維持管理 計 472.0 97 145 1,579 新土地改良区 471.8 15 40 1,579 維持管理
| 宇都宮市の田川水系8土地改良区が 合併予備契約書に調印 |
宇都宮市の田川水系「給分用水」、「雀宮南部」、「山田川下流」、「上金井」、「中島」、「田川中部」、「飯山上篠井」、「田川用水」、の8土地改良区は、去る9月29日、ホテル東日本宇都宮2階羽衣の間において、佐藤栄一宇都宮市長、小田部弘栃木県農務部参事兼河内農業振興事務所長の立会いのもと、合併予備契約書の調印式を挙行した。8土地改良区は、それぞれ大規模な工事は完了し、土地改良施設の維持管理に移行しているため、土地改良区の事業運営基盤を強化し、効率的な運営を図っていくために、平成17年3月に統合整備推進協議会を設置して合併を検討して来た。
調印式には各土地改良区の役員等、約50名が出席。統合整備推進協議会長で給分用水土地改良区の野中位徳理事長が、「合併により適正な施設の維持管理、運営基盤の強化を図って行きたい」と挨拶した。続いて、出席者が見守る中、8土地改良区の理事長及び立会人により合併予備契約書の調印が行われた。続いて、来賓である佐藤宇都宮市長、小田部栃木県農務部参事兼河内農業振興事務所長及び本会会長(代理:薄井参事)が祝辞を述べた。
今後8土地改良区は、それぞれ総(代)会において合併を議決し、同総(代)会において選任される8名の設立委員によって県知事あて許可申請が行われ、来年4月1日付けで「うつのみや中央土地改良区」が誕生する見込みである。

統合整備の概要
旧改良区名 面 積 役員数 総代数 組合員数 事業概要 給分用水土地改良区 314 21 50 498 維持管理 雀宮南部土地改良区 73 11 − 114 維持管理 山田川下流土地改良区 208 15 − 266 維持管理 上金井土地改良区 58 7 − 58 維持管理 中島土地改良区 142 13 − 212 維持管理 田川中部土地改良区 209 13 − 209 維持管理 飯山上篠井土地改良区 61 11 − 64 維持管理 田川用水土地改良区 365 11 38 513 維持管理 計 1,430 102 88 1,934 新土地改良区 1,430 25 49 1,734 維持管理
| 段本先生が那須野ヶ原を視察 大田原市で懇談も実施 |
全国水土里ネット顧問の段本幸男参議院議員が去る9月25日、大田原市において北那須土地改良事業推進協議会役員等と懇談した後、那須野ヶ原土地改良区連合を訪れて、小水力発電施設等を視察した。 大田原市においては、北那須土地改良事業推進協議会の加藤会長初め役員等との懇談会を開催し、国政報告や新たな農政の展開などについて講演した後、出席者と膝を交えての意見交換を行った。
出席者からは、「農政が大きく変化する中、土地改良関係予算が大幅に削減され、将来に不安を抱いている。農業・農村を守るための施策をしっかりとやってもらいたい。」などという意見が出され、段本先生は「新政権になっても、地方切り捨てなどということがないよう、言うべきことは言う。農業・農村に必要な公共事業は、しっかりと守らなければならない。」と答えていた。
その後、段本議員は、那須野ヶ原土地改良区連合を訪れて、星野恵美子事務局長から小水力発電についての説明を受けた。事務局長からの土地改良区等の今後の在り方などに関する意見・要望等を受け止め、全国初の開水路落差工用発電シムテムと小水力発電所等の現場を視察した。
北那須推進協議会役員と懇談する段本幸男参議院議員
水土里ネット那須野ヶ原星野局長から説明を受ける段本幸男参議院議員
| 全日本中学生水の作文コンクール |
私たちの毎日の生活を始め、農業や工業などの産業活動を支える重要な資源である水について、次代を担う中学生に日常の生活体験などから考えていただくことを目的に「全日本中学生水の作文コンクール」が、「水の週間」行事の一環として開催されました。この栃木県審査会において、優秀賞に輝いた高根沢町立北高根沢中学校3年加藤広佳さんの作品を紹介します。なお、国土交通省の行なった中央審査会においても見事入選を果たしました。
中央審査会入選
「市の堀用水の水」
高根沢町立北高根沢中学校
3年 加 藤 広 佳
「たんたん田んぼの高根沢」
これは私の町の歌の一節です。この歌詞からもわかるように、私の住んでいる高根沢町は水利の便に恵まれた坦々とした水田地帯が広がり、栃木県を代表する米どころとして名高い町です。しかし昔は、水に恵まれない、米作りをするのが大変な地域だったそうです。この事実を知ったとき、私は信じられませんでした。そこで、現在の町になるまで何が起こったのか、調べてみることにしました。
約350年前の春、「市の堀用水」という用水路ができました。それまでは、井沼川の水を利用して農業を営んでいましたが、水量の確保も容易でなく開田も難しかったそうです。そこで土室村の地頭山崎半蔵が、水量豊かな鬼怒川からの用水路を計画、多数の人足と十年の歳月をかけて完成したのです。当時は、道具などもなかなか手に入らず、作業のほとんどが人間の手によって行われたそうです。
その後、何度かの改良工事が行われ、延長43 km、受益面積約2300haの大用水路となりました。この用水路が通る地域は、県内でも指折りの米どころになっていることから、市の堀用水は大きな役目を果たしていることがわかります。私も、高根沢町が水に恵まれた地域になったのは、市の堀用水のおかげだったことがわかりました。
市の堀用水の歴史を知った私は、昔の人が手掘りでどれくらいの長さを掘ることができたのか、疑問に思いました。「延長43kmと本に書いてある用水の長さを見ても、長いのか短いのかピンとこなかったので、高根沢町から市の堀用水の旧取入口まで、用水沿いの道を、父の車でたどってもらうことにしました。
まず、自宅の一番近くに流れる市の堀用水を見ました。用水の幅はとても広く、水量も豊かで、ゴウゴウとうなりを立てて流れていました。私は父の車で、用水沿いの道を流れとは逆方向の、取入口に向かって走りました。昔と今の場所は違うらしいけれど、それでも豊かな水の原点を少しは知ることができると思ったからです。車は用水路沿いに桑窪、台新田、飯室と進んでいきます。ふと窓の外を見ると、たくさんの水田を見ることができました。そして出発して数分後、私たちの車は高根沢を出、隣のさくら市に入りました。もちろん、周囲には豊かな水田地帯が広がっています。
それからまたしばらくすると、市の堀用水取入口のある塩谷町に入りました。用水の幅は、私の町で見たときよりも狭くなっており、流れる水量も少なくなっています。少しして、私たちの車は、ついに用水の旧取入口があった場所に到着しました。ここまで来るのに、出発してから実に1時間、車はほとんど走りっぱなしでした。こんなに長い距離を、昔の人々はたった十年で掘ってしまったのです。たいした道具も使わず、ほとんど手掘りで……。私は、「すごい」の一言でしか表現できませんでした。
「市の堀用水」によって、私たちの町はもちろん、用水路が通る地域は、豊かな米作りをすることができるようになりました。市の堀用水がもたらしてくれた「水」が、現在の豊かな収穫をもたらしてくれたと言っても言い過ぎではないでしょう。現在は用水から水田に、簡単に「水」を手に入れることができますが、それを当たり前のことのように思ってしまってはいけないのです。用水路の開発に力を尽くした人々、用水路を毎日掘った人々など、多くの人々の汗と涙が流されたことを忘れず、感謝しなければいけません。
私たちの身近に存在し、私たちに豊かさをもたらしてくれる「水」。これからは、昔の人々に感謝しながら、「水」を大切に使いたいです。
| 全国「田んぼの学校」フォーラムinとちぎ |
社団法人農村環境整備センター主催による全国「田んぼの学校」フォーラムinとちぎは、平成18年10月21日、宇都宮大学多目的ホールにおいて、県内外から約200名の参加者を得て開催された。
田んぼの学校は、農村の自然を学び舎、遊びの場として活用し、農業や農村の伝統文化への理解を深め、食や環境に対する感性を高めてもらうのが狙いであり、様々な運営主体が水路で魚と遊んだり、田んぼの虫を調べたり、お米を作ったりと、それぞれの方法で活動している。
フォーラムの開会式は、午後1時に開会。農村環境整備センターの川嶋久義専務理事が主催者挨拶を述べた後、地元協力団体を代表して宇都宮大学農学部教授の水谷正一メダカ里親の会会長と、来賓として出席した福田富一栃木県知事が歓迎の挨拶を述べられた。
プログラム第1部の記念講演は、農と自然の研究所の宇根豊代表理事が「田んぼの学校にとりくむ理由」と題して講演し、「農業は生き物相手の仕事からどんどん遠ざかっているが、効率性以外のものがあり、それをどこかに残しておかなくてはならない。一つの知恵が田んぼの学校だ。」と訴えた。
第2部の地元団体の活動事例発表は、(1)NPO法人グランドワーク西鬼怒、(2)メダカ里親の会、(3)水土里ネット那須野ケ原、(4)志鳥倶楽部、(5)小山メダカの学校の順に、参加した子供達の体験感想を中心にそれぞれの活動状況を発表。他県から参加した団体からも活動事例の発表があった。
第3部のパネルディスカッションは、東京農業大学の守山弘客員教授がコーディネーターに、NPO法人くすの木自然館の浜本奈鼓専務理事がコメンテーターとなって進められ、地元団体の代表者の(1)NPO法人グランドワーク西鬼怒・藤井伸一氏、(2)メダカ里親の会・中茎元一氏、(3)水土里ネット那須野ケ原・星野恵美子氏、(4)志鳥倶楽部・小川正順氏、(5)小山メダカの学校・高瀬孝明氏がパネラーとなって進められた。後半では、会場の参加者とも直接意見交換を行うなど活発な議論となった。
会場を移しての情報交換会では、駆けつけた手塚照夫河内町長、野中英夫栃木県農務部長が歓迎の挨拶を述べ、大久保寿夫小山市長(本会副会長)が乾杯の音頭をとって、本県産の食材を中心とした料理と地酒を潤滑油に活発な交流を行った。
翌日の現地勉強会では、メダカ里親の会の活動拠点とNPO法人グランドワーク西鬼怒の活動拠点を訪れ、それぞれ視察・研修を行った。
| 「農業農村整備さなえまつり」を出展 ふるさと栃木フェア2006 |
本会は、去る10月28日から29日の2日間にかけて、宇都宮市のマロニエプラザ及び宇都宮市体育館を会場に開催された「ふるさと栃木フェア2006」に「農業農村整備さなえまつり」を出展した。
このフェアは、県内各地の創意工夫を凝らした地域活性化の取組を紹介するとともに、各地の特産・名産品を一堂に集め展示・販売するほか、本県の豊な食と農に関する情報を発信するとともに、県内の豊富な観光資源を広く県民に紹介することを目的に栃木県の主催で開催しているもので、今回で16回目を数える。
フェアには、期間中、約8万人の県民が訪れ、参加者は市町毎の物産店や農産物直売所での買物、各種の試食会、イベントなどで、今年のキャッチフレーズ「おいしい“とちぎ”たのしい“とちぎ”みんなの“とちぎ”」を楽しんだ。
今回のフェアにおける本会の出展内容は、いのち・循環・共生をテーマに農業農村の持つ多面的な魅力を情報発信し、農業農村整備事業と土地改良区の役割をPRするため各種コーナーを設置し、来場者に対して特に環境及び生態系に配慮した農業農村整備事業をアピールするとともに、土地改良区の果たしている役割などについて啓発を行った。
出展コーナーの一つ、水田周辺の水域に生息する身近な魚や水生昆虫などを展示した水槽コーナーでは、「田んぼまわりの生き物たちの名前当て」と銘打ったクイズを行ったことや、イモリやカエルの両生類、ゲンゴロウ、タイコウチ、ミズカマキリなどに触れることができることもあって予想以上に多くの子ども達の興味を引くことができた。また、大人達には、子どもの時に遊んだ田んぼの生きものの記憶に生態系に配慮した農業農村整備事業に関心が寄せられ、水路と田んぼを往来するためのドジョウ水路の製作や設置に関する質問が寄せられるなど、一定の成果を実感することができたイベントとなった。
| 農業基盤整備資金の金利改定 |
平成18年9月21日付で、農林漁業金融公庫の農業基盤整備資金の貸付利率が次のとおり改定されました。
なお、借入時の金利は、金融情勢により変動しますので、最新の利率は最寄の農林漁業金融公庫にご確認ください。
区 分 現 行 改 定 補助事業 県 営 2.25% 2.05% 団体営 2.10% 1.90% 非 補 助 一 般 2.10% 1.90%
| 「みかもの里ウォーキング」 |
去る9月30日、大岩藤土地改良区と栃木県21世紀土地改良区創造運動推進本部は、一般県民から募集した親子づれなど105名の参加を得て「みかもの里ウォーク」を開催した。
開催の趣旨は、地域住民とりわけ非農家の人々に余暇を利用したウォーキングを通じて、風光明媚な景観と自然の豊かさに触れながら、万葉集に詠われたみかも山の東麓に開けた岩舟町下津原地内の農業水利施設と郷土に伝承される歴史を訪ね、先人達の苦労と偉業伝統文化などを肌で感じてもらおうというもの。
大岩藤土地改良区の永島明理事長は、主催者挨拶の中で「みかも山は、万葉の昔から歌に詠まれた自然豊な地域であるとともに世界的偉人の慈覚大師を生んだ地域でも有ります。また、この地域は、長年水不足に悩まされてきたが、県営の圃場整備とかんがい排水事業の完成によって解消し、安定的な営農が可能となった。本日は、このウォーキングを通じて、土地改良施設の役割を認識していただき、理解を深めて頂きたい。」と述べられた。
次いで、栃木實岩舟町長は、「岩舟町は、地理的有利性を活かし、首都圏農業を展開しており、本年4月には、地域農業の中核施設としていわふねフルーツパークを開園した。豊富な種類と豊かな味覚がありますので、存分に楽しんでいってください。」と歓迎の挨拶を述べられた。
ウォーキングは、いわふねフルーツパークからみかも山公園を出発し、同公園内のあじさいの路を通り、国道50号沿いの道の駅「みかも」で休憩を兼ねて見学した後、折り返しみかも山東麓の田園地帯を北上、途中大岩藤第二揚水機場までの中間点で、改良区の準備した、地元岩舟町の特産品を素材とした20種類以上もあるというジェラードアイスクリームが参加者に振舞われ、額をつたう汗を拭いながら、アイスクリームを頬張りしばしの涼をとった。一行は、大岩藤土地改良区の事務所に到着し4班に分かれて、事務所前で、岩舟山を背景に記念写真をとり、事務所に隣接する第二揚水機場の前で、山崎事務局長からこの地域の営農の状況、事業概要の説明を受けた。ライシャワー米国駐日大使が訪れた慈覚大師円仁誕生地に立ち寄って、大岩藤土地改良区の役員でもある永島秀男氏から由来等の説明を受け、地元が生んだ世界的偉人の遺徳を偲ぶとともに、この地の歴史や文化に想いを馳せた。
ゴールでは、先ほど撮影された記念写真が手渡されたほかに、抽選で10名の参加者に特産品のぶどうがプレゼントされ、土地改良区の粋な計らいに当選した参加者からは笑みと歓声がこぼれた。
全行程が8.9kmのコースでもあって、天候にも恵まれ、残暑の残るやや汗ばむ陽気の一日で、熱中症も心配されたが、全員が完走し、清々しい一日を満喫した様子であった。
| 平成18年9・10月主要行事報告 |
9月
日 行 事 1 安足土地改良事業推進協議会農業農村整備事業研修会 4 都道府県水土里ネット事務責任者会議 14〜15 栃木県土地改良事業団体連合会OB会第8回通常総会 15 足利市わたらせ川左岸土地改良区合併予備契約書調印式 15 関東ブロック水土里ネット協議会第2回事務責任者会議 15 平成18年度関東農地集団化推進協議会第2回幹事会 19 栃木県担い手育成総合支援協議会第2回幹事会・事務局員合同会議 22 農地・水・環境保全向上対策説明会 26 平成18年度第1回農業農村整備部会 29 田川水系土地改良区合併予備契約書調印式 30 みかもの里ウォーク
10月
日 行 事 2 平成18年度利根川水系農業水利協議会第1回研究会 3〜4 換地処分実務研修会並びに換地計画作成研修会 6 換地関係異議紛争処理対策専門委員会 6 第15回農業集落排水事業技術検討会 8 平成19年度新規採用職員一次試験 10 第29回全国土地改良大会 京都大会 11 「農地・水・環境保全向上対策」技術研修会 16 平成19年度県農林漁業施策・予算に関する建議・要請会 17 県営圃場整備事業平成17年度換地処分地区表彰 17 平成19年度予算概算要求等に係る説明会 18 とちぎの食を考える集い 19 栃木県水田農業推進協議会米政策改革担当部課長会議 19〜20 平成18年度基幹水利施設管理技術者育成支援事業研究会 19〜20 関東ブロック水土里ネット協議会秋季総会 21〜22 全国「田んぼの学校」フォーラムinとちぎ 23 平成19年度国の農林施策に対する提案・要望 25〜26 平成18年度栃木県河宇土地改良協議会先進地研修 26〜27 平成18年度栃木県農村総合整備事業促進協議会先進地視察研修 28〜29 ふるさと栃木フェア2006 28〜
11月3日首都圏イベント『水土里の体験展’06』 29 とちぎ夢大地フォーラム2006 30〜31 疏水サミットinあおもり2006
| 表紙写真説明 |
表紙の写真『棚田の収穫』
○撮影者
鈴 木 三 朗 氏
(芳賀郡茂木町在住)
○撮影地 芳賀郡茂木町
○コ メ ン ト
平成17年度「美しいとちぎのむら写真コンテスト」農村のくらしと文化部門で最優秀賞に輝いた作品です。
審査員講評は、「秋の取り入れの風景がよく捉えられ、画面から柔らかな空気が伝わってくる作品です。棚田の湾曲した曲線とそこに働く人々の様子が捉えられて、画面に動きと奥行きを出しています。
また、稲穂の黄色が左右にバランスよく配置され、写真の構成にも優れています。」というものでした。