 |
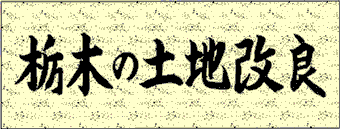 |
『水土里ネットとちぎ』は本会の愛称です

−主な内容−
 |
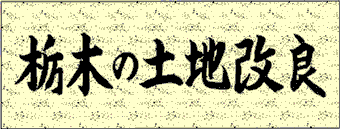 |


新年のごあいさつ 水土里ネットとちぎ
(栃木県土地改良事業団体連合会)
会 長 後 藤 伊 位
会員の皆様あけましておめでとうございます。
今年も皆様とともに、新しい年を迎えることができました。心からお慶びを申し上げます。
昨年を振り返ってみますと、明るい話題が少なかったように思います。国際的には、北朝鮮による核実験やミサイル発射実験など、国民を震撼させる事件を初め、中東のイラクでは、未だに混迷から脱することができないでおります。農業関係でも、WTO農業交渉が農産物輸出国と輸入国間の意見が対立して、事実上決裂してしまいました。
国内におきましても、いじめを原因とする子供達の自殺事件や飲酒運転による悲惨な事故のニュースが新聞のトップを飾っていました。景気につきましては、回復基調を継続しているというものの、私達国民にとっては、全く実感が湧いて参りません。農業関係でも、本県では低温と日照不足の日々が7月下旬まで続き、米の作柄が不良になってしまいました。全国的にもやや不良という状況であったにも拘わらず、需要が減少したため、価格が低迷する中で、さらに生産調整量を増やさなければならないという厳しい現実を突き付けられております。
昨年9月に誕生した安倍新内閣には、美しい国づくりをスローガンに掲げておられますので、是非とも、地方或いは農業・農村に目を向けてもらいたいと切に願うものであります。
さて、平成19年度国の予算につきましては、小泉前内閣の構造改革路線を引き継ぎ、引き続き公共投資関係費を削減する方針の中で、昨年末に決定された政府案では、農業農村整備事業費は対前年比92.7%の6747億円でありますが、農地・水・環境保全向上対策のうちの共同活動支援交付金の256億円が非公共予算へシフトされたことに伴い、これを含めると約96.2%と実質的な予算が確保されました。この上は、次期通常国会におきまして速やかに成立し、適時・的確な予算の執行が図られることを期待するものであります。
農業・農村は、安全で安心な食料を安定的に供給するとともに、豊かな自然環境や良好な景観の保全・形成などの多面的な機能を発揮することにより、日本という美しい国をかたちづくり、国民の生活を支えております。
その根源たる「水」「土」「里」は、先達のたゆまざる努力により育まれたものであり、これらの財産を守り、次世代に適切に引き継いでいくことが、農業農村整備に携わる私達の責務であります。
農業農村整備につきましては、「食料・農業・農村基本法」の理念に即し、環境との調和に配慮しつつ、既存ストックの有効活用を重視した保全管理、農業の構造改革の加速化に資する生産基盤の整備、地域再生に資する活力ある美しいむらづくりの推進など、新たな時代に対応した使命を担う農業農村整備を強力に推進して参りたいと存じております。
末筆ながら、私共連合会は、適正な業務運営に努めつつ、国並びに県の施策に呼応しながら、会員皆様の負託に応えるよう誠心誠意努力して参りたいと存じておりますので、より一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
会員皆様のご健勝をご祈念申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ 栃木県知事 福 田 富 一
県民の皆様、あけましておめでとうございます。
私は知事就任以来、県民誰もが豊かさを実感できる“とちぎ”を創り上げていくため、対話と協調による県民中心、市町村重視の県政運営を基本として、各種施策を積極的に展開して参りました。
その結果、昨年は、子どもに対する医療費助成の小学3年生までの拡大や3歳未満児への現物給付の導入、新たな発想で住民と市町村が協働して取り組むまちづくり活動を支援する「わがまち自慢推進事業」の創設など、元気で活力ある“とちぎ”づくりのための各種施策を市町村と連携して進めることができました。
今年は就任3年目を迎えますが、常に県民の皆様の声に耳を傾けながら、昨年策定しました総合計画「とちぎ元気プラン」の目標達成に向け、全力を挙げて取り組んでいく決意を新たにしたところです。
現在、少子高齢化の進行や本格的な人口減少時代の到来等が経済や社会に様々な影響を及ぼすと懸念される中、地方自治体においては、財政の健全化や行政改革の推進、さらには医療福祉の充実、安全安心のまちづくり等多様化するニーズへの対応など、様々な課題を抱えております。
今後とも社会の活力を維持し、県民生活の質的向上を図っていくためには、県民一人ひとりの個性や能力をはじめ、自然や文化、産業基盤など、本県の優れた資源を活かし、飛躍の可能性を最大限に引き出しながら、県民や市町村との信頼と責任あるパートナーシップのもと、私たちが直面する課題の解決に向けて、勇気を持って果敢にチャレンジしていかなければなりません。
このため、今年は、県庁組織の大幅な改編を行い、県の政策形成機能を担う総合政策部や県民生活に関する施策を総合的に推進する県民生活部を創設するなど、組織横断的な課題等へ迅速かつ的確に対応できる体制を整えることといたしました。
また、結婚や子育てを社会全体で支援する取組を新たに実施するなど少子化対策を強化するほか、団塊の世代の豊富な知識や経験を地域の活性化に活かす「団塊の世代に着目した“とちぎ”の元気づくり」に着手するとともに、深刻な社会問題ともなっております、いじめや自殺対策等に積極的に取り組んで参りたいと考えております。
県民の皆様におかれても、「新たな“公”を拓く」という考え方に立ち、それぞれの立場や垣根を乗り越えて、郷土の課題の解決に向けて協働して取り組んでいただけることを期待しております。
私は、今年をさらなる飛躍の年とするために、「いいひと いいこと つぎつぎ“とちぎ”」を合言葉として、県民の皆様と手を携え、元気で活力ある“とちぎ”の実現のため最大限の努力を傾注して参りたいと考えておりますので、より一層の御理解と御支援をお願い申し上げます。
年の始めに当たり、私の所信を申し上げますとともに、本年が皆様にとって素晴らしい年となりますことをお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

「美しい国、日本」を目指して 参議院議員 佐 藤 昭 郎
水土里ネットとちぎ の役職員ならびに会員の皆様、2007年あけましておめでとうございます。御家族そろっての穏やかな正月を迎えられたことと拝察申し上げます。
まず、旧年中は土地改良をめぐる内外の情勢が非常に厳しい中、常日頃の御尽力、御協力に心から敬意と感謝を申し上げる次第です。
さて、昨年は小泉内閣から安倍内閣へ政権交代が行われる中、我国経済は全体として、いざなぎ景気を超える長期好景気を持続しました。しかし、「いざなぎはこんな不景気だったのか」と川柳にあるごとく、地域、業種、企業規模等によって偏りのある状況で、農村地域や農業分野においては景気の実感はまさにまだら模様となっています。このような中で2007年を迎えるわけですが、国政は1月中旬召集予定の第166回通常国会で本格的に始動します。内政、外交とも重要課題が山積していますが、これに取り組む政府、与党の大きな柱は安倍総理の掲げる「美しい国、日本」です。これを実現する具体的戦略が我国の経済活力を維持しながら、国民生活を豊かにし、国・地方の財政再建を図るための「経済成長戦略」です。グローバル化の中で、引き続き我国が世界における大競争時代を勝ち抜くためには、経済・社会のあらゆる分野での改革・効率化を図ること以外に妙手はないことを確認したわけです。
このような大きな流れの中で、食料・農業・農村分野も例外たりえません。いやむしろ、中央と地方格差解消、経済成長と環境の両立など「美しい国、日本」を目指すためには、農業農村分野が元気を持つことが必須であり、その具体的なツールとしての土地改良、農業農村整備の役割は極めて重大です。また、昨年の臨時国会において成立した「教育基本法改正案」や「防衛庁省昇格法案」に現れていますが、安倍内閣になり、国政においては戦後60年を経て政府・与党の中に「この国のかたち」の基本を問う大きな流れができてきました。1億2千万の人口を持つ我国が独立国としての誇りと安全・安心な国民生活を目指すためには食料供給力の維持、向上が必要条件です。具体的に政策を実行していくためには地方財政問題やWTO、EPA/FTA交渉など大きな困難がありますが、2007年が正念場であり、現場・行政・政治が連携して取り組めば道筋が見えてきます。
私自身も皆様方との情報交換を密にしつつ、国政の場において全力を尽くす所存です。最後に、今年は7月に参議院選挙が行われます。政策決定システムにおける政治主導の流れが強まる中、我々が主体的に改革をリードしていくためには、土地改良の「政治意志」の結集が重要だと考えます。皆様方の一層の御協力、御指導、御鞭撻を祈念致し、私の新年のあいさつと致します。

本もの転換『百年の大計』 参議院議員 段 本 幸 男
明けましておめでとうございます。清々しいお正月をお迎えのことと思います。
昨年は、5年半に及んだ小泉内閣から、戦後生まれの安倍総理に政権交代されました。多くの国民が、これまでとはまた違った新しい変革を期待しているところです。外交面では、身近な脅威となった北朝鮮の核実験への的確な対応、内政面では、格差社会が広がる中この是正、さらにはいじめをはじめとする教育問題への早期の対応など、大きな課題が目白押しです。
昨年はその助走期間でしたが、今年はこれらをどのように具現化していくのか、その成果が問われる年となります。しかも今年は、農政がこれまでの価格支援から所得支援へ、かつてない大改革が進められようとする年でもあります。
わが国が、『人口減少』という、かつて経験したことのない時代に入り、このままでは『むら』が消えてゆくということも決して他人事でない危機が迫っています。悪くすれば全国の農家が『共倒れ』になることも予想される事態となっています。
が、他方では、安倍総理が『美しい国づくり』を標榜するように、今まだ残された都市にはない農村の『コミュニティー』に期待が集まっていることも事実です。教育問題や環境問題にみるまでもなく、日本再生のためには、都市再生だけでなく農村再生が車の両輪となって初めてそれが可能となるのです。
こうした中で求められているのは、10年先、15年先を見越した『むらの展望』なのではないでしょうか。美しい村が荒れないように、政治が、行政が、そして村の人たちが何をしなければならないのか。私はそこに、100年先までも見通した農地制度の改革がなければ、19年度の改革だけでは決してうまくいかないと考えます。本当の農業の活力を引き出すためには、また国民すべてが望む「最低限50%以上の食料自給率を確保することが国の責務」を実現するためには、100年通じる『国の大計』が必要だと考えるのです。
そしてそのもとに、土地改良はどのような役割を果たしてゆくのか。おそらく歯車の形も、そして大きさも、これからの時代に合ったものへ変えていかなければ、決してその役割を担ってゆくことはできないと思います。変革の時代、自らもその意識を強く持たないと生き残りは叶わないのです。
求められている新たな展望が、少しずつ動き出しています。バイオエタノールなどの環境とリンクする土地改良。農地の証券化など、都市の資本を呼び込む制度の確立と圃場整備の連携。歯抜け状態の集落を、超長期視点で『集落再編』するなど。さまざまなことが考えられます。
これまでにない発想で、21世紀に翔ばたく農村再生に向け、土地改良がその原動力となろうではないですか。平成19年が、そのような土地改良改革元年になるよう、みなさまとともにがんばりたいものです。私にとっても選挙の年。改革のためにもその勝利に全力を上げたいと思っています。

新年のごあいさつ 栃木県農務部長 野 中 英 夫
新年あけましておめでとうございます。
皆様には、平成19年の輝かしい新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。また、昨年中は、県農政の推進に深い御理解と御協力をいただきましたことに、厚くお礼申し上げます。
今日の農業・農村は、食料自給率の低迷、農業従事者の高齢化、さらには国際化への対応など、多くの課題を抱えています。また、安全・安心な食料供給はもとより、消費者の視点を一層重視する環境に配慮した農業の展開なども求められており、大きな変革期を迎えています。
このような中、国では経営所得安定対策として「品目横断的経営安定対策」と「米政策改革推進対策」を表裏一体とし、「農地・水・環境保全向上対策」を車の両輪として、いよいよ平成19年度から、戦後農政の大転換とも言える施策が始まろうとしています。
県においても、こうした動向を踏まえ、「首都圏農業の新たな展開」を図り、農業・農村の更なる活性化と健康的で豊かな食の提供などを目指して、農業者を始め、関係団体、消費者、行政など県民の皆様の相互連携と協働の下、本県の持つ優位性を積極的に活かした「攻めの農政」を展開するため、「とちぎ“食と農”躍進プラン」を策定し、平成18年度から取り組みを始めているところです。
また、農業農村整備事業につきましても、この部門計画として「とちぎ水土里づくりプラン」を策定し、農業構造の改革に向けた生産基盤の整備を始めとして、生産を支える農業用施設の維持・保全、元気で個性豊かな農村の形成、自然と調和した農村環境の保全、さらには快適でうるおいのある農村生活環境の整備を図り、豊かな地域資源を活かした魅力あふれる農村づくりに、積極的に取り組んでいるところです。
これからの食料の安定的供給、農業の持続的発展、農村の振興を図るためには、農業農村整備事業の果たす役割が依然として重要でありますので、今後とも皆様方の一層の御支援と御尽力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、皆様方の御健勝とますますの御発展を心から祈念申し上げまして、年頭のあいさつといたします。

新年のごあいさつ 栃木県農務部技監
大久保 幸雄
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、新年を清々しい気持ちでお迎えのこととお喜び申し上げます。
また、常日頃から農業農村整備事業の推進を通しまして、本県農業の振興にご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今日の農業・農村は、経済のグローバル化が急速に進むなかで、農業従事者の減少、高齢化、食料自給率の低迷、さらに農業の構造改革の立ち遅れ、農村地域の活力低下や地域資源の保全管理の支障等様々な課題を抱え、これらへの対応が求められているとともに、安全・安心な食料の安定供給はもとより、自然環境の保全や環境を重視した農業生産など、農業・農村への期待や要請も高まってきています。
このような中、国においては平成19年度から導入される経営所得安定対策に係る「農政改革関連三法」が昨年6月に成立し、同じく7月には「経営所得安定対策等実施要綱」が省議決定されたところであり、これにより、これまですべての農業者に対して品目別に講じられてきた価格政策を、支援の対象者を農業の「担い手」に限定して品目横断的な所得政策へと転換するなど、戦後農政の大きな転換点を迎えたわけであります。
県においても、昨年、これまで取り組んできた首都圏農業の確立をさらに進め、「創意工夫と意欲に富んだ農業の確立」、「活力ある美しい農村の創造」、「健康的で豊かな食の提供」の実現など、農政全般の着実な改革による「首都圏農業の新たな展開」をめざして「とちぎ“食と農”躍進プラン」を策定したところであります。
また、その部門計画として「とちぎ“水土里”づくりプラン」を策定し、本プランに基づき本県の豊かな地域資源を県民共通の財産として見直し、県民が協働して保全・継承していける社会の形成に努め、自然環境の保全や農村の活性化などの要請に対応しながら、農業生産基盤や生活環境施設の整備を推進し、本県農業・農村の更なる発展をめざして参ります。
さらに、19年度からは「経営所得安定対策」の3本柱の一つであり、「品目横断的経営安定対策」と車の両輪をなす「農地・水・環境保全向上対策」が4月から実施されます。本対策は、農業の持続的発展と多目的機能の健全な発揮を図るための基盤となる農地・水・環境の良好な保全と質的向上を、農業者はもとより地域ぐるみで行う共同活動等に支援するものであり、本県農業・農村における生産資源や環境資源の維持・保全に大きく寄与するものであり、着実に進めてまいりたいと考えております。
これら対策等の推進にあたりましては、貴連合会をはじめとする関係機関の皆様との連携がますます重要となりますので、より一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
最後に、皆様方のご多幸とご健勝をお祈りいたしまして、新年のあいさつといたします。

新年のご挨拶 栃木県農務部農村振興室長
大 塚 国 一
新年明けましておめでとうございます。
皆様方には、ご家族と共に健やかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
また、日頃より農業・農村整備事業をはじめ県農政の円滑な推進に格別のご支援、ご協力をいただいておりますことに、心からお礼申し上げます。
さて、農業・農村を取り巻く情勢につきましては、国から、担い手に施策を集中する品目横断的経営安定対策、これと表裏一体の関係にある米の生産調整支援対策、さらに、これら産業対策と車の両輪となる地域政策としての農地・水などの資源や環境の保全向上を図るための対策が示され、本年から、新たな農業・農村施策が本格的に実施されることとなります。
このような中で、県におきましては、本県農業・農村振興の基本的方向とその実現に向けての具体的施策を明らかにした「とちぎ食と農躍進プラン」を策定したところであり、農村の持つ豊かな地域資源の活用や都市住民との協働等を通した活力ある農村づくり、さらには健康的で豊かな食の提供を通した県民生活への貢献など、攻めの農政により、元気で活力のある「とちぎの農業・農村」の実現を図ってまいります。
特に、当農村振興室におきましては、「とちぎ食と農躍進プラン」に掲げる施策を着実に展開するため、都市と農村の交流基盤の整備を促進するとともに、これまでに整備された農産物直売所や農村レストラン等の施設の有機的な連携充実を図りながら、団塊の世代の受入促進などの新たな視点も取り入れて、都市との交流・協働を進め農村地域の活性化を図ります。
また、社会全体において環境に配慮した循環システムが重視される中、農業においても、家畜排せつ物などの動物や植物の多様な有機性資源の有効活用や農業生産活動により発生する廃棄物の減量化、リサイクルなどが求められています。このため、家畜排せつ物等をメタン発酵させることにより発生するバイオガスを発電等に利用するバイオガスシステムの実証試験を行い、バイオガス発電を核としたバイオマス循環利用システムの確立等を推進します。
さらに、条件が不利な中山間地域では、過疎化や高齢化などから、従来農村が持っていた集落機能が低下し農業・農村の多面的機能の維持・保全が困難になってきています。このため、安全で快適な暮らしを実感できる生活環境の整備と生産基盤の整備を一体的に進めるとともに、多様な地域活動や鳥獣害対策など中山間地域への総合的な支援を行います。
今後とも、自然豊かで住み良い農村の形成をめざし、農村の様々な地域資源を活かした地域づくりや快適な生活環境の整備等、各種施策を総合的に推進して参りたいと考えておりますので、会員の皆様の一層のご理解とご支援をお願いいたします。
結びに、会員の皆様のご健勝と栃木県土地改良事業団体連合会の益々のご発展をご祈念申し上げまして新年のごあいさつといたします。

新年のご挨拶 栃木県農務部農地計画課長
細 岡 求
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、輝かしい新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
また、日頃から本県の農業農村整備事業の円滑な推進のため特段のご協力とご尽力をいただき、心からお礼申し上げます。
最近の農業・農村をめぐる情勢は、担い手の減少・高齢化、耕作放棄地の拡大や食料自給率の低下、国際化への対応、さらには、食の安全・安心への関心、農業構造の改革や地域農業の活性化、環境を重視した農業生産など、大きな転換期を迎えています。
一方、農業・農村は、農業生産や農地・農業用水等の資源の保全等を通じて、食料を安定的に供給し、国土や自然環境の保全、いやしの場の提供、文化の伝承等の様々な機能を発揮し、持続可能な社会を構築する上で、不可欠な役割を担っており、農業・農村への期待が大きくなっています。
このような情勢の中、国では新たな「食料・農業・農村基本計画」(17年3月)や「21世紀新農政2006」(18年4月)に基づき施策の集中・重点化を図り、国内農業の体質強化と「攻めの農政」に取り組んでいるところであります。
県においても、農政全般の着実な改革による「首都圏農業の新たな展開」をめざし、平成18年度を初年度とする「とちぎ“食と農”躍進プラン」とその部門計画として「とちぎ“水土里”づくりプラン」を策定したところであります。
平成19年度は、戦後農政を大きく転換することとなる「経営所得安定対策」がスタートする年であり、「品目横断的経営安定対策」と車の両輪をなす「農地・水・環境保全向上対策」が4月から実施されますので、この対策の着実な取組を進めるとともに、2年目を迎えるプランの着実な推進を図るため、地域の実情に即した効率的で効果的な農業農村整備事業の計画、土地改良施設の適切な維持・保全やこれら施設等を管理している土地改良区の育成強化、さらには計画的な土地利用による優良農地の確保など、豊かな地域資源を活かした、魅力あふれる農村づくりを重点施策として推進して参ります。
これらの推進にあたりましては、土地改良区をはじめとする関係機関の皆様との連携がますます重要となりますので、より一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
最後に、「水土里ネットとちぎ」の益々のご発展と皆々様のご健勝をお祈りいたしまして、挨拶といたします。

新年のごあいさつ 栃木県農務部農地整備課長
粂 川 元 一
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には平成19年の新年を清々しい気持ちで迎えられたことと心からお慶び申し上げます。
皆様方には、日頃より農業農村整備事業の推進につきましてご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。
我が国の食料・農業・農村をめぐる情勢につきましては、担い手の減少や高齢化の進行、食の安全・安心への対応など様々な課題に直面しております。
平成17年3月に策定された「食料・農業・農村基本計画」に基づき、日本農業の構造改革の推進や国際競争力強化のため同年10月に経営所得安定対策等大綱が決定されました。大綱は「品目横断的経営安定対策」「米政策改革推進対策」「農地・水・環境保全向上対策」の三つの柱からなっており、農業農村整備事業関係では3番目の対策が重要な柱であり、18年度中にモデル的に検証を行い4月から本格的に保全管理などの施策が展開されることとなります。
県におきましては、平成18年度を初年度とする県総合計画である「とちぎ元気プラン」、農業振興計画である「とちぎ“食と農”躍進プラン」及び農業農村整備事業推進計画である「とちぎ水土里づくりプラン」に基づいて各種の施策推進を図っているところであり、平成19年度農業農村整備事業予算につきましては、県の厳しい財政事情のなかで編成を進めており、事業実施について厳しい状況が予想されますが、メリハリある予算執行により「担い手等の経営体を育成するほ場の整備」と「かんがい排水事業」や「農道事業」の早期完成に努めて参りたいと考えております。
とくに、経営体育成基盤整備事業(ほ場整備事業)につきましては、品目横断的安定対策に対応するため新たに制度拡充された「農業経営高度化支援事業(ソフト事業)」に積極的に取り組んで担い手の育成と農地集積を図ることとしています。
また、将来にわたる食料の安定供給を確保するうえで、重要な役割を担う既存の基幹的農業水利施設の長寿命化を図るため、施設の機能診断及び劣化の状況に応じた適切な対策を行う農業水利施設保全対策事業に本年から着手したいと考えております。
今後とも、会員の皆様や地域の皆様と地域農業のあり方や展開方向について議論を重ね、今やるべきことにしっかりと対応して参りたいと考えておりますのでご協力をお願いいたします。
結びに、皆様のご多幸・ご健勝を心からお祈り申し上げ新年のあいさつといたします。
| 疏水サミットinあおもり2006が開催 |
昨年の10月30日・31日の2日間、第1回疏水サミットが青森県十和田市の奥入瀬渓流グランドホテルにおいて、全国各地で疏水を維持管理する水土里ネットの関係者など500余名が参加して盛会に開催された。
「水土里(みず・つち・さと)育む疏水」をテーマに開催されたサミットは、まず、基調講演において、林良博東京大学大学院教授が「疏水に期待するもの」と題して講演を行い、「疎水は、世界に誇れる観光資源でもあり、水は世界的に不足していて石油よりも貴重な時代にある」とし、「美しい農村の景観と国土を守るという視点から保全活動を国民的運動にしよう」と提言した。
次に、疏水を管理する水土里ネットを代表し、水土里ネット稲生川・米田安典工事課長、水土里ネットほっかい・林徹参事、水土里ネット那須野ケ原・星野恵美子事務局長の3名から、それぞれの疏水の概要、歴史、魅力及びその魅力を伝える21創造運動の活動等の事例が紹介された。また、地元青森県からは、若松賢子青森県農林水産部農村整備課技師から、県独自の取り組みとして、農業用水利施設が果たす役割や周辺の地域情報を広く発信する「あおもり水辺の郷」の事例が紹介された。
続いて、パネルディスカッションでは、林教授をコーディネーターに、新渡戸明十和田市立新渡戸記念館館長、中山洋子(株)リクルート総務部、永田麻美まちむら交流きこう「びれっじ」編集長、中條康朗農林水産省農村振興局次長の4氏がパネラーとして参加し、疏水によって育まれた歴史・文化・風土・生活・技術・観光と多彩な意見交換が行われた。最後に、林氏が議論を総括し、「ふるさとの資源は、水と土が根本であり、これをどう継続的に守っていくかが大切である。」と締めくくった。
2日目の現地研修は、「三本木原(現十和田市一帯)開拓」の原点でもある稲生川の視察が行われた。同河川は、旧五千円紙幣の肖像で知られる新渡戸稲造の祖父にあたる旧南部藩士新渡戸傳を中心に1855年に工事着手され、傳の長男十次郎、孫七郎の三代によって1871年頃までに11kmに及ぶ水路が開削され、その後も開拓事業は地域の人々によって受け継がれ、太平洋岸までの水路が完成した。三本木原台地は、火山灰台地であり、ここに水路を開削し農業用水を導水し、不毛の台地を緑豊かな大地とした先人達の情熱と努力、それを可能とした当時の農業土木技術の高度なことに、感嘆させられた。これらを地域資源として後世に継承していくべく、地域住民が一体となって保全に取り組んでいる状況は、地域コミュニティの創造の一助となっているようである。
また、サミット開会に先立ち、「疏水ネットワーク設立総会」が開催され、正会員として登録された地域水土里ネット及び都道府県水土里ネット、特別会員である都道府県など多くの関係者が参加し、盛会のうちに行なわれた。総会は、役員に理事17名、監事2名を決定し、初代会長として青森県の水土里ネット稲生川・熊野清市理事長を選任した後、「疏水ネットワーク会則」、「平成18年度事業計画」及び「平成18年度収支予算」を議決し閉会した。なお、本県からは、理事に水土里ネット那須ヶ原が選任された。


| 農業農村整備の集いに全国の関係者が参集 |
全国水土里ネット(会長・野中広務水土里ネット京都会長)は、11月6日、東京都千代田区平河町の砂防会館「シェーンバッハ砂防」において、来賓に国井正幸農林水産副大臣はじめ、佐藤昭郎、段本幸男参議院議員ほか多数の国会議員、農林水産省から山田修路農村振興局長等を招き、全国の土地改良関係者約千人を集めて「農業農村整備の集い」を開催した。
集いは定刻に開会し、全国から255点の応募のあった「ため池のある風景」写真コンテストの表彰式が行われた。また、講演の部では、日本青年館結婚相談所長の板本洋子さんによる「結婚問題からみる農村と女性」と題した講演が行われた。板本さんは、1969年(昭和44)に日本青年団協議会に勤務し、1980年(昭和55)から結婚相談所設立と同時に専務。1984年(昭和59)に所長となり現在に至っている。長年結婚相談で全国を廻った体験談や全国3,900社の結婚相談所のアンケート等を踏まえた農村部の現状について述べた。農業を悲観的に見ているのは男性で女性はそう考えていない。未婚状態を悲観するのではなく、農村には可能性を秘めていると訴えた。
大会の部では、野中会長が開会挨拶に立ち、「新たな食料・農業・農村基本計画に基づき、産業政策としての担い手に対する、経営安定策と農地や農業用水などの、資源や農村環境を将来にわたって保全し向上させていくための地域政策を、車の両輪として推進されることとなっており、国においてもこれらの施策を平成19年度から本格的に実施されようとしている訳でございます。
今後のいずれの政策も、私ども水土里ネットに関わる深い政策でありますが、特に地域資源の保全、或いはこれらの向上を図るための農地・水・環境保全向上対策に付きましては、まさに水土里ネットがこれまで取り組んできた、水・土・里を地域のコミュニティーとともに守り育んで行くものであり、国の平成19年度の担い手に施策を集中する、新たな経営安定対策に関連をいたしましても、農業の持続的発展を確保するため、農業生産の基盤となる農業利水のストックの適切な保全・更新など、農業生産基盤の整備を引き続き推進するとともに圃場整備の推進等担い手の育成、農地の利用促進など新たな構造改革を一層推進して行くよう、今後の予算措置や制度の充実を皆様とともに望むものであります。」と述べられた。
続いて、国井副大臣が来賓祝辞に立ち、「農林漁村は、食料の安定供給に努めるととともに、国土や自然環境の保全、良好な景観の形成といった多面的機能の発揮を通じ、国民の暮らしにおいて重要な役割を担っております。
農業に秘めている21世紀に相応しい戦略や産業そして可能性を引き出すためには、意欲と能力のある担い手に対し、農業の構造改革や持続的発展に不可欠な基盤整備を引き続き推進するとともに、新たな施策を円滑に行うことで、生産性や品質の向上など、課題の解決を図ることが必要であると考えております。
こうした中で、来年度より担い手を対象とした新たな経営安定対策の導入、米政策改革推進対策の見直し、農地水環境保全向上対策の導入という3本の柱からなる政策改革が実施されます。
特に、農地・水・環境保全向上対策につきましては、国民共有の財産である農地・農業用水等の資源を、良好な状態で次世代に継承するための、地域ぐるみの効果の高い活動を支援して行くことといたしております。
今後、地域の皆様からのご要望を踏まえ、農政推進に必要不可欠な基盤整備を推進するとともに、新たな施策の本格導入が円滑に行われるよう、必要な平成19年度予算の確保に最大限の努力をして参る所存でございますので、引き続き皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。」と述べられた。
続いて、来賓紹介では駆けつけた約70名の国会議員が紹介された後、山田農村振興局長が情勢報告として、平成19年度農業農村整備事業予算について概要等を説明した。
その後協議に入り、全国水土里ネット吹田 副会長(水土里ネット山口会長)を議長に選任して議事が進められた。
初めに、岩手県の胆沢平野土地改良区事務局藤田優氏が、次に熊本県の水土里ネット一宮事務局長の甲斐純一郎氏が「21世紀土地改良区創造運動と資源保全施策」と題して、環境保全に向けた取り組みについて発表した。
最後に、水土里ネット千葉の星川正晴副会長・常務理事が大会決議(後記のとおり)を朗読し、これを採択して閉会した。
なお、大会決議は、農林水産省及び財務省並びに関係国会議員に要請した。
農業・農村は、国民に安全・安心な食料を供給するとともに、豊かな自然環境や美しい景観の保全・形成、伝統文化の継承などの多面的な機能の発揮を通じて、国民の命を守り、生活に潤いと安らぎをもたらしている。
決 議
このような農業・農村は、先人達がたゆみない努力と創意工夫によって守り育んできた「水」、「土」、「里」を基礎にしており、この国民共有の財産を適切に守り、より良い形で次世代に引き継いでいくことは、今日の我々に課せられた重要な責務である。
特に、大規模かつ広域にわたる基幹的農業水利施設の老朽化が進み、それらの施設が担っている食料の安定供給力の確保が危ぶまれる中、施設の保全、更新、整備を行う国営事業の役割は益々重要となってきている。
昨年閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画に基づき、担い手の経営に着目した新たな経営安定対策とあわせ、環境保全を重視しつつ農地・農業用水などの地域資源を保全向上させる農地・水・環境保全向上対策が、来年度から本格的に実施されるとされており、我々農業農村整備に携わる者としても、これまで培ってきた技術や経験を活かし、新たな施策の成果が速やかにかつ最大限に引き出されるよう努力する覚悟である。
国におかれては、経営所得安定対策等大綱を着実に実現に移し、農業・農村の持続的な発展を確固としたものにするため、平成19年度予算編成に向けて、下記事項を実現することを要請する。
記一 安全・安心な食料の供給、食料自給率の向上及び農業・農村が持つ多面的機能の発揮に不可欠な農地・農業用水の整備・保全並びに農村の振興に必要な施策については、地方との連携のもと、国の責務として確実に推進するよう措置するとともに、所要の地方財政措置を講ずること
一 農地・水・環境保全向上対策を全国幅広く実施できるよう本格導入するとともに、所要の地方財政措置を講ずること
一 農業の構造改革を加速化させるため、基盤整備を契機とした担い手の育成・確保や農地の利用促進を図ること
一 食料供給の基礎となる基幹的農業水利資産を効率的に次世代に引き継ぐため、国営事業を着実に推進するとともに、農業水利施設を更新・保全管理する新たな仕組みを整備するなど、国はその責務を十分に果たすこと
一 農村地域における防災・減災対策を一層推進すること
一 国産バイオ燃料の導入促進等バイオマス資源の総合的な利活用システムの構築を推進すること
一 これらの政策推進のために必要な農業農村整備関係の予算を確保すること
平成18年11月6日
農業農村整備の集い
| 水土里の体験展‘06 |
全国水土里ネット及び都道府県水土里ネット(後援:農水省等)は、昨年の10月28日から11月3日までの7日間、東京駅の八重洲地下街メインアベニュー及びセンタースポットにおいて「水土里の体験展‘06」を開催した。
今回で4回目の開催となるこのイベントは、「水」と「土」によって育まれた“食”と“農”の大切さについて、都市に住む人々と未来を担う子ども達に感じ取っていただき、ふるさとの自然や農村環境の大切さなど、農業の多面的な価値を籾すりや藁細工の体験などを通じて楽しみながら知ってもらうこと、またその中で大きな役割を担う水土里ネットの活動を知っていただくことを目的に実施した。
会場には稲穂が実った田んぼが再現され、通行人の目を楽しませたほか、農村に棲む生き物の展示や竹とんぼ作りなどの体験コーナーが設けられ、連日家族連れなどで賑わった。
また、開催初日には、別会場のヤンマービル1階ロビーにおいて「ふるさとの田んぼと水」子供絵画展2006の表彰式が開催され23人の入賞者に主催者などからそれぞれ賞状が手渡された。なお、全国から9239点の応募作品が集まり、本県からは、354点の応募があり、うち7点の作品が入選を果した。


| 農村総合整備事業・ 農業集落排水事業の推進等を提案要望 |
関東地区農村総合整備推進連絡協議会は、昨年11月2日に第33回通常総会を東京都において開催した。本県からは、川崎和郎那珂川町長ほか1市4町の職員と本会職員が出席。国に対する提案及び要望事項を採択し、同日農林水産省及び関東農政局並びに関係国会議員に陳情を行った。
なお、提案及び要望事項は、次のとおり。
提 案 要 旨
関東ブロック管内の農業農村整備事業の推進につきましては、平素より格別のご高配を賜り、関係者一同深く感謝申し上げます。
関東地域は、都市化が進展する首都圏や大都市を取り巻く地域からなり、それぞれの地域特徴を活かした多様な農業が展開されている中で、食料生産はもとより、環境保全・自然生態系の保全など、私たちの生活環境の多くを担っております。
しかしながら、農業・農村においては、都市化・混住化の進展に伴い農地の減少や、農業従事者の高齢化・担い手不足が一層深刻化しており、耕作放棄地の増加と中山間地域の活力低下など、多くの課題に直面しております。
このようなことから、農業・農村の活性化と維持・保全に向けた様々な事業展開を図ってきたところでありますが、都市部に比べ生産基盤のみならず生活環境基盤などの整備が遅れ、「農業・農村」「中山間地域」の健全な地域形成の構築に向けた施策について、さらなる支援強化と拡充に向けた予算措置を提案いたします。
1 農村総合整備の推進について
新たな食料・農業・農村基本計画を実現する経営所得安定対策等大綱を加速するためには、食料の安定供給の基盤である農地・農業用水や、豊かな自然環境、さらには地域独自の伝統文化が継承される、質の高い農村居住空間を形成することが大切であり、地域固有の資源が適切に保全管理される地域づくりや、人づくりのための施策が、一層必要となります。
ついては、健全な農業・農村及び中山間地域の構築に向け、国と地方の緊密な連携に基づいた農村総合整備が、重点的・計画的に推進されるよう、次の事業について、積極的な予算措置を提案いたします。
(1) 農村振興総合整備事業
(2) 田園空間整備事業
(3) 中山間地域総合整備事業
(4) 集落基盤整備事業
(5) 集落地域整備統合補助事業
(6) 村づくり交付金
(7) 美しいむらづくり総合整備事業
(8) 元気な地域づくり交付金
2 農業集落排水事業の推進について
農村地域は、食料の生産はもとより国土の保全、水源のかん養、自然生態系の保全や健全な水循環機能など数多くの役割を担っております。
このため、農村の快適な生活環境の創出や豊かな水環境の回復など地域の特性を活かした、安らぎや潤いのある農村空間を構築する、農業集落排水事業の推進が必要となります。
ついては、農業集落排水施設の維持管理や、機能強化に対する事業の拡充や、資源循環型社会に向けた農村地域のバイオマス利活用の促進など、環境保全に向けた農村地域への支援について、さらなる予算措置を提案いたします。
(1) 農業集落排水資源循環統合補助事業
(2) 汚水処理施設整備交付金
(3) バイオマスの環づくり交付金
| 岩舟町の3土地改良区が合併予備契約書に調印 |
岩舟町の「静和土地改良区」、「岩舟南部土地改良区」、「静戸川土地改良区」の3土地改良区は、昨年12月21日、岩船会館コンベンションホールにおいて、栃木岩舟町長、山口下都賀農業振興事務所長の立会いのもと、合併予備契約書の調印式を挙行した。 3土地改良区は、それぞれ大規模な工事は完了し、土地改良施設の維持管理に移行しているため、組織のスリム化と事務経費の節減を図ろうと、昨年5月に合併推進協議会を設置して合併を検討して来た。 調印式には、3土地改良区の役員等、約60名が出席。合併推進協議会長で静和土地改良区の茂呂理事長が、「合併により事業運営基盤を強化し、公法人として質の高い運営を図り、今後、諸事業に取組んで行きたい」と挨拶した。次に岩舟町山崎経済課長がこれまでの合併協議の経過等について報告を行い、ビデオ映像により3土地改良区を紹介した。続いて、出席者が見守る中、3土地改良区の理事長及び立会人により合併予備契約書の調印が行われた。 最後に来賓である栃木岩舟町長、永島藤岡町長、小林岩舟町議会議長(代理:岡副議長)及び山口下都賀農業振興事務所長並びに本会会長(代理:野澤専務理事)が祝辞を述べた。 今後3土地改良区は、それぞれ総会において合併を議決し、同総会において選任される12名の設立委員によって県知事あて認可申請が行われ、平成19年4月1日付けで「岩舟土地改良区」が誕生する見込みである。

旧改良区名 面 積 役員数 総代数 組合員数 事業概要 静和 150 18 ― 256 維持管理 岩舟南部 54 12 ― 150 維持管理 静戸川 53 12 ― 106 維持管理 計 257 42 ― 512 新土地改良区 257 12 35 512 維持管理
| 秋の叙勲 |
政府は、昨年11月3日付けで平成18年秋の叙勲の受章者を発表した。
総数は、4028人。うち県内在住者は、57人が受章した。土地改良関係では、元小川町長渡辺良治氏が旭日双光章に、前市貝町長の国井義慧氏が瑞宝双光章に輝いた。
旭日双光章(地方自治功労)
渡 辺 良 治 氏(71歳)
那須郡那珂川町小川在住。昭和35年に栃木県庁に入庁。平成7年に旧小川町長に初当選から平成17年まで連続3期11年務める。土地改良関係では、西の原用水土地改良区連合理事長、南那須地域土地改良事業推進協議会長、平成9年から平成17年まで本会理事を務める。
瑞宝双光章(教育功労)
国 井 義 慧 氏(75歳)
芳賀郡市貝町田野辺在住。栃木県教育委員会芳賀教育事務所長、市貝小校長、市貝町教育長などを歴任。平成5年に市貝町長に初当選から平成13年まで連続2期8年務める。土地改良関係では、芳賀台地土地改良区理事長を務める。
| 鹿沼市堆肥化センターのオープン式典 |
鹿沼市が、市内で発生する有機性資源を堆肥としてリサイクルすることにより、農村生活環境の改善及び土づくりの促進を図り、循環型社会の形成を目的に整備を進めていた農村振興総合整備事業の堆肥化センター(愛称・ほっこりー)が、竣工の運びとなり、昨年11月2日、現地でのオープン式典が挙行された。
式典には、阿部和夫鹿沼市長はじめ、国井正幸農林水産副大臣、阿見英博鹿沼市議会議長、池田貞夫栃木県上都賀農業振興事務所長他多数の関係者及び来賓が出席し、盛大に挙行された。
◆事業の概要◆
事 業 名 農村振興総合整備事業(むらづくり交付金)
総事業費 23億900万円
整備年度 平成16年度〜平成19年度
所 在 地 鹿沼市油田町地内
敷地面積 4.57ha
主要施設及び規模
管理棟、前処理・乾燥棟、堆肥舎、製品
棟、炭化棟、副資材棟 計 12,597.04m2
施設能力 処理資源量 29,478t/年(118.0t/日)
堆肥製造量 8,060t/年(32.2t/日)

| 塩野室地区の竣工式 |
このほど、県営圃場整備事業の塩野室地区が竣工の運びとなり、昨年11月11日、現地での記念碑除幕
式と祝賀会が挙行された。
式典には、斎藤文夫日光市長、渡辺渡栃木県議会議員、星一男栃木県議会議員、池田貞夫栃木県上都賀農業振興事務所長他多数の来賓と阿久津清塩野室土地良区理事長はじめ多くの役員が出席し、盛大に挙行された。
◆事業の概要◆
事 業 名 県営圃場整備事業塩野室地区
地区面積 79.6ha
総事業費 9億405万円
工 期 平成12年度〜平成17年度
組合員数 68名

| 芹沼地区の竣工式 |
このほど、県営圃場整備事業の芹沼地区が竣工の運びとなり、昨年11月17日、現地での記念碑除幕式と祝賀会が挙行された。
式典には、斎藤文夫日光市長、渡辺渡栃木県議会議員、星一男栃木県議会議員、池田貞夫栃木県上都賀農業振興事務所長他多数の来賓と沼尾好惟大谷川流域土地改良区理事長はじめ多くの役員が出席し、盛大に挙行された。
◆事業の概要◆
事 業 名 県営担い手育成基盤整備事業芹沼地区
地区面積 157.4ha
総事業費 14億9100万円
工 期 平成11年度〜平成17年度
組合員数 199名

| 五行川東地区の竣工式 |
このほど、県営圃場整備事業の五行川東地区が竣工の運びとなり、昨年11月22日、現地での記念碑除
幕式と祝賀会が挙行された。
式典には、藤田忠義二宮町長、佐藤勉衆議院議員、
山岡賢次衆議院議員、石坂真一栃木県議会議員、一木弘司栃木県議会議員、大久保幸雄栃木県農務部技監他多数の来賓と飯山一五行川東土地改良区理事長はじめ多くの役員が出席し、盛大に挙行された。
◆事業の概要◆
事 業 名 県営担い手育成基盤整備事業五行川東地区
地区面積 490.0ha
総事業費 45億4800万円
工 期 平成5年度〜平成15年度
組合員数 478名

| 宇芳真地区の竣工式 |
このほど、県営畑地帯総合整備事業の宇芳真地区が竣工の運びとなり、昨年12月4日、現地での記念碑除幕式と祝賀会が挙行された。
式典には、福田武隼真岡市長、森仁芳賀町長、大久保幸雄栃木県農務部技監、鈴木忠同参事兼芳賀農業振興事務所長他多数の来賓と鈴木穆宇芳真土地改良区理事長はじめ多くの役員が出席し、盛大に挙行された。
◆事業の概要◆
事 業 名 県営畑地帯総合整備事業宇芳真地区
地区面積 171ha
総事業費 23億6290万円
工 期 平成9年度〜平成17年度
組合員数 433名

| 非補助農業基盤整備資金の案内 |
国の補助を受けない土地改良事業・生活基盤整備事業等に対して、低利の融資が受けられます。
◆非補助農業基盤整備資金とは
地域の特性に応じた農業生産基盤の整備・保全を図り、食料の安定供給の確保等政策目的を実現してゆくためには、国の直轄事業や補助事業と関連した非補助事業の推進が重要になっています。
非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国からの補助を受けないで、かんがい排水やほ場整備、客土などの事業に取り組み、農業生産基盤の整備・保全の推進を図る場合、農林漁業金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対して低利で融資する資金です。
なお、国の補助対象でない県又は市町村単独による補助事業についても、融資の対象となります。
◆融資の条件
■貸付対象者
〇土地改良区
〇土地改良区連合(事業主体となる場合に限る)
〇農業協同組合
〇農業協同組合連合会
〇農業を営む人
〇農業振興法人
〇5割法人・団体(農業集落排水事業の実施に限る)
■貸付限度額
複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区等が当該年度に負担する額までとなっています。(ただし、融資1件当たりの最低額は50万円となっています。)
なお、農業集落排水事業では、一部施設ごとに限度額を設定しています。
■貸付利率
1.80%(平成18年12月20日現在)
固定金利であり、償還が終わるまで適用される金利は変更ありません。
金融情勢により貸付金利は変動しますので、直近の利率は最寄の農林漁業金融公庫にお問い合わせください。
■償還期限
最長25年(据置期間10年以内を含む)になっており、事業内容に応じて設定できます。
■償還方法
元利均等償還、元金均等償還のいずれかを選択できます。
■融資対象事業種類
かんがい排水、畑地かんがい、ほ場整備、客土、農道、索道、畦畔整備、農地造成、農地保全、防災、維持管理、農業集落排水、飲雑用水施設などとなっています。
| 農業基盤整備資金の金利改定 |
平成18年12月20日付で、農林漁業金融公庫の農業基盤整備資金の貸付利率が次のとおり改定されました。
なお、借入時の金利は、金融情勢により変動しますので、最新の利率は最寄の農林漁業金融公庫にご確認ください。
区 分 現 行 改 定 補助事業 県 営 2.05% 1.95% 団体営 1.90% 1.80% 非 補 助 一 般 1.90% 1.80%
| お知らせ |
本会の第78回通常総会は、栃木県土地改良会館において、平成19年3月22日(木)午前10時に開会する予定です。
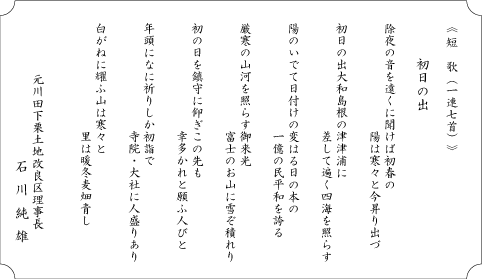
| 平成18年11・12月主要行事報告 |
11月
日 行 事 1〜2 栃木県土地改良事業推進協議会第2回役員会 2 鹿沼市堆肥化センター「ほっこりー」オープン式典 2 関東地区農村総合整備推進連絡協議会理事会及び第33回通常総会 6 平成19年度農業農村整備事業予算拡大陳情 6 平成18年度利根川水系農業水利協議会現地研修会 6 農業農村整備の集い 9〜10 南那須地域土地改良事業推進協議会視察研修 9〜10 上都賀土地改良事業推進協議会先進地視察研修 9 栃木県農地・水・環境保全向上対策推進協議会連絡会議 11 県営圃場整備事業塩野室地区竣工式 14〜15 平成18年度農業集落排水事業先進地視察研修 14〜15 安足土地改良事業推進協議会現地研修会 14 都道府県水土里ネット事務責任者会議 16〜17 塩谷地方土地改良事業推進協議会先進地研修 17 県営圃場整備事業芹沼地区竣工式及び祝賀会 17 全国土地改良施設管理事業推進協議会第10回通常総会 21 栃木県監査委員による財政的援助団体等に対する監査(本監査) 22 県営圃場整備事業五行川東地区竣工式及び祝賀会 28 平成18年度栃木県農業担い手躍進大会 29〜12/1 関東農政局による平成18年度土地改良事業団体連合会検査 30〜12/1 平成18年度利根川水系土地改良情報連絡会
12月
日 行 事 4 県営畑地帯総合整備事業宇芳真地区竣工除幕式及び祝賀会 4 平成18年度農業農村整備技術強化対策事業一般研修会 13 栃木県水田農業推進協議会臨時総会 14 構造改革推進ほ場整備全国研究会及び第1回全国研究会 20 本会第3回理事会 21 静和・岩舟南部・静戸川土地改良区合併予備契約調印式 21 都道府県水土里ネット会長・事務責任者合同会議 21 非補助土地改良事業等推進農業基盤整備資金借入申込手続説明会 25〜26 芳賀郡市土地改良区協議会員研修会 28 仕事納め式
| 表紙写真説明 |
表紙の写真『夜明けの堰』
○撮影者
入 江 重 典 氏
(宇都宮市在住)
○撮影地 河内郡河内町
○コ メ ン ト
平成17年度「美しいとちぎのむら写真コンテスト」
整備された水・土・里部門で優秀賞に輝いた作品です。
審査員講評は、「黒づくみがものたらないが、逆に力強さが感じられます。上下対称の画面構成がおもしろい。
また、施設全体をシュリエット的に捉えた表現力は巧みで、重量感さえ感じられる作品となっています。」というものでした。