 |
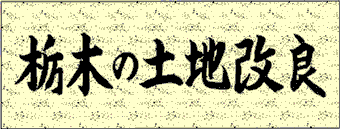 |
『水土里ネットとちぎ』は本会の愛称です

−主な内容−
 |
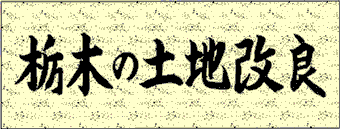 |


新年のごあいさつ 水土里ネットとちぎ
(栃木県土地改良事業団体連合会)
会 長 大久保 寿 夫
会員の皆様あけましておめでとうございます。
今年も皆様とともに、新しい年を迎えることができました。心からお慶びを申し上げます。
また、昨年中は、本会の業務運営に対して皆様より賜りましたご高配に、衷心より御礼と感謝を申し上げます。更に、農業農村整備事業の推進に御尽力されておられますことに対しまして、深く敬意を表します。
昨年は、災害の多い年でありました。海外においては地震や津波によって都市が一瞬にして壊滅し、多くの尊い人命が奪われるなど大災害が発生しました。この映像を見るにつけ自然の力の強大さを改めて知らされました。国内においても地球温暖化の影響による暴風雨やゲリラ豪雨による災害が各地で発生し、尊い人命と貴重な財産が失われました。被災されました方々に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、被災地が早期に復旧され、通常の生活を取り戻すことができますようお祈り申し上げます。
さて、御承知のとおり、昨年8月末に行われました総選挙におきましては、民主党の圧勝であり、本格的な政権交代により、鳩山連立政権が誕生いたしました。前政権下で編成された平成21年度補正予算の見直しが行われ、予算執行の一時凍結により、新規事業の農地有効利用支援整備事業や土地改良負担金対策などに影響が出たところであります。また、来年度の予算編成については、前政権下で行われた8月末の概算要求を白紙撤回し、民主党のマニフェスト実現のため、概算要求を10月に再提出させたところでありますが、95兆円もの膨大な要求額となりました。これを圧縮する目的で行政刷新会議による事業仕分けが行われ、農道整備事業や田園整備事業等が廃止されました。その後、民主党は、政府に対し、平成22年度予算の重点要望として19項目を要請しましたが、土地改良事業費は概算要求額を半減するものでありました。この結果、昨年末の概算決定においては、農業農村整備事業費は、対前年比63.1%減の2129億円とかつてない厳しい内容となりました。農山漁村地域整備交付金1,500億円が措置されておりますが、来年度の事業実施地区の予算付けが極めて厳しいのではないかと心配しているところであります。この上は来年度の予算獲得に向けて全力を傾注して参りたいと考えております。
一方、喫緊の農政課題でありました農地政策改革については、我が国の食料、農業をめぐる諸情勢の変化に対応して、国民に対する食料の安定供給を確保するため、これまでの耕作者自らが所有することを適当としてきた制度から有効利用を促進する「農地法等の一部を改正する法律」が昨年12月に施行されました。今回の改革の視点は、(1)農地転用規制の厳格化、(2)農用地区域内農地の確保、(3)農地の権利を有する者の責務の明確化、(4)農地の面的集積の促進、(5)農地を利用する者の確保・拡大、(6)遊休農地対策の強化の6つを柱として緊急に行うというものであります。
農業農村をめぐる諸情勢は、大変厳しい状況下ではありますが、農業・農村は、安全で安心な食料の供給とともに、豊かな自然、美しい景観の形成などの多面的な機能を発揮することにより、日本という美しい国をかたちづくり、国民生活を支えて参りました。
その根源たる「水」「土」「里」は、先達の絶ゆまざる努力により育まれたものであり、これらの財産を守り、次世代に適切に引き継いでいくことが、農業農村整備に携わる私達「水土里ネット」の責務であります。
本会としましては、食料・農業・農村基本法の理念に即し、環境との調和に配慮しつつ、既存ストックの有効利用を重視した保全管理や農業の構造改革の加速化に資する生産基盤の整備、地域再生に資する活力ある美しいむらづくりの推進など、新たな時代に対応した使命を担う農業農村整備を強力に推進して参る所存であります。
結びに、平成22年が今までにない大きな変革の年になりますが、私共連合会は、適正な業務運営に努め、国並びに県の施策と呼応しながら、会員皆様の負託に応えるよう誠心誠意努力して参りたいと存じておりますので、より一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
会員皆様のご健勝をご祈念申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

平成22年 新年知事あいさつ 栃木県知事 福 田 富 一
県民の皆様、あけましておめでとうございます。
早いもので、私が知事に就任してから5年余が経過いたしました。この間、私は、元気で活力ある“とちぎ”づくりを目指し、対話と協調による県民中心、市町村重視の県政運営を基本として、各種施策を積極的に推進して参りました。
昨年は、当面の最重要課題であります経済・雇用対策に全力で取り組みましたほか、今月中に運用を開始する「ドクターヘリ」の導入など地域医療の確保、通学路の歩道整備や道路の冠水対策、災害時の拠点となる県有施設や県立学校などの耐震化対策など、安全・安心への備えを進めました。また、「有名有力県」への取組といたしまして、そば、あゆ、牛乳など魅力ある地域資源を活用した「食の街道」づくりの推進や、「いちご情報館」の整備などにより“とちぎブランド”の創造と発信に努めて参りましたほか、県民総ぐるみで地球環境の保全に取り組むため、「とちぎ環境立県戦略」を策定するなど、地球と人にやさしい“エコとちぎ”づくりを積極的に推進していくこととしたところであります。
しかしながら、本県経済は、引き続き厳しい状況が続いています。また、申し上げるまでもなく、人口減少社会の到来、経済のグローバル化、高度情報化の進展や地球環境問題の深刻化など、私たちを取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。さらに、本県財政は、財政調整的基金が今年度末には30億円にまで減少し、今後も毎年度300億円を超える財源不足が見込まれるなど、かつて経験したことのない、極めて厳しい状況にありますほか、「住民に身近な行政は地方で」という考え方のもと、国と地方の役割分担を抜本的に見直す第二期地方分権改革も、まさに正念場を迎えています。
こうした状況にある中で、時代の潮流を的確に捉え、将来をしっかりと見据えた県政運営を行っていくことが極めて重要となって参ります。このため、昨年10月に策定した「とちぎ未来開拓プログラム」に基づき、内部努力の徹底、歳入の確保や行政経費の削減など行財政全般にわたる取組を進め、県政運営の土台となる財政基盤の立て直しを図りますとともに、「平成22年度政策経営基本方針」により、すべての活動の原動力となる「人づくり」を政策の基本に据え、「経済・雇用対策」、「協働による地域づくり」や「安心な地域社会の実現」といった課題に重点的に取り組むなど、事業の選択と集中を図り、最終年度を迎える総合計画「とちぎ元気プラン」の総仕上げを図って参ります。
また、現在、これからの“とちぎ”づくりを推進するため、平成23年度を初年度とする新しい総合計画の策定に取り組んでおりますが、新しい総合計画におきましては、県民の皆様とともに目指すべき“とちぎ”の将来像をしっかりとお示しし、将来に向けて夢と希望を持っていただける“とちぎ”の実現を目指して参りたいと考えておりますので、より一層の御理解と御支援をお願い申し上げます。
年の始めに当たり、私の所信を申し上げますとともに、本年が皆様にとって素晴らしい年となりますことをお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。
平成22年1月

新年のごあいさつ 栃木県農政部長 高 斎 吉 明
新年あけましておめでとうございます。
皆様には、健やかに輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、昨年中は、県農政の推進に深い御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
今日の農業・農村を取り巻く状況は、農業従事者の減少や高齢化の進行をはじめ、県民が求める安全・安心な食料の安定供給や食料自給率の向上に対する要請など大きな変革の時期を迎えています。
このような中、不安定な国際情勢等を背景にした肥料や原油等の大幅な価格変動により、農家の経営環境が悪化するなどの課題が生じている一方、低迷する経済状況の中において、地域経済を担う産業として、また雇用の場として、農業・農村に対する期待が高まりをみせています。
また、政権交代により、新たに戸別所得補償制度が導入されるなど、国の農業政策が大きく変わろうとしており、今後、本県農業に大きな影響が出てくることも予想されております。
県といたしましては、これらの変化に適切に対応しながら、農業者をはじめ、関係団体、消費者など県民の皆様との連携と協働の下、これまで取り組んできた首都圏農業の確立を基本に、消費者の視点を重視した産地育成や収益性の高い農業生産構造の確立を図っていく他、経営感覚に優れた農業者の育成や他産業との連携に対する支援などにも重点をおき、産業として持続的に発展できる本県農業の実現に向け、その基盤作りに取り組んで参ります。
また、農業農村整備事業につきましても、「とちぎ水土里づくりプラン」に基づき、担い手への農地集積を基本とし、地域の特性に応じた生産基盤の整備をはじめ、今後増大する農業水利施設等の維持・保全や更新整備、中山間地域を含めた農村地域の生活環境基盤整備を進めて参ります。さらには、食を中心にしてブランド化や地域づくりを進める「とちぎ食の回廊づくり」、次世代に継承したい田園風景の選定と有効活用を促進する「とちぎの田園風景百選事業」をはじめとする各種事業により環境と調和のとれた農村の形成、地域協働による農村環境の保全など、活力と魅力にあふれる農業・農村づくりにも、積極的に取り組んで参ります。
県内の社会・経済情勢は、一段と厳しい状況にありますが、食料の安定供給や農業・農村の持続的発展のためには、農業農村整備事業の果たす役割が引き続き重要であり、その推進に当たりましては、推進母体である土地改良区の運営基盤の強化並びに活動の更なる充実が必要であると考えております。土地改良事業団体連合会の皆様方には、今後ともなお、一層の御支援と御尽力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、皆様方の御健勝と益々の御発展を心から祈念申し上げまして、年頭のあいさつといたします。

新年の御挨拶 農村振興課 課長 小 川 正 順
新年あけましておめでとうございます。
皆様方には、御家族と共に健やかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
また、農村振興に関わる事業をはじめ、県農政の円滑な推進に日ごろから格別の御支援、御協力をいただいておりますことに、心からお礼申し上げます。
さて、農業・農村におきましては、昨年の政権交代による行政刷新会議による事業仕分けや米の個別補償制度の創設などの大きな転換期を迎え、さらには農産物の価格の低迷など、単に農業・農村のコスト低減などの努力だけでは対応しきれない非常に厳しい局面を迎えております。
県におきましては、これらの情勢を十分踏まえ緊急的な対応を図るとともに、県財政の健全化に向けた「未来開拓プログラム」による事務事業の見直しを進めたところですが、今後とも、本県の有する条件を活かした首都圏農業の展開を基本とした「とちぎ“食と農”躍進プラン」に基づき、農村の持つ豊かな地域資源の活用や都市住民との協働等を通した活力ある農村づくり、健康的で豊かな食の提供など、元気で活力ある「とちぎの農業・農村」の実現を図ってまいります。
当農村振興課におきましては、躍進プランに掲げた施策を着実に展開するため、地域資源を活かした都市と農村の交流・協働の取組を引き続き促進するとともに、「とちぎ食の回廊づくり」などの新たな展開にも積極的に対応しながら、農村地域の総合的な活性化を図ります。
また、健全な農村環境の保全継承と農村地域の活性化を図っている「農地・水・環境保全向上対策」については、「田んぼまわりの生きもの調査」や地域の創意工夫を活かした景観形成などを契機に、活動のグレードアップを推進していきます。本県の誇れる田園風景を百年後の後世に引き継ぐ「とちぎのふるさと田園風景百選事業」については、百選風景の認定や農村環境に対する県民の理解促進等を図りながら、田園風景の保全や地域活性化等を図っていきます。
社会全体で地球温暖化防止や環境への配慮が重視される中、農業においても多様なバイオマスの利活用を推進するとともに、バイオ燃料については関係機関団体等と十分に連携を図りながら、バイオディーゼルを始めとした実用化の促進を進めていきます。
さらに、生産条件等が不利な中山間地域では、過疎化や高齢化、野生鳥獣被害などから、農業・農村の持つ多面的機能の維持・保全が困難になってきております。このため、安全で快適な暮らしのための生活環境整備と生産基盤の整備を一体的に進めるとともに、中山間地域等直接支払制度等による、地域活性化の多様な活動や鳥獣害対策など総合的な支援を行います。
今後とも自然豊かで住みよい農村の形成をめざし、農村の様々な資源を活かした魅力ある地域づくり、快適な生活環境の整備等、各種施策を総合的に推進して参りたいと考えておりますので、会員の皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。
結びに、会員の皆様の御健勝と栃木県土地改良事業団体連合会の益々の御発展を祈念申し上げまして新年のごあいさつといたします。

新 年 の あ い さ つ 農地整備課長 福 田 保
あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、輝かしい新年を健やかに迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。
皆様方には、日頃から農業・農村整備事業の円滑な推進に格別の御支援、御理解を賜り深く感謝申し上げます。
今日の食料・農業・農村をめぐる情勢につきましては、農業従事者の減少・高齢化や農産物価格の低迷に加え、肥料や原油等の大幅な価格変動による農作物生産コストの上昇等に伴い、農家経営環境が不安定化するなど様々な課題に直面しております。
一方、食料自給率の向上や安全・安心な食料の安定供給など、消費者の視点を重視した取り組みが求められており、さらには、新たな雇用創出の場として、農業・農村に対する期待が高まってきています。
こうした中、県としましては、本県の農業振興計画である「とちぎ”食と農”躍進プラン」及びその部門計画として農業農村整備事業の展開方向を示した「とちぎ水土里づくりプラン」に基づき、活力と魅力にあふれる農業・農村を目指して各種施策を推進しております。
平成22年度の農業農村整備事業につきましては、県の財政が一段と厳しい状況にありますが、選択と集中による予算編成により、最終年度を迎える「とちぎ水土里づくりプラン」の目標達成に向けて施策展開を図って参りたいと考えています。
特に、経営体育成基盤整備事業(ほ場整備事業)につきましては、水田の汎用耕地化や農地の集積、担い手の育成を目的に、生態系や景観などの環境にも配慮し、さらには、耕作放棄地の抑制に寄与するなど、地域の特性に応じた整備を積極的に推進して参ります。
また、農業水利施設は食料の安定供給に不可欠であるだけでなく、国土の保全、水源かん養などの多面的機能を有し、未来に継承していかなければならない県民全体の財産であることから、今後耐用年数に到達する施設が増加していく中、より計画的かつ効率的な対応が求められています。
このため、平成20年度から実施している基幹的な水利施設における劣化状況等の実態調査(基幹的農業水利施設保全計画基礎調査)の結果等に基づき、整備年次スケジュールを作成し、ストックマネジメント事業や維持管理適正化事業等の補助事業を最大限に活用しながら、将来に向けた計画的な維持管理や更新整備を図って参ります。
一方、これらの施設の主な管理主体である土地改良区については、組織運営の充実化を図ることが重要であることから、引き続き統合整備を進めるとともに、土地改良区の体質強化や情報共有化の促進に向けた取り組みを進めて参りたいと考えております。
今後とも本県農業・農村の更なる発展を目指し、農業農村整備事業をはじめ、各種施策を推進して参りますので、御理解と御協力をお願いいたします。
結びに、皆様の御多幸・御健勝を心からお祈り申し上げ新年のあいさつといたします。
| 平成21年度第1回農業農村整備部会を開催 |
本会は、昨年10月2日、栃木県土地改良会館において農業農村整備部会の平成21年度第1回会議を、来賓に福田保栃木県農政部農地整備課長を招き開催した。
農業農村整備部会は、新たな農業農村整備事業の積極的な進展を図るための諸対策の検討及び推進のための諸活動を行うことを業務としている。
会議に先立ち、平成21年7月7日に開催の本会第2回理事会において、今年3月の任期満了に伴い、農業農村整備部会員の選任について承認された部会員に対し、小坂副会長が委嘱状の交付を行った後、挨拶をいただいた。
会議は、千保一夫部会長が開会挨拶を述べ、福田農地整備課長から来賓挨拶をいただいた。
議事は、千保部会長が議長を務め、次のとおり進められた。
第1号議案「副部会長の互選について」は、姿川土地改良区理事長 加藤一克氏、小山用水土地改良区理事長 山中政博氏をそれぞれ互選した。
その後、協議事項に入り、千保部会長が引き続き座長を務め、次のとおり進められた。
「平成20年度活動報告について」及び「平成21年度活動計画について」を説明し、会議に諮ったところ原案のとおり承認、議決した。
続いて、「平成22年度県農業等施策並びに予算編成に関する建議要望について」を審議し、原案のとおり承認した。
その他、平成22年度農業農村整備事業費概算要求について・同農業農村整備事業予算拡大陳情及び農業農村整備事業の集いについて・とちぎ未来開拓プログラム(試案)に関する要請活動の説明を行い閉会した。
なお、新たに委嘱された部会員は次のとおり。
◆農業農村整備部会員(敬称略)
部 会 長 千 保 一 夫(大田原市長)
副部会長 加 藤 一 克(姿川土地改良区理事長)
〃 山 中 政 博(小山用水土地改良区理事長)
部会員 猪 瀬 成 男(上三川町長)
〃 吉 澤 新 市(鬼怒川右岸土地改良区理事長)
〃 佐 藤 信(鹿沼市長)
〃 橋 本 啓 藏(南押原土地改良区理事長)
〃 田 井 哲(日光市土地改良区理事長)
〃 小 林 利 恒(市貝町長)
〃 小 坂 利 雄(真岡市土地改良区理事長)
〃 黒 崎 健(芳賀町土地改良区理事長)
〃 日向野 義 幸(栃木市長)
〃 田 邉 豊 吉(壬生町土地改良区理事長)
〃 遠 藤 忠(矢板市長)
〃 猪 瀬 圭 市(氏家土地改良区理事長)
〃 伴 達(喜連川土地改良区理事長)
〃 高 橋 勇 丞(大田原市土地改良区理事長)
〃 津久井 恭 夫(那須町土地改良区理事長)
〃 川 崎 和 郎(那珂川町長)
〃 佐 藤 勉(小川土地改良区理事長)
〃 玉 造 恵 一(荒川南部土地改良区理事長)
部会員 大豆生田 実(足利市長)
〃 寺 嶋 勝 豊(佐野市土地改良区理事長)
〃 小 沼 勝 重(三栗谷用水土地改良区理事長)
任期:平成24年3月31日
| とちぎ未来開拓プログラム(試案)に関する要請書を県に提出 |
本会は、昨年10月7日、栃木県庁において、先の8月27日に開催した本会第83回臨時総会で決議した「とちぎ未来開拓プログラム(試案)に関する要請」を、栃木県土地改良事業推進協議会、栃木県ほ場整備連絡協議会、栃木県農業集落排水事業連絡協議会、農業農村整備を推進する会の関連四団体と連名で実施した。
要請には、大久保寿夫本会会長の他、小坂利雄栃木県土地改良事業推進協議会長、加藤一克栃木県ほ場整備連絡協議会長、高橋森一栃木県農業集落排水事業連絡協議会長、岡本芳明農業農村整備を推進する会長の4名が栃木県庁に出向き、栃木県知事をはじめ青木克明栃木県議会議長、高斎吉明栃木県農政部長、小川正順同部農村振興課長、福田保同部農地整備課長に対して要請書(後掲のとおり)をそれぞれ手渡した。本県農業・農村の振興と発展を根底から支えている農地・水・水利施設等の整備保全と農村地域の環境整備を推進するため、関係団体会員の総意の下に強く要請するとともに、農業農村整備事業の更なる推進への理解を求めた。
本県は、これまで、恵まれた立地条件を活かした収益性の高い生産構造の実現に向け「首都圏農業」を基本に各種の施策を展開された結果、米麦、園芸、畜産のバランスのとれた生産構造が確立しております。
要 請 書
また、むらづくり運動などの様々な取組を通して都市と農村の交流が進み、地域が活性化してきておりますが、農業農村整備事業もこれらの一翼を担って参りました。
しかしながら、担い手の減少や高齢化、土地利用型農業の構造改革、農村資源・環境の維持保全、国際化への対応など、多くの課題がある中で、農業農村整備事業もこれらの課題を視野に入れた施策の展開が求められております。
このような中にありまして、栃木県におかれましては、本年5月に財政健全化への道筋を定めた「とちぎ未来開拓プログラム」試案を公表され、平成25年度からの収支の均衡した予算を編成するため、公共事業の3割削減、非公共事業の5割削減などの方針が示されました。
これにより、農業農村整備事業の実施に大きな影響が出ることを懸念しているところであります。特に、圃場整備につきましては、約7割の農用地が整備済であり、膨大な水利施設がストックされており、今後、更新時期のピークを迎えようとしておりますので、これらの施設の維持保全が課題となっております。また、生活排水処理施設などの環境整備につきましても、大幅に遅れている現状にあります。
つきまして、本県農業・農村の振興と発展を根底から支えている農地・水・水利施設等の整備保全と農村地域の環境整備を推進するため、本会会員の総意により下記事項について強く要請いたします。
記
1.農業生産を根底から支え、農業構造改革の加速化に資するとともに、農村生活環境の改善に資する農業農村整備事業の計画的、かつ、着実な推進
2.農業農村整備事業の計画的、かつ、着実な推進に資するための財源及び体制の確保
3.農業・農村における生産資源や環境資源の維持保全とともに、活力ある地域づくりの契機となっている農地・水・環境保全向上対策の推進
4.県単独農業農村整備事業の削減の見直し
5.集中改革期間における新規事業着手抑制の緩和
6.市町村総合交付金における農業集落排水事業費廃止の見直し
平成21年10月7日
栃木県土地改良事業団体連合会
会 長 大久保 寿 夫
栃木県土地改良事業推進協議会
会 長 小 坂 利 雄
栃木県ほ場整備連絡協議会
会 長 加 藤 一 克
栃木県農業集落排水事業連絡協議会
会 長 高 橋 森 一
農業農村整備を推進する会
会 長 岡 本 芳 明
| 平成22年度農業農村整備事業に関する要請を実施 |
本会は、昨年11月30日、農業農村整備事業の円滑な推進に資するため本会内に設置する農業農村整備部会(部会長・千保一夫大田原市長)、栃木県土地改良事業推進協議会(会長・小坂利雄真岡市土地改良区理事長)とともに、平成22年度農業農村整備事業の予算に関する要請を本県選出等関係衆参国会議員に対して実施した。
なお、要望書は次のとおり。
要 望 書
[1]現状と課題 (略)
[2]事業推進に関する要望
1−1農業農村整備事業の予算の確保と土地改良制度の確立
・農業構造改革の加速化、安全安心な食料供給基盤の確保と地域づくりの推進を通じて、わが国農業の国際競争力の強化、国民生活の安全安心の確保、環境の保全向上を図るのは国の責務であり、そのためこれらに直接裨益する国営事業をはじめとする農業農村整備事業の継続的な実施が必要でありますので、現在の農業・農村の基盤が崩壊しないよう、必要な予算の確保と、併せて施策の展開を図られたい。
・また、国民への食料の安定供給や食料自給率の確保に鑑み、農地の確保や基盤整備の推進については、公的関与の拡大と諸事業制度の維持強化を継続的に図られたい。
・農業情勢の変化に沿って、農業・農村の整備が円滑に図られるよう適切な土地改良制度の確立を図られたい。
1−2農政改革のための基盤づくりの推進
(1) 水・土・里を守るために必要な農業生産基盤整備事業の重点的・計画的な推進
・ほ場整備事業、かんがい排水事業、畑総事業等の推進。
・ 低コスト整備手法の導入や、住民参加型手法の活用等、画一的な整備から弾力的整備への転換の推進。
(2) 地域資源の多面的機能を活かした総合的基盤づくりの推進
・地域の個性、創造力を生かした農業戦略や地域づくりを実施する農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の確保と拡充。
(3) 食料供給力強化に向けた取り組みの推進
・食料供給力の強化を図るため、農地有効利用支援整備事業を確実に推進されたい。
2 土地改良施設の更新・管理に対する支援
(1) ストックマネジメントの技術的確立と予防保全対策の実施
基幹水利施設から末端施設に至る一貫した保全管理システムの構築のためには、施設劣化の将来予測や予防保全対策に係わる事業予算の継続的な確保を図られたい。
(2) 土地改良施設維持管理適正化事業の推進
本事業は、土地改良施設の定期的な整備補修を行い、土地改良施設の機能の保持と耐用年数の確保に資するものであり、事業予算の継続的な確保や事業制度の拡充を図られたい。
3−1地域資源を活かした活力のある地域づくりの推進
(1) 農業集落排水事業の推進
・農業用用排水の水質保全や農村生活改善及び地域資源循環の向上を図るため継続的に推進されたい。
(2)農業水利施設を活用した小水力発電整備事業の推進
・ 農業水利施設の持つ自然エネルギーの効率的な活用を図るため、小水力発電整備事業等を継続的に推進されたい。
(3)都市との交流を促進する農村環境保全整備の推進
・ 地場産品の販売、農業体験や自然環境を手段とする経済活動を興すため、生態系の保全や農村景観、さらには歴史的風土を保全する取り組みを推進されたい。
3−2 農地・水・環境保全向上対策の推進
農村は、伝統文化や環境を守り、良好なコミュニティを維持するなど、多面的機能を有し、国民全体が享受されるものである。
したがって、農村の多面的機能が維持・発揮されるよう、地域の実情に応じた地域協議会運営や活動組織の共同・営農活動に対する一層の支援の継続を図られたい。
| 水土里の集いに全国の関係者が参集 |
全国水土里ネット(会長・野中廣務水土里ネット京都会長)は、昨年11月30日、東京都千代田区平河町の砂防会館「シェーンバッハサボー」において、全国の土地改良関係者及び農地・水・環境保全向上対策活動組織等の関係者約600名を集めて「水土里の集い」を開催した。
集いは、第1部として講演会の部で始まり、阿武隆弘全国水土里ネット企画研究部長による基調報告が行われた。続いて、鈴木宣弘東京大学教授による(「食料危機」の教訓をどう活かすか)と題した特別講演が行われた。
特別講援をされる鈴木宣弘東京大学教授
第2部の表彰及び発表会では、21世紀土地改良区創造運動・第11回「ため池のある風景」写真コンテスト・疏水のある風景・写真コンテスト2009の表彰式が執り行われた。まず初めに、21世紀土地改良区創造運動大賞受賞地区9地区・さなえ賞11地区に対して、野中廣務全国水土里ネット会長から表彰状が授与された。続いて、第11回「ため池のある風景」写真コンテストが行われた。全国から寄せられた作品343点の応募の中から最優秀賞に輝いた和歌山県橋本市の澤井祥憲氏に対して全国ため池等整備事業推進協議会の吹田会長から表彰状が授与され、引き続き、疏水のある風景・写真コンテスト2009の表彰式が行われた。最優秀賞に輝いた長野県長野市の増田恵氏に対して佐藤準全国水土里ネット専務理事から表彰状が授与された。
次に、事例発表では、本年度21世紀土地改良区創造運動大賞を受賞した山形県の水土里ネット笹川の伊藤健氏から水辺学習マイスターと題して、水土里ネット鹿児島の松崎義人氏から世代継承マイスターと題して、それぞれの水土里ネットの活動についてその現状を紹介された。
最後に、各ブロック代表土地連などから模範的取組と関連する提言等が発表され平成21年度「水土里の集い」を終了した。
野中廣務全国水土里ネット会長の主催者挨拶
| 栃木県農村総合整備事業促進協議会視察研修を開催 |
昨年10月29日、栃木県農村総合整備事業促進協議会では、会員市町及び県関係者の参加を得て千葉県香取市農事組合法人和郷園(木内博一代表理事)の先進地視察研修を開催した。
近年の農村総合整備事業における技術開発や自然循環型農業の先駆的取組みの事例として、9月2日の栃木県農村総合整備事業促進協議会幹事会で詳細決定を行い今回の研修の運びとなった。
和郷園では最初に、食品残渣や畜産排せつ物をコンポストにするリサイクルセンターと液肥からメタンガスを発生させ利活用を図るバイオマスプラントを見学した。
バイオマスプラント【背後の黒い装置がメタン発酵槽】
続いて、和郷園本部に移動し事業活動について、(1)農産物の計画生産販売、(2)調整のための加工事業(冷凍、カット野菜)、(3)リサイクル事業(堆肥、液肥、エネルギー)、(4)海外の取組み等の説明を受けた。平成20年度の野菜生産において、大葉が全体の約5割を占め、大根・サンチュ・ミニトマト・とまと・人参・ごぼうと続いている。また、年間の生鮮野菜の売り上げが15億円を超えていると説明があった。また、平成16年にユーレップギャップ(EUREPGAP:ヨーロッパ小売業組合農業規範)を我が国で初めて取得している。EUREPGAPとは、食品の質を保証するとともに、人間・環境に負担のない食品産業を追求することを目標とした国際的な適正農業規範のことで、和郷園では世界を見据えた先進的な取組みが行われていると実感した。
冷凍野菜工場(さあや'Sキッチン)では、生鮮野菜を現地で直接冷凍加工している。主に、ほうれん草・小松菜・大和芋・枝豆・ブロッコリーといった野菜を取り扱っている。私たちの研修時は、さつまいもの冷凍加工が行われていた。工場長の話にもあったが、製造ラインを見ていると、栽培管理のもとに収穫された農産物を衛生管理して農産物加工製品として生産されていることがわかった。
和郷園から農産物の製品出荷が行われ、製品の一部はカットセンターや冷凍加工センターで加工品として製品化される。残渣は、リサイクルセンターへ集積され堆肥として生産農家へ還元するといった一連の循環型農業の工程を確認することができた。
和郷園の佐藤正史理事より各施設の説明を受け、参加者全員が積極的に意見交換を行い、多くの情報を得ることができた。
帰路において、本協議会幹事長である那珂川町農林振興課山本勇課長より、「今回多数の参加により視察研修を実施し無事に終了することができた。今後とも、協議会においては、会員市町の意見を踏まえて視察研修を推進していきたい。」と挨拶をいただき、一日にわたる研修が終了した。
佐藤理事より組織概要の説明(和郷園本部)
| 利根川水系農業水利協議会現地研修会が開催 |
昨年11月16日(月)利根川水系農業水利協議会(本部)主催による現地研修会が、(独)水資源機構「利根大堰」(埼玉県行田市)及び国土交通省関東整備局「首都圏外郭放水路」(埼玉県春日部市)において、会員等48名が参加して開催された。
【独立行政法人 水資源機構『利根大堰』】
利根導水路事業は、東京都をはじめとする首都圏の水需要の急激な増加に応えるため、利根川水系の総合的な水資源開発計画の一環として、昭和36年に水資源開発促進法及び水資源開発公団が成立され、その後、東京オリンピックを控えた昭和38年に工事が着手されたもので、事業の目的は下記の3つがある。
(1)利根川上流のダム群により開発した都市用水を武蔵水路及び荒川を経由して東京都・埼玉県に導水する。
(2)利根川中流部に展開する約29,000haの水田に安定的に灌漑用水を供給する。
(3)緊急かつ暫定的に利根川の余剰水を取水して隅田川の河川浄化を行う。
都市用水の暫定取水は、昭和39年8月から東京オリンピックに合わせて荒川に緊急取水され、武蔵水路完成後の昭和40年3月からは、見沼代用水元圦からの利根川余剰水の通水を行った。
利根大堰完成後の昭和43年4月からは、農業用水・都市用水等の本格的な取水が開始されている。
また、利根大堰右岸地下に設置されている魚道自然の観察室では、アユ、マス、コイ、サケ等の遡上が確認できる。
利根大堰
【国土交通省関東地方整備局『首都圏外郭放水路】
利根川と荒川に挟まれた中川・綾瀬川流域は、両河川地域と比べ地盤が低く水がたまりやすい地形で、昔から両河川の洪水のたびに浸水被害に悩まされていた。
しかし、急激な都市化により洪水被害を防ぐ河川整備や下水道整備が追いつかず、過去と比較にできないほど甚大な被害を受ける恐れがある。
首都圏外郭法水路は、中川、倉松川、大落古利根川などの中小河川の洪水を地下に取り込み、地底50mを貫く総延長6.3kmのトンネルを通して江戸川に流す世界最大級の地下放水路である。日本が世界に誇る最先端の土木技術を結集し、平成18年6月におおよそ13年の歳月をかけて、大落古利根川から江戸川までの通水が可能になった。
庄和排水機場には、地下トンネルから流れてきた水の勢いを弱め、江戸川にスムーズに排水を流すため、地下約22mの位置に長さ177m、幅78m、高さ18mにおよぶ巨大な調圧水槽が造られている。
その巨大水槽には、長さ7m幅2m、高さ18m、重さ約500tの柱が59本もあり、水槽の天井を支える光景は、まさに地下にそびえるパルテノン神殿を思わせる。
首都圏外郭放水路では、事前予約による一般見学が可能である。
◆外郭放水路 TEL 048-747-0281
同協議会では、水利情報の収集及び提供、農業用水の確保、渇水対策などの諸問題を検討、協議するため活動を続けています。
調圧水槽
| 栃木県農業集落排水事業連絡協議会視察研修を開催 |
昨年11月17日、栃木県農業集落排水事業連絡協議会では、管理組合及び会員市町の参加を得て群馬県太田市下田中地区農業集落排水処理施設の先進地視察研修を行った。
全国の農業集落排水施設数は、約5,000地区に及んでおり、今後、長期経過施設の更新需要が増加すると想定されることから、農業集落排水処理施設の処理方式の切替改築事例の先進的な取組み事例を研修対象として、第2回役員会で詳細決定を行い今回の研修の運びとなった。
下田中地区農業集落排水処理施設に到着後、太田市上下水道局下水道施設課平野課長より太田市の農業集落排水処理施設の概要について、市内には12地区の農業集落排水処理施設が稼動し、下田中地区は、平成3年に供用を開始して市内で最初の施設である説明を受けた。
表ー1 下田中地区の実施状況
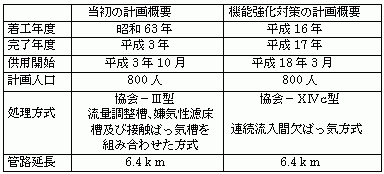
続いて、切替改築工事の計画・設計を担当された、水土里ネット群馬より地区及び工事概要について説明を受けた。
当初は、流量調整槽、嫌気性濾床槽と接触ばっ気槽を組み合わせた協会−III型と呼ばれる生物膜法の施設であったが、水槽部のコンクリート防食を行っていなかったことにより、水槽内部の劣化が進行している状況であった。このため、機能強化事業により処理施設の機能低下の回復を図るとともに、処理方式を協会− XIVG型の活性汚泥方式に変更した。この取り組みは、全国で一番最初の切替改築地区として実施された。
この下田中地区の切替改築の特徴として、(1)既存の処理水槽を活用して工事が行われたこと。(2)工事期間中は、仮設の膜処理による水処理施設を配置して汚水処理を実施したこと。(3)防食工事や接触材の搬出工事を行うこと。から、水槽の天井(鉄筋コンクリート)を撤去して、再度、天井を設けたことの説明を受けた。併せて、中継ポンプ施設のコンクリート劣化の補修も実施し、FRP性の人孔更生材料でライニング処理を実施していた。
工事概要の説明(水土里ネット群馬より)
続いて、切替改築の状況について保守点検担当者より説明があり2班に分かれて、前処理施設、流量調整施設、生物処理施設、沈殿施設、消毒・放流施設、汚泥処理施設及びブロワ施設について説明を受けた。
前処理施設のある地階
(切替改築に伴い、新たに配管や機械設備が配置されている。)
本施設には、脱臭装置が設けられているが、ばっ気槽の蓋を開けた際に、温泉たまごのような独特の臭気は感じられなかった。また、保守点検担当者の方が、放流水をひしゃくで汲み上げて見せてくれたが、透視度は100cmを超えるような清澄感が確認できた。
切替改築により、処理水質が向上し公共用水域の水質改善が図られるとともに、臭気が抑制されたことにより、周辺環境の改善に寄与できたことがわかった。
消毒・放流施設
この日は、小雨まじりの中での視察研修でもあったが、太田市、水土里ネット群馬及び保守点検担当者の説明を熱心に聞き入るとともに、切替改築にあたっての工事中の状況や維持管理の留意点、そして、地元負担金についての質問等について意見交換を行った。
帰路において、本連絡協議会高橋森一会長より挨拶があり、「多数の参加により視察研修を実施することができました。施設の老朽化に伴う改修は、太田市に限らず栃木においても重要なテーマになっていきます。そのような中で、切替改築工事の機能強化事業の実例を確認することができました。今後は、既存施設の有効活用や長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減する手法は重要になっていく。」と話された。
また、「政権交代により現段階における農業集落排水事業の動向は不透明ですが、これからも各管理組合、県及び関係市町の方々のご協力を頂きまして事業推進を図っていきたい。」と述べられ、視察研修も有意義に終了することができた。
| 疏水サミットin熊本2009が開催される |
食料生産や環境保全など農業用水の持つ多面的な役割を多くの人々に理解してもらい、先人達が守ってきた資源を次世代に伝えようと、全国水土里ネット及び熊本県並びに水土里ネット熊本の主催による「疏水サミットin熊本2009」が9月2日熊本市の崇城大学市民ホールにおいて、全国の疏水・行政関係者など約1,200人が参加して開催された。
午前中には、疏水ネットワーク総会が開催され、平成20年度事業及び決算報告と平成21年度事業計画及び予算が承認・可決されたほか、役員改選では、本会の大久保会長が監事に選任された。さらに、次回の開催県を兵庫県とすることを決定した。
サミットは、午後1時に開会し、荒木泰臣会長の開会挨拶に続いて、蒲島郁夫熊本県知事が開催県の歓迎挨拶、幸山政史熊本市長が開催市の歓迎挨拶を述べた後、来賓挨拶を齋藤晴美農村振興局次長が述べた。
次に基調講演として、大山のぶ代氏が「たかが水・されど水」と題して、自身の体験や祖母などの教えを紹介しながら、水の大切さや疏水の意義などを講演した。熊本市碩台小学校の生徒による水をテーマとしたミュージカル「セイスフェアリー」(節水等の啓発教育活動)を上演した。

その後、「過去から未来へ、ふるさとの水とみどりを守り育む」をテーマとしたパネルディスカッションが行われ、林良博東京大学大学院農学生命科学研究科教授をコーディネーターに、パネリストには、齋藤晴美農村振興局次長、市川勉東海大学産業工学部環境保全学科教授、今坂智恵子熊本市水保全課長、甲斐純一郎黒川・白川河川流域水土里ネット連携協議会事務局長、高尾雅光サントリービジネスエキスパート株式会社環境活動部長が就いた。
ディスカッションは、2部構成で進められ、第1部では、「先人の努力」をテーマにして、甲斐氏が「熊本疏水の歴史と農業の発展について」と題して加藤清正公が開削した鼻ぐり井手、国の重要文化財に指定されている通潤橋などを紹介した。続いて、齋藤局次長が「世界の水事情と我が国の農業用水」と題して、地球上に存在する水の0.001%しか利用できない中で、人口増加や気候変動などにより不足ぎみであることや、我が国が世界でも希少な水循環を水田農業を通じて達成している一方で、食料の輸入を通じて世界から多量の水を輸入していることなどを説明した。さらに、市川教授は「熊本の地下水と農業」と題して、熊本市の湧水の水源地の白川郷の宅地化により地下水量が減少していることを紹介した。
第2部では、「水資源を未来にどうつなぐか」をテーマにして、高尾部長が「サントリーの水資源保全の取組」と題して、「水と生きるサントリー」をコーポレートメッセージとして、水源を守り育み、水を大切に使う、水を奇麗にして還元するための様々な活動を紹介した。続いて、今坂課長が「熊本地域協働で取り組む水保全活動」と題して、熊本市の上水道はすべて地下水であるため、地下水保全都市宣言を行い、白川郷の休耕田の水張交付金を出していることや家庭用及びビニールハウス雨水浸透枡の設置義務、家庭用雨水タンク設置補助、熊本水遺産登録制度、くまもと水検定、水守認定登録制度、熊本地域地下水保全活用協議会、日本水大賞グランプリ受賞、平成の名水百選に入っている水前寺江津湖及び金峰山湧水群などを紹介した。
討論では、農業用水は、文化や歴史と結び付き、水と緑を守る環境施設であるとの認識で一致し、「国民の理解を得て施設の維持管理をすべき」とか「貿易均衡を保ちつつ、国内農業を守る方策の検討が必要」などの意見が出された。最後に、次期開催県の紹介が行われて閉会した。
翌日の現地研修は、上井手用水・南阿蘇村疏水群コースと通潤用水コースの2コースで開催され、参加者は、前日に紹介された歴史的遺跡を体感していた。
| 下田原南部地区記念碑除幕式及び竣工式 |
この度、県営経営体育成基盤整備事業 下田原南部 地区が竣工の運びとなり、去る平成21年10月20日、宇都宮市下田原町地内において記念碑除幕式及び竣工記念式典が挙行された。
式典には、栃木県知事代理の粂川元一参事兼河内農業振興事務所長、宇都宮市長代理の手塚英和経済部長、五月女裕久彦県議会議員、本会会長代理の大久保幸雄専務理事他、多数の来賓と齋藤悟下田原南部土地改良区理事長をはじめ多数の役員及び組合員が出席する中、盛大に挙行された。
◆事業概要◆
事業名 県営経営体育成基盤整備事業
下田原南部 地区
事業実施年度 平成15〜20年度
事業受益面積 66ha(地区面積:85.4ha)
総事業費 7億1千3百万円
組合員数 94名
| 関東一都九県土地改良事業団体連合会協議会 秋季総会・提案要望活動が開催 |
昨年10月23日、平成21年度関東一都九県土地改良事業団体連合会秋季総会が東京都千代田区平河町ルポール麹町において開催され、関東農政局、各都県水土里ネット関係者が出席した。
冒頭に当番県の水土里ネットながの中原正純会長から、「政権交代により農業農村整備事業は厳しい条件化に晒されており、培った英知で難局を打開しなければならない。」と挨拶があり、また、来賓として佐藤昭郎参議院議員より、「平成22年度は、新政策である農家戸別補償に農業農村整備事業予算を削減して充当することも想定されるため、現場の声を上げることが肝要になる。」と挨拶があった。
議事は、平成21年度農業農村整備事業推進に関する提案・要望等について審議され、原案通り承認・可決された。
第1号議案 国に対する提案・要望について
(1)提案・要望書(案)について
(2)提案・要望行動実施計画(案)
について
(3)提案・要望先(案)について
第2号議案 次期当番県について
総会終了後、本県は案内県として茨城県・山梨県と関東農政局に対して、提案・要望を行った。提案・要望は次の通りである。
提 案 書
(秋季総会における議決事項について)
I.現状と課題
関東地域は、都市化が進展する首都圏のほか、自然豊かな中山間地域や島しょも多く存在し、首都圏という巨大な消費地を有する地域特性を活かし、消費者ニーズに対応する多様な農業が展開されてきている。
このような状況の下、農業・農村の現状は、都市化・混住化の進展にともない、生産基盤としての農地の減少・担い手の高齢化、後継者不足に加えて、農産物価格の低下や食料自給率の低迷などの深刻な問題を抱えている。
また、集落機能の低下等により、地域共同の農地・農業用水等の保全管理体制の脆弱化等、様々な課題に直面している。
その一方で、世界の食糧事情は、穀物価格の高騰や輸出規制の広がりなどの現象が起きており、食料供給力の強化は喫緊の課題となっている。
このようなことから、関東地域における農業・農村の整備・振興をこれまで以上に進めていく上で、次のような具体的な課題がある。
1.農業農村整備事業推進上の課題
農業の持続的発展や食料の安定供給並びに食料自給率向上等に向けて、新たな食料・農業・農村基本計画の策定が進む中で、国内生産の増大を図る農業構造改革を進め、資源保全活動などを通じて農業・農村の持つ多面的機能を発揮させる上で、農業農村整備事業は、最も重要な施策である。
また、農業農村整備事業は、農業や農業者に裨益するのみならず、農業の国際競争力の強化、国民の食に対する安全安心の確保などに大きく貢献するものであり、国民全体にその利益が及ぶものである。
このまま予算が削減されると、農政課題の解決のみならず、食糧供給基盤の維持に支障を来たしかねないことを大いに懸念しているところである。
今後、農業者のみならず国民全体の利益のため、経営所得安定対策等大綱に即して構造改革を加速するとともに、安心安全な食料供給基盤と地域づくりを進めるのに必要な、国営事業をはじめとする予算を確保し、国と地方の緊密な連携により、重点的・計画的に推進していくことが必要となる。
2.土地改良施設の更新・管理上の課題
近年多くの地域において、標準耐用年数を超えた基幹水利施設等が増加の一途をたどることから、更新整備に要する事業予算の確保とともに、土地改良区が行う保守点検による管理体制の整備費や部分的な整備補修等の維持管理費が課題となっている。
また、このような課題を推進するためには、地域住民の理解と参画を得つつ、円滑に推進するための手続の改善など、情勢変化に応じた土地改良制度の早期改正が課題となっている。
3.農地・農業用水等、地域資源の保全における課題
農地・農業用水及び農村の多様な生態系や景観などは、これまで農家中心とする地域共同活動により形成・保全管理されてきたが、農村の高齢化、混住化などによりその適切な保全管理活動が困難となってきている。
また、都市と農村の交流などによる新しい地域振興の芽が育ちつつあるが、その活動に対する支援の充実が必要となっている。
平成18年度から、全国的に、地域の実情に応じた地域ぐるみで行う農地・水・環境向上対策の活動が展開されているが、この活動の柱となっている地域協議会などに対する支援の継続と一層の充実が課題となっている。
4.土地改良事業団体連合会の体制強化に向けた課題
土地改良事業団体連合会は土地改良事業を行う者の連合体として、行政と一体となって農業農村整備全般の推進に大きな役割を担ってきた。
近年、公共事業費の減少や財政の逼迫化、更には契約制度の運用見直しなどにより、その運営基盤や事業実施体制が脆弱化してきている。
今後、食料自給率の向上に向けた構造改革に資する耕作放棄地対策、農地の利用集積、及び農地・水・環境向上対策等の推進、並びに情報化の推進、更には品確法を踏まえた市町村などへ工事発注事務の支援の推進などを一層図っていくこととしており、このために必要な体制整備、機能強化にどう取り組んでいくかが課題となっている。
II.事業推進に関する提案
1−1.農業農村整備事業の予算の確保と土地改良制度の確立
・ 農業構造改革の加速化、安全安心な食料供給基盤の確保と地域づくりの推進を通じて、わが国農業の国際競争力の強化、国民生活の安全安心の確保、環境の保全向上を図るのは国の責務であり、そのためこれらに直接裨益する国営事業をはじめとする農業農村整備事業の継続的な実施が必要であるので、現在の農業・農村の基盤が崩壊しないよう、必要な予算の確保と、併せて施策の展開を図られたい。
・ また、国民への食料の安定供給や食料自給率の確保に鑑み、農地の確保や基盤整備の推進については、公的関与の拡大と諸事業制度の維持強化を継続的に図られたい。
・ 農業情勢の変化に沿って、農業・農村の整備が円滑に図られるよう適切な土地改良制度の確立を図られたい。
1−2.農政改革のための基盤づくりの推進
(1)水・土・里を守るために必要な農業生産基盤整備事業の重点的・計画的な推進
・ ほ場整備事業、かんがい排水事業、畑総事業等の推進
・ 低コスト整備手法の導入や、住民参加型手法の活用等、画一的な整備から弾力的整備への転換の推進。
(2)地域資源の多面的機能を活かした総合的基盤づくりの推進
・ 地域の個性、創造力を生かした農業戦略や地域づくりを実施する農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の確保と拡充。
(3)耕作放棄地の解消に向けた総合的な取り組みの推進
・ 食料の安定供給と優良農地の確保を図るため、耕作放棄地の発生防止・解消に向けた総合的な取り組みを推進されたい。
・ 更に耕作放棄地の解消と面的集積を加速するため、農地に関する地図情報の整備の拡充を図られたい。
(4)食料供給力強化に向けた取り組みの推進
・ 食糧供給力の強化を図るため、農地有効利用支援整備事業を確実に推進されたい。
2.土地改良施設の更新・管理に対する支援
(1)ストックマネジメントの技術的確立と予防保全対策の実施
基幹水利施設から末端施設に至る一貫した保全管理システムの構築のためには、施設劣化の将来予測や予防保全対策に係わる事業予算の継続的な確保を図られたい。
(2)土地改良施設維持管理適正化事業の推進
本事業は、土地改良施設の定期的な整備補修を行い、土地改良施設の機能の保持と耐用年数の確保に資するものであり、事業予算の継続的な確保や事業制度の拡充を図られたい。
3−1.地域資源を活かした活力のある地域づくりの推進
(1)農業農村排水事業の推進
・ 農業用用水排水の水質保全や農村生活改善及び地域資源循環の向上を図るため継続的に推進されたい。
(2)農業水利施設を活用した小水力発電整備事業の推進
・ 農業水利施設の持つ自然エネルギーの効率的な活用を図るため、小水力発電整備事業を継続的に推進されたい。
(3)質の高い居住空間を形成するための田園空間整備事業の積極的な推進
・ アメニティ豊かな居住文化の創造は農村固有の特性であり、この特性を活かす田園空間整備事業を継続的に推進されたい。
(4)都市との交流を促進する農村環境保全整備の推進
・ 地場産品の販売、農業体験や自然環境を手段とする経済活動を興すため、生態系の保全や農村景観、更には歴史的風土を保全する取り組みを推進されたい。
3−2.農地・水・環境向上対策の推進
農村は、伝統文化や環境を守り、良好なコミュニティを維持するなど、多面的機能を有し、国民全体が享受されるものである。
4.土地改良事業団体連合会(水土里ネット)の体制強化の推進
(1)水土里ネットの特性を活かした体制強化への支援
市町村、土地改良区等を会員とする水土里ネットは、行政と一体となって農業農村整備を推進してきており、その計画、実施、施工、管理に必要な農業土木技術のみならず、農業経営の改善、農地の利用集積、農村環境資源の保全、地域コミュニティの活性化など、多くの分野にわたる技術や行政ノウハウを総合的、系統的に有しており、農業の発展、農業・農村の振興を図る上で不可欠な公的技術集団である。したがって、水土里ネットのこのような特性は必要不可欠であり、事業の実施にあたり十分活用できうるような体制づくりに配慮されたい。
(2)水土里情報利活用促進事業とGISシステム運用への支援
・ 本事業は農地の利用集積計画、施設の保全・更新計画、地域防災計画等の策定など、水土里ネットの新たな展開方向を築くものであり、農地情報図と農地情報の早期整備が求められておりますので、事業の円滑な推進に資するため、指導を強化されるとともに、その維持管理体制への支援制度を図られたい。
・ GISを活用するためのメニューの創設
農地情報共有化支援事業での支援ソフトの導入や、農業水利施設管理事業等においてGIS化する経費を補助の対象とする制度を創設されたい。
(3)ストックマネジメントに対応する新たな土地改良施設管理センターの構築と支援
・ ストックマネジメントの効率的運用を図るためには、水土里ネットを地方の拠点とする土地改良施設管理センターとして構築することがより効果的である。ついては、土地改良施設機能更新等円滑化対策事業の展開等、将来に対処する取り組みを推進されたい。
・ ストックマネジメントの推進のためには、施設状態の将来予測、予防保全対策工法の検討、ライフサイクルコストの算定、最適運用計画の策定などが必要となることから、土地改良事業団体連合会や土地改良区、市町村がこうした技術を修得することに対する支援を図られたい。
| 関東地区農村総合整備推進連絡協議会理事会 及び第36回通常総会を開催 |
昨年10月23日、東京都千代田区平河町ルポール麹町において、関東地区農村総合整備推進協議会理事会を一都九県の関係理事のもと、当番県である水土里ネットながの中原正純会長による議事進行により、開催された。
その後引き続き、第36回通常総会を、同中原会長による開会宣言で始まり、泉原明関東農政局整備部地域整備課長を来賓に招き、「政権交代により概算要求等の説明は差し控えたい。必要な情報については、農林省のHPより確認をしていただきたい。」と挨拶された。
議事は、中原会長を議長に選任して進められ、平成20年度事業報告、同収支決算、平成21年度事業計画、同収支予算、同負担金の負担方法及び納入時期、国に対する提案及び要望事項、役員の選任について、各原案どおり承認・議決した。
総会終了後、承認された提案書・要望書を農林水産省・国会議員・農林水産省(農村振興局)・関東農政局へ要請活動をそれぞれ行った。

| 第32回全国土地改良大会が島根で開催 |
本年度の開催が第32回の開催となる全国土地改良大会は、全国水土里ネット及び水土里ネットしまねの主催、農林水産省、島根県、松江市の後援により、去る10月28日に島根県松江市のくにびきメッセにおいて、全国の土地改良関係者など、およそ3,600人が参集して盛大に開催された。本県からは、土地改良区の役職員並びに本会役職員の総勢28名が参加した。
島根大会の開催趣旨は、大会テーマに『国引きのロマン、水・土・里の想い。神話の郷から今、未来へ』を掲げ、食料の安定供給や食の安全・安心が大きな関心事となっている昨今、農業生産を支える農地や農業用水路などを維持・保全・整備する農業農村整備の重要性を広く国民にアピールするとともに、土地改良法制定60年という節目の年に、今一度、「水・土・里」の想いを再認識し、共生・循環・持続する国のかたちづくり、地域づくりについて語り合うことを目的に開催された。
大会のオープニングは、地元島根県出雲市出身のオペラ歌手、錦織健氏「さくら さくら」(日本古揺)・「誰も寝てはならぬ」(プッチーニ「トゥーランドット」より)の独唱が披露され、会場を大いに盛り上げた。
続く大会式典は、水土里ネットしまね宇津徹男副会長の開会宣言で島根大会の幕がきって落とされた。まず、国歌斉唱が、オペラ歌手、錦織健氏のリードにより、厳かな中に全員で唱和した。これに続いて、青木幹雄水土里ネットしまね会長の開催県挨拶、野中廣務全国水土里ネット会長の主催者挨拶と続き、溝口善兵衛島根県知事の歓迎挨拶があり、来賓を代表され、郡司彰農林水産副大臣からの祝辞があった。
土地改良事業功績者表彰においては、長年にわたって土地改良事業に貢献された方の表彰式が執り行われ、農林水産大臣表彰6名、農村振興局長表彰16名、全土連会長表彰47名の方々が受賞の栄に浴された。本県からは、本会の吉澤新市理事鬼怒川右岸土地改良区理事長が全土連会長表彰の栄に浴した。
この後、農業農村の振興に向けた優良活動事例の映像紹介、齋藤晴美農村振興局次長による基調報告、島根大学生物資源学科学部4年次生の影山浩樹さんと丸田恵理子さんによる「神在月の今日ここに集う関係者は、健全な水・土・里を守ることにより、食料・水・エネルギーの資源供給を担うばかりでなく、国土を保全する重要な責務をも担う者として、国民の負託と信頼に一致団結して応えていくことを、日本国の黎明の歴史を今に伝えるここ島根の地において宣言する。」などとした大会宣言が力強く行われた。
大会も終盤を迎え、次期開催県紹介では、長崎県のPRビデオが上映され、大会旗が水土里ネットしまねから全国水土里ネットへ、さらに水土里ネット長崎へと引き継がれたところで、宮本正則水土里ネット長崎会長が次期開催県挨拶を行い、『伝えよう水の音色・土の温もり・里の安らぎ・西端の風にのせて』をテーマに、来年10月26日に長崎県島原市で開催したい。皆様のお越しをお待ちする。」と述べた。
結びに、吹田全国水土里ネット副会長が閉会の0挨拶を述べて滞りなく式典の幕を閉じた。
式典終了後、歓迎アトラクションとして、島根県を代表する石見神楽が披露され、会場を大いに沸かせた。
また、本県参加団は、10月27日〜29日の3日間に視察研修を実施し、足立美術館・出雲大社御本殿大屋根特別拝観・松江城・小泉八雲記念館・水木しげるロード等を見学した。
開会挨拶をする野中廣務全国水土里ネット会長
参加者全員で記念撮影

全国水土里ネット会長賞 【吉澤新市氏の略歴】
昭和7年3月12日生まれ、77歳。宇都宮市柳田町在住。
昭和58年の平石東部土地改良区設立と同時に副理事長として参画し、平成11年より同土地改良区理事長に就任。
平成15年8月から石井川土地改良区理事長に就任し、平成18年4月に新設合併を行い、新生・鬼怒川右岸土地改良区の初代理事長に就任し現在に至る。
併せて、平成15年8月から鬼怒中央土地改良区連合理事長に就任し現在に至る。
平成21年4月から栃木県河宇土地改良協議会長並びに本会理事に就任し現在に至る。
他に、昭和56年から宇都宮市農業委員会委員を7期21年間務め、その間に農地部会長並びに農政部会長などの要職に就くとともに、全国農村青少年先進地農家留学生研修受入指定農家、栃木県野菜園芸技術研究会理事及び同研究会名誉会員等となって、農業後継者の育成にも尽力された。
| 「水と緑の里山ウォークin矢板」を開催 |
本会は、昨年11月1日、矢板市山田及び東泉地内において、山田土地改良区、東泉土地改良区、泉地区土地改良区及び栃木県21世紀土地改良区創造運動推進本部との共催により、一般県民から募集した親子づれなど約90名の参加を得て「水と緑の里山ウォークin矢板」を開催した。
このウォーキングは、本年度から本会が取り組んでおります「農業用水水源地域保全対策事業」の一環として、私たちの命を繋ぐ安全・安心な食料を生産するためになくてはならない農業用水と、これを育む水源林との関わりについて県民の理解を深めていただくことを目的に開催した。併せて、農業用水の管理に深く関る水土里ネットの果たす役割や活動についても知っていただくために、21世紀土地改良区創造運動としても実施した。
当日は、天候にも恵まれ、青空のもと、山田堰、圃場整備事業の実施において生態系の保全に配慮した工法によって整備された生態系保全水路、水源の森高原山の伏流水を使用する森戸酒造や文化財などを巡る約9.1kmのウォーキングを通じて、農業用水の役割やそれを育む水源林の大切さ、水土里ネット(土地改良区)の働きや農業農村整備事業等を紹介した。
今回のサプライは、東泉農村公園での昼食に、共催する地元3水土里ネットの婦人の方々が地元産の食材に腕によりをかけた栗ご飯や豚汁を準備し、地産地消による秋の味覚を楽しんでいただいた。また、ゴール後には、試食用に矢板市産のリンゴとたかはら米を配布するなど、豊かな実りから農業用水の大切さや水を育む水源林の大切さを感じ取っていただいた。
参加者からは、「農作物を育てるのと同じように水を管理することの大切さが理解できた。」、「生態系保全水路などは、参加して説明されなければ見逃してしまうので、勉強になった。」、「農業、農村の重要性、大切さをもっとPRしていくべき。」など、沢山の感想が寄せられ、大変盛況であった。
開会式では、主催者を代表して本会篠崎享雄事務局長が挨拶に立ち「本日は、このウォーキングを通じて、農業用水の大切さや水源林の役割、土地改良施設の役割とこれを守る水土里ネットの活動について、認識していただき、理解を深めて頂きたい。」と述べた。
次いで、津久井良樹矢板市経済建設部参事兼農務課長は、「矢板市は、高原山に象徴されるように水と緑豊かな自然と触れあえるまちづくりを推進しており、当地区も、ご覧のように環境と調和の取れた圃場整備を進めてきたところです。この豊かな自然を満喫していってください。」と歓迎の挨拶を述べられた。
ウォーキングは、ラジオ体操で体をほぐした後、本会の福田信博総務部長が天然記念物指定のミヤコタナゴと下の問屋の千年カヤについて説明を行って、水土里ネットの幟旗を持ったスタッフの先導により、最初の見学地・山田堰をめざして出発した。一行は、稲の刈り入れの終わった田園の中を進み堰に到着すると、堰管理者の平石充山田土地改良区理事長から堰の歴史や管理状況等の説明を受け、参加者は300年余の歴史に驚き感銘を受けていた。また、この時期、まだ水量のある箒川の流れが奏でる旋律に暫し身体を委ね、清々しい空気に包まれ、無我の中で自然と一体となり心身のリフレッシュを図っていた。

堰を後にした一行は、次の見学地の生態系保全水路を目指し、県営中山間地域総合整備事業で整備のなった圃場整備地区の中、農道を周囲の里山の景色を楽しみながら進だ。生態系に配慮して整備した水路の前で、本会の野澤伸輔次長兼会員支援課長が、土地改良事業の概要、施設の概要などの説明を行った。次の鏡山寺では、同寺が所蔵する県指定文化財の阿弥陀如来坐像画を見学させていただき、坂井隆雄住職の説明に熱心に聞き入り、質問も出された。
東泉農村公園での昼食は、地産地消をテーマに地元矢板市産の食材を使用し、共催する3水土里ネットの婦人の方々に腕を振るって調理していただいた栗ご飯や豚汁に舌鼓をうちながら自然の中での食事のひと時を楽しんだ。料理は、お代りする方が続出で、大変好評であった。参加者には、お腹も心も満足していただいた。
最後の見学先の森戸酒造では、森戸康雄代表取締役の案内で3班に分かれて酒蔵を見学した。新酒の仕込み前でありましたが、酒造りの工程や氏の原材料すべてに地元産をこだわった酒造りなどの説明を受け、熱心に聞き入り質問も出された。また、蔵元の直売所では、お土産を買い求める人だかりが賑わいを見せていた。
ゴールの山田公民館では、当地域の特産品のリンゴとたかはら米が手渡された。朝のうち心配された天気も回復し、ウォーキングには絶好の天候となり、全行程9.1kmのコースであったが、全員が完走し、心地好い疲れと豊かな自然を満喫した清々しい一日に満足した様子であった。


| 関東地区農村総合整備推進事業研修会 並びに農業集落排水事業研修会に参加して |
昨年11月12日・13日、長野県長野市サンパレス山王において「平成21年度関東地区農村総合整備推進事業研修会並びに農業集落排水事業研修会」が開催された。
研修会は、当番県である長野県土地改良事業団体連合が主体となり下記のカリキュラムで実施された。各講座では農村総合整備推進事業・農業集落排水事業の概要、長野県内の農村の活性化、地域の環境修復への取組みや地燃料システムの開発研究についてパワーポイントによる説明と現地見学が2日間に亘る大変有意義な研修会であった。
◎研修会内容
○地域整備課所管事業について
農業集落排水事業関係
低コスト型農業集落排水施設更新支援事業
農業集落排水水質保全効果発揮促進事業
関東農政局整備部地域整備課 農業集落排水係長 会澤 俊彦
平成21年度新規事業の概要
新規需要米生産製造連携関連施設整備事業
低炭素むらづくりモデル支援事業
農村振興総合整備推進事業
関東農政局整備部地域整備課 農村整備係長 恵美須 美生
○低コスト型農業集落排水施設更新支援事業について
管路施設の調査方法
(社)地域資源循環技術センター 田中 正
○中山間地域の活性化事例について〜川上村の挑戦〜
地域条件を生かした取組みと農作物のPR・市場開発
長野県南佐久郡川上村 産業建設課長 中島 修
○野尻湖の植生復活事業について
水草帯復元研究会の活動
上水内郡信濃町 教育委員会学芸員 近藤 洋一
○地域完結型地燃料システムと地域循環型社会
バイオエタノール製造実験事業
(株)総合環境研究所 所長 高山 光弘
| 命を「いただきます」 水土里ネットとちぎ 総務部会員支援課 高橋伸拓 |
ある報道で「小学校の給食」が取り上げられていた。内容は、給食費を納めているのだから「いただきます」と言うのがおかしいとの保護者の意見があるということであった。何に対して「いただきます」と言おうとしているのか。飽食の時代を象徴する考え方なのだろうか。私たちは山、農村、海からの食料により生かされている。我々の食料となる動植物すべてには命があり、それらをいただくことに対する感謝は、忘れてはならないことである。
そのような中で内陸農村部では、田んぼまわりの動物を貴重なタンパク源として食してきた文化がある。そういった文化を現在に伝える取り組みが「環境教育」として広まりつつある。田んぼまわりで食されていた動物は、魚ではドジョウ、昆虫ではイナゴが代表的ではないだろうか。しかし今の若い世代や子供たちは、それらを食材としなくても十分に栄養を摂取することが出来ている。実際に子供たちを交えた生きもの調査等のイベントで質問すると、ほとんどの参加者は食べたことがない。
栄養価が高いこれらの生きものは農業が育む。農作物の生産現場からは複利的な田畑まわりの生きものを食すことで命の大切さを学び、農業および農村環境への理解が生まれるのではないだろうか。ひいては、農村部に形成される二次的自然の保全や人間社会との共生につながり、地域文化の継承が持続的に行われるようになるのではないだろうか。
ドジョウの唐揚げ
コバネイナゴの佃煮
| ホームページ・メールアドレス変更のお知らせ |
平成22年1月より本会のホームページURLとメールアドレスが変更となりますのでお知らせいたします。
新ホームページURL:http://www.tcgdoren.or.jp/
※旧アドレスは平成22年3月末で廃止となります。
課 名 新メールアドレス 総務課 soumu@tcgdoren.or.jp 会員支援課 kaiinshien@tcgdoren.or.jp 水土里情報センター midorijouhou@tcgdoren.or.jp 情報管理課 jouhoukanri@tcgdoren.or.jp 農村整備課 nousonseibi@tcgdoren.or.jp 換地課 kanchi@tcgdoren.or.jp 測量課 sokuryou@tcgdoren.or.jp
| 平成21年10・11・12月主要行事報告 |
10月
日 行 事 1 栃木県土地改良士部会・優良先進事例視察研修 2 平成21年度第1回農業農村整備部会 2 農地・水・環境保全向上対策グレードアップ推進講座(下都賀・安足) 16 県営土地改良事業の換地業務に係る感謝状贈呈式 17 第9回花と農産物の清南大地食の祭典 18 平成22年4月本会職員採用試験(第一次試験) 18〜30 第40回海外農業研修(秋のヨーロッパ農業研修) 19 平成22年度県農業等施策・予算に関する建議・要請会 20 下田原南部地区記念碑除幕式及び竣工式 22〜23 平成21年度北那須土地改良事業推進協議会優良先進事例研修会 23 関東一都九県土地改良事業団体連合会協議会秋季総会 23 関東地区農村総合整備推進連絡協議会第36回通常総会 23 関東一都九県土地改良事業団体連合会協議会・提案要望活動 24〜25 とちぎ“食と農”ふれあいフェア2009 27〜29 第32回全国土地改良大会島根大会 29 平成21年度栃木県農村総合整備事業促進協議会先進地視察研修 29 平成21年度農業農村整備技術強化対策事業施工技術研修会
11月
日 行 事 6 河宇土地改良協議会先進地研修会 11 全国土地改良施設管理事業推進協議会第13回通常総会 11〜12 平成21年度塩谷地方土地改良事業推進協議会先進研修会 12〜13 関東地区農村総合整備推進事業研修会・農業集落排水研修会 17 平成21年度農業集落排水事業先進地視察研修 20 生き物マップ・写真コンテスト審査会 25〜26 安足土地改良事業推進協議会・土地改良区職員等現地研修会 25〜26 平成21年度芳賀郡市土地改良区協議会・会員研修会 26 平成21年度農業農村整備技術強化対策事業一般研修会 30 平成22年度農業農村整備事業予算拡大陳情 30 平成21年度「水土里の集い」
12月
日 行 事 4 平成21年度農地連担化促進促進研修会 16 本会第3回理事会 28 仕事納め式
| 表紙写真説明 |
表紙の写真『喜びの瞬間』
○撮影者
那須拓陽高等学校 3年 高林 賢 さん
○コ メ ン ト
平成20年度「美しいとちぎのむら写真コンテスト」農業に生き生きと携わる人々の部門で見事優秀賞に輝いた作品です。
審査講評は、「収穫の喜びが良く伝わってくる。アングルを下げたことによりサツマイモの部分がアップされたことと、バックの白い空が整理された。高校生3人のバランスがよくまとまっている。」というものでした。