 |
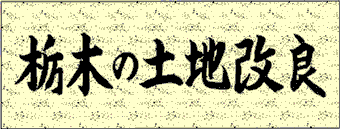 |
『水土里ネットとちぎ』は本会の愛称です

−主な内容−
 |
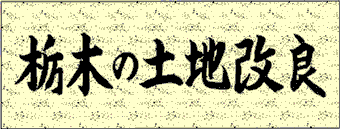 |


新年のごあいさつ 水土里ネットとちぎ
(栃木県土地改良事業団体連合会)
会 長 大久保 寿 夫
会員の皆様、あけましておめでとうございます。
今年も皆様とともに、輝かしい新年を迎えることができました。心からお慶びを申し上げます。
旧年中は、本会の業務運営に格別の御高配を賜り、衷心より感謝と御礼を申し上げます。
また、日頃から、農業農村整備事業の推進に御尽力を賜り、心から敬意を表する次第であります。
さて、昨年を振り返ってみますと、明るい話題が少なかったように思います。北朝鮮による韓国延坪島への砲撃事件、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件と海上保安庁のビデオ流出、大阪地検特捜部の郵便不正事件における証拠改ざん隠蔽や警視庁公安情報流出など、我が国の安全を脅かす問題や政府機関の不始末などが目立つ年でありました。
農業関係では、4月20日に発生した宮崎県口蹄疫では、大量の牛や豚等の家畜の殺処分が行われました。被災されました畜産農家の方々に心からお見舞いを申し上げたいと存じます。
私共、土地改良関係者にとりましては、国の平成22年度農業農村整備事業予算が対前年比36.9%と極めて大幅な削減となってしまいまして、事業の実施に大きな影響が出ることが懸念されたところであります。幸い、新設された農山漁村地域整備交付金や前年度繰越金を充当することによって事なきを得ましたが、昨年末に決定されました平成23年度農業農村整備事業予算案につきましては、対前年比100%でありまして、農山漁村地域整備交付金や非公共事業予算を含めましても、対前年比113%程度でありまして、事業実施への影響は避けられないのでないかと危惧しているところであります。
私共は、会員皆様の事業の実施に影響が出ないよう、政府与党、県政与党、栃木県など関係方面に懸命に要請して参りました。
また、会員土地改良区には、総会における特別決議をお願いし、会員市町の議会には、地方自治法第99条の意見書の提出をお願いし、県内すべての市町議会で採択していただき、政府などの関係機関に意見書を提出していただきました。誠にありがたく、ここに改めて厚く御礼を申し上げる次第であります。
しかしながら、結果は大変厳しいものでありますので、間断なく強力な要請活動を展開して参りますので、会員皆様のより一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。
農業・農村は、安全で安心な食料の供給とともに、豊かな自然、美しい景観の形成などの多面的な機能を発揮することにより、日本という美しい国を形づくり、国民生活を支えております。
その根源たる「水」「土」「里」は、先達のたゆまざる努力により育まれたものであり、これらの財産を守り、次世代に適切に引き継いでいくことが、農業農村整備に携わる私達の責務であります。
農業農村整備は、食料・農業・農村基本法の理念に即し、環境との調和に配慮しつつ、既存ストックの有効利用を重視した保全管理、農業の構造改革の加速化に資する生産基盤の整備、地域再生に資する活力ある美しいむらづくりの推進など、新たな時代に対応した使命を担う農業農村整備として強力に推進して参りたいと存じております。
末筆ながら、私共連合会は、適正な業務運営に努めつつ、国並びに県の施策に呼応しながら、会員皆様の負託に応えられるよう誠心誠意努力して参りたいと存じておりますので、より一層の御指導、御支援を賜りますようお願い申し上げます。
会員皆様の御健勝と御多幸を御祈念申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ 栃木県知事 福 田 富 一
県民の皆様、あけましておめでとうございます。
私は、知事就任以来、誰もが豊かさを実感できる“とちぎ”を創り上げるため、対話と協調による県民中心、市町村重視の県政を基本として、各種施策を積極的に推進して参りました。
昨年は、厳しい財政状況の中、自律的な行財政基盤の確立に向けた「とちぎ未来開拓プログラム」の実質的な初年度として、その着実な実行を図りながら、当面の最重要課題である「経済・雇用対策」に全庁を挙げて取り組んで参りました。また、最終年度となる栃木県総合計画「とちぎ元気プラン」に掲げた目標の達成に向け、こども医療費助成対象の拡大、保育所の整備促進など子育てしやすい環境づくりや、1月に導入した「ドクターヘリ」の効果的な活用、医師確保対策の充実など地域医療体制の強化を通じ、「安心な地域社会の実現」に努めたほか、「とちぎ環境立県戦略」に基づくレジ袋削減運動の展開など「地球と人にやさしい“エコとちぎ”づくり」や、多彩な地域資源を活かした「とちぎ食の回廊づくり」の推進など「ブランドに着目した誇り輝く“とちぎ”づくり」等に全力を傾注してきたところであります。
一方、少子高齢化の進行と人口減少の本格化、経済のグローバル化や高度情報化の進展、さらには、地球環境問題の深刻化など、私たちは今、時代の大きな変化の真っただ中にいます。加えて、円高の進行など経済情勢の急激な変動や地方分権改革をめぐる動きなど、県政を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。
県では、こうした時代の潮流や社会経済情勢の変化に的確かつ柔軟に対応しながら、目指すべき将来像を実現するため、現在、新しい5か年間計画である栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン(仮称)」の策定を進めており、本年は、このプランのもと、新たなスタートをきることになります。新しいプランでは、「とちぎ元気プラン」の成果を継承するとともに、限られた行財政資源を有効に活用するため、選択と集中による施策の重点化を図り、政策の基本に「人づくり」を据えながら、「暮らしを支える安心戦略」「明日を拓く成長戦略」「未来につなぐ環境戦略」の3つの重点戦略を展開して参ります。そして、多様な主体による協働をさらに前進させる「地域をともに創る」という考え方に立ち、県民の皆様と手を携え、「人の元気」や「産業の元気」、「元気な自然」や「元気な地域」にあふれる、「安心 成長 環境 をともにつくる、元気度 日本一 栃木県」を目指して参ります。
平成23年は、北関東自動車道がいよいよ全線開通を迎える年でもあります。近隣県となお一層連携・協力しながら、真の「有名有力県」に向け、私自らも、本県の多彩な魅力を県の内外に積極的に発信して参りますので、皆様のより一層の御理解と御支援をお願い申し上げます。
年の始めに当たり、私の所信を申し上げますとともに、本年が皆様にとって素晴らしい年となりますことをお祈り申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

とちぎの農業のさらなる飛躍に向けて 栃木県農政部長 吉 沢 崇
新年あけましておめでとうございます。
皆様には、健やかに輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、日頃から県農政の推進に深い御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
今日の農業・農村を取り巻く状況は、農業従事者の減少や高齢化、担い手不足をはじめ、農業所得の減少や耕作放棄地の増加、さらには国際化への対応など、大変厳しいものがあります。一方で、安全・安心な食料の安定供給や豊かな自然環境の保全形成に加え、職業としての「農業」が再評価されるなど、農業・農村に対する期待が高まっています。
このため国では、平成22年3月に新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定し、「国民全体で農業・農村を支える社会」の創造を新たに掲げ、「戸別所得補償制度」や「農業・農村の6次産業化」、「優良農地の確保と有効利用の促進」などを主な柱として各種施策を展開しています。
県といたしましては、これらの国の施策等に適切に対応しながら、農業者をはじめ、関係団体、消費者など県民の皆様との連携と協働の下、本県農業のさらなる飛躍を図るため、現在、新しい5か年間計画である「次期農業振興計画」の策定を進めております。この計画では、これまでの「首都圏農業」の考え方を基礎とし、本県の持つ優位性を積極的に活かしながら、プロ農家の育成や産地競争力の強化はもとより、全国へのマーケット展開や交流人口の増大に伴う県内流通の拡大、さらには、食品産業と連携した「フードバレーとちぎ」の取組を推進するなど、新たな発展の可能性を追求しながら、国際化にも対応できる「成長産業として発展するとちぎの農業」を目指して参ります。
農業農村整備につきましても、「次期農業振興計画」の基本理念を踏まえ、担い手への農地集積を基本とした地域特性に応じた生産基盤の整備をはじめ、ストックマネジメントによる農業水利施設等の計画的・効率的な保全管理や更新整備、中山間地域を含めた農村地域の生活環境基盤の整備を進めて参ります。さらには、食をテーマにブランド化や地域活性化を進める「とちぎ食の回廊づくり」、次世代に継承したい「とちぎ田園風景百選」の認定、地域の協働による農村環境の保全など、食を支え、活力と魅力にあふれる「とちぎの水土里づくり」に積極的に取り組んで参ります。
県内の社会経済情勢は、一段と厳しい状況にありますが、食料の安定供給や農業生産の一層の効率化をはじめ、美しく豊かな農村づくりを進めていくためには、農業農村整備の果たす役割が引き続き重要であり、その推進母体である土地改良区には大きな期待が寄せられています。今後とも運営基盤の強化並びに活動のさらなる充実に努め、地域農業の振興に寄与いただきたいと考えておりますので、土地改良事業団体連合会員の皆様方には、なお一層の御支援と御尽力をお願い申し上げます。
結びに、皆様方の御健勝と益々の御発展を心から祈念申し上げまして、年頭のあいさつといたします。

新年のごあいさつ 農村振興課 課長 南 斎 好 伸
新年あけましておめでとうございます。
皆様方には、御家族と共に健やかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
また、農村振興に関わる事業をはじめ、本県農政の円滑な推進に日ごろから格別の御支援、御協力をいただいておりますことに、心からお礼申し上げます。
近年、人々の価値観やライフスタイルが変化するなかで、農村のもつ「うるおい」や「やすらぎ」への関心は高く、豊かな自然や農産物など、多様な地域資源を有する農村との交流への期待が膨らんでおります。
一方、過疎化や高齢化、鳥獣被害の拡大などにより、農業・農村の多面的機能の低下、耕作放棄地の増大など地域の活力低下が懸念され、さらにCO2削減や生物多様性保全のための生産活動の推進など、地球環境問題への積極的な対応も求められております。
農村振興課におきましては、こうした社会経済情勢の変化に的確かつ柔軟に対応しながら、次期農業振興計画に掲げた施策を着実に展開するため、農産物直売所等の魅力向上や地域資源を活かした都市と農村の交流・協働の取組を推進するとともに、「とちぎ食の回廊づくり」などにも積極的に取り組みながら農村地域の活性化を図って参ります。
また、健全な農村環境の保全継承と農村地域の活性化を図る「農地・水・環境保全向上対策」については、引き続き「田んぼまわりの生きもの調査」や地域の創意工夫を活かした活動など、地域が主体の取組が継続されますよう推進して参ります。
さらに、社会全体で地球温暖化防止や環境への配慮が重視される中、農業においても多様な再生可能エネルギーを利活用することが重要であることから、関係機関団体等と十分に連携を図りながら、地域の特性に応じた、小水力や太陽光など農山村地域における再生可能エネルギーの利活用について検討して参ります。
一方、生産条件等が不利な中山間地域においては、過疎化や高齢化、野生鳥獣被害などにより、農業・農村の持つ多面的機能の維持・保全が困難になってきております。このため、安全で快適な暮らしのための生産基盤と生活環境の整備を一体的に進めるとともに、中山間地域等直接支払制度等による地域活性化に向けた活動や、都市住民・企業・大学等の多様な参画による地域資源を保全・活用するための取組や鳥獣害対策など総合的な支援を行います。
今後とも自然豊かで住みよい農村の形成をめざし、農村の様々な資源を活かした魅力ある地域づくり、快適な生活環境の整備等、各種施策を総合的に推進いたします。さらに、「田園風景百選」につきましては、1月の実行委員会で認定するとともに、2月2日の記念シンポジウムで広く紹介し、魅力ある地域づくりの場として役立て参りたいと考えておりますので、会員の皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。
結びに、本年が会員の皆様にとってすばらしい年となり、さらに栃木県土地改良事業団体連合会の益々の御発展を祈念申し上げまして、新年のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ 農地整備課長 人 見 允
あけましておめでとうございます。
皆様方には、御家族と共に健やかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
また、日頃から農業農村整備事業の円滑な推進に格別の御支援、御理解を賜り深く感謝申し上げます。
今日の農業・農村をめぐる情勢につきましては、農業従事者の減少や高齢化、農産物価格の低迷や耕作放棄地の増加など、様々な課題に直面しております。
一方、農村地域は、安全で安心な食料の安定供給はもとより、県土の保全形成に大きな役割を果たしており、これらの機能を将来にわたり発揮していくためには、今後とも、農村での健全な農業生産活動を通じて農地を維持するとともに、地域協働による地域資源の保全・整備が不可欠です。
こうした中、県としましては、国予算の大幅な縮減や県の財政が一段と厳しさを増すなかで、県民にとって最良の選択は何かという観点から、徹底した選択と集中により、活力と魅力にあふれる農業・農村をめざして、「次期農業振興計画」の基本理念を踏まえた各種施策を展開して参りたいと考えています。
特に、生産基盤の整備につきましては、水田の大区画化による生産性の向上と汎用化、担い手の育成と農地の利用集積を目的に、生態系や景観などの自然環境にも配慮し、地域の特性に応じた整備を積極的に推進して参ります。
また、農業水利施設は、食料の安定供給はもとより、国土の保全や水源かん養などの多面的機能を有し、未来に継承していかなければならない重要な社会資本であることから、今後、施設の老朽化などに伴う機能低下に備える必要があります。
このため、施設の長寿命化を図るストックマネジメント手法の考え方に基づく適切な保全管理に向け、土地改良区など施設管理者への理解促進や技術力向上及び管理体制の構築を支援し、計画的・効率的かつ経済的な施設の保全管理や更新整備を推進して参ります。
また、土地改良区については、農業水利施設の管理主体としての運営基盤強化や地域社会への貢献に対する取組を支援して参りたいと考えております。
今後とも会員の皆様や地域の皆様とともに地域農業のあり方や展開方向について議論を重ね、本県農業・農村の更なる発展を目指し、農業農村整備事業を始め各種施策を推進して参りますので、御理解と御協力をお願いいたします。
結びに、皆様の御多幸・御健勝を心からお祈り申し上げ新年のあいさつといたします。
| 『「食」と「地域」の再生に向けた 農業農村整備予算の確保を求める集会』が開催 |
「食」と「地域」の再生に向けた農業農村整備予算の確保を求める集会が平成22年12月2日、東京都新宿区「日本青年館」で6月7日に続き、開催された。
この集会は、全国の農業者、農業農村の将来を危惧する市町村長、有識者、水土里ネット関係者66名が呼びかけ、全国から約450名が参集した。
当県からは水土里ネットとちぎ大久保寿夫会長(小山市長)、河宇土地改良協議会吉澤新市会長(鬼怒川右岸土地改良区理事長)をはじめとして30名が参加した。
集会の冒頭、呼びかけ人代表挨拶として、水土里ネット田沢疏水高貝久遠理事長が「平成22年度予算において、農業農村整備予算は大幅に削減され、我が国の農業農村は、将来に大きな不安を抱えることになった。呼びかけ人は、このような農業農村の厳し過ぎる現状を打破すべく、思いを同じくする全国の人々の声を国会や政府に届けようと、5月より行動を開始し、6月には同様な集会を開催した。また、7月には国民の皆様に広く現状を訴えるべく、全国紙に意見広告も出した。今後も引き続き訴えていくべきことは、農業農村を支えている農業農村整備が減少すれば、我が国の農業農村が衰退するということである。本日、参集した地域においても各方面に要請活動を展開し、皆様の力を結集し、農業農村整備事業の予算の確保を求めて、政権与党はじめ関係要路に訴えようではないか。」と述べた。
次に全国水土里ネット野中広務会長が激励挨拶で「先般の予算では土地改良予算が大幅に削減され、土地改良関係団体はもちろん、農業農村を愛し、これらが国の基であると考える良識ある国民に大きな心配・驚きを与えた。通常の仕分けが済んだ後、小沢一郎前幹事長自らの手で土地改良予算を大幅削減した異常さがある。全土連は、幹事長室・農水省をはじめとする関係部署に、削減の復元を陳情してきたが、政務官に会うだけで何らの回答を得ないままの状態にあった。小沢前幹事長との長い対立があっただけに、全土連会長を辞するから予算の復元をと切望したが、返答がないまま更迭された。新内閣に替わり、鹿野農水大臣になり、私どもの陳情を受け取ってもらい、今後の予算について理解を得られた。農業農村は国の基であり、大本であり、日本の豊かな国土や自然環境も農業農村が健全であってはじめて維持されるものであるから、農業者のみならず国民全体の声として届ける運動を展開しなければならない。現在、食を巡る世界情勢は不透明で、皆さんの声が時代を超えて大切なものとして、農業農村を守る努力をしなければならない。農村が永い歴史の上に、先人達の労苦の上に、そして国土保全の大本として国を支え守ってきたことに思い、一層努力したい。」と力強く述べた。
この後、「兵庫における土地改良施設の現状」兵庫県水土里ネット加陽、「笠野原台地の現状」鹿児島県笠野原土地改良区、「農業農村整備事業のPR活動と予算確保の活動報告」愛知県豊川総合用水土地改良区、「平成23年度予算についての情勢報告」全国水土里ネットの4つの情勢報告がされた。
激励挨拶の野中会長
最後に以下の決議を採択し、ガンバロウ三唱で閉会した。
要 請 書
政府は、3月末新たな食料・農業・農村基本計画を閣議決定し、「食」と「地域」の再生に向けて食料・農業・農村政策を国家戦略として位置付け、政府一丸となって政策を推進していくことを表明されており、我々は具体化に大いに期待しております。
しかしながら、平成22年度予算における農業農村整備事業費の大幅削減によって、我が国の農業・農村はその将来に大きな不安を抱えることとなりました。
農地や農業利水施設は食料生産の基礎として不可欠なものであり、農地の改良や施設の更新が円滑に推進されなければ、食料生産が減少するとともに転作作物への転換も滞り、食料自給率の向上に支障を来たすばかりでなく、農村地域の災害の誘発等の増加により農業・農村が成り立たなくなると危惧されるところであります。このため、農村地域の人々から様々な不安の声が挙がるとともに、多くの有識者からも、国民全体の不利益につながるとの指摘がなされているところです。
このような中、23年度概算要求では元気な日本復活特別枠も活用いただき5%増の要求額となりましたが、21年度と比較すれば依然として4割以下に留まる規模となっております。また、特別枠の確保いかんによって本年度の大幅削減から更にマイナスとなれば、我が国の農地や農業水利施設への影響は計り知れません。
農業・農村は、国の大本であり、日本の豊かな国土や自然環境も、農業・農村が健全であって初めて維持されるものです。食を巡る国際情勢も踏まえつつ、日本の農業・農村を下支えする農業農村整備の厳しい状況を打開いただくよう、下記事項の実現を強く要請するところであります。
記
1農業農村整備事業関係の元気な日本復活特別枠要望事項である戸別農家所得補償実施円滑化基盤整備及び農山漁村地域整備交付金について、特別枠要望額を満額確保すること
2食と地域の再生に向け、平成23年度の農業農村整備事業予算について、特別枠を含めた全体規模を大幅増とすること
3農業水利施設の適切な保全管理と計画的な更新・整備、水田汎用化に向けた排水対策などの農地の整備を国策として推進すること
平成22年12月2日※当県呼びかけ人(敬称略)
・大久 保寿夫 小山市長
・吉澤 新市 水土里ネット鬼怒中央 理事長
| 民主党幹事長室・農林水産省・民主党栃木県連・自民党栃木県連に農業農村整備事業の平成23年度予算拡大の要請 |
本会は、去る11月26日、民主党栃木県連及び自民党栃木県連に対して、農業農村整備事業に関する平成23年度農業農村整備事業予算拡大の要請を行った。また、12月2日には民主党幹事長室・農林水産省・関係国会議員に対しても要請活動を実施した。
今回の要請は、今年度の農業農村整備事業予算が対前年比36.9%と大幅に削減され、当県において圃場整備が4割程度いまだ未整備であることに加え、全国的に農業水利施設の耐用年数のピークが今後10年間は続くものとされている等の農業農村整備事業の実施に厳しい影響を受けている現状に危機感を抱き、必要な予算措置を求めた要請活動である。
11月26日は、本会から小坂利雄副会長・大久保幸雄専務理事はじめとして、農業農村整備を推進する会岡本芳明会長・益子町土地改良区谷口正己理事長・南河内土地改良区黒川英代理事長・湯津上土地改良区礒紘一理事長が、民主党栃木県連を訪ねて、簗瀬進常任顧問・佐藤栄県会議員に要請書を手渡し、内容を説明した後、意見を交わした。次に自民党栃木県連では、佐藤事務局長に要請書を手渡した。
12月2日は、本会より大久保会長・大久保専務理事・小山市美田中部土地改良区稲葉要理事長・小山市美田東部土地改良区藤沼光一副理事長が民主党幹事長室で要請するため、国会議事堂衆議院第15控室で米長晴信民主党組織副委員長・陳情要請対応本部長代理と面談し、農業農村整備事業の平成23年度予算拡大を講じるよう求めるとともに、平成23年度予算拡大の必要性を説明し、要請書を手渡した。また、各土地改良区理事長をはじめ要請に参加された皆様は4班の分担により、農林水産省及び当県選出国会議員に要請活動を行った。なお、要請参加者・要請先及び要請書内容については、下記のとおりである。
12月2日要請参加者(敬称略)
鬼怒川右岸土地改良区理事長 吉澤新市
日光市土地改良区理事長 田井 哲
日光市土地改良区事務局長 渡邊幸男
市貝町農林商工課長 神野正明 (代理出席)
栃木市産業振興部農林課長 江連敏夫 (代理出席)
大岩藤土地改良区理事長 石川守久
思川西部土地改良区理事長 椎名英雄
思川西部土地改良区事務局長 横塚 清
大田原市産業文化部農林整備課長佐藤富夫 (代理出席)
那須町土地改良区理事長 津久井恭夫
佐野市土地改良区理事長 寺嶋勝豊
三栗谷用水土地改良区事務局長足立一彦 (代理出席)
農業農村整備を推進する会会長 岡本芳明農業農村整備を推進する会事務局長 君島一郎
小山市美田東部土地改良区副理事長 藤沼光一
小山市美田東部土地改良区事務局長 高瀬孝明
小山市美田中部土地改良区理事長 稲葉 要
要請先(敬称略)
民主党幹事長 岡田克也
民主党幹事長代理・陳情要請対応本部長 枝野幸男
民主党政調会長 玄葉光一郎
民主党参議院政策審査会長・陳情要請対応本部長代理一川保夫
民主党組織副委員長・陳情要請対応本部副本部長米長晴信
民主党政策調査会農林水産部門会議座長 佐々木隆博
民主党政策調査会農林水産部門会議農業農村整備WT座長 森本和義
自民党幹事長 石原伸晃自民党政務調査会長 石破 茂
自民党農林部会長 宮腰光寛
農林水産大臣 鹿野道彦
農林水産副大臣 筒井信隆
農林水産副大臣 篠原 孝
農林水産大臣政務官 松木けんこう
農林水産大臣政務官 田名部匡代
農林水産省農村振興局長 吉村 馨
農林水産省次長 齋藤晴美
農林水産省総務課長 枝元真徹
農林水産省農村政策部長 三浦 進
農林水産省農村計画課長 坂本 修
農林水産省中山間地域振興課長 小林厚司
農林水産省都市農村交流課長 仲家修一
農林水産省農村環境課長 近藤秀樹
農林水産省整備部長 齊藤政満
農林水産省設計課長 田野井雅彦
農林水産省土地改良企画課長 上大田光成
農林水産省水資源課長 島田眞司
農林水産省農地資源課長 矢野 均
農林水産省防災課長 黒田憲司
農林水産省農村整備官 坂井康宏
衆議院議員 石森久嗣
衆議院議員 福田昭夫
衆議院議員 渡辺喜美
衆議院議員 山岡賢次
衆議院議員 茂木敏充
衆議院議員 遠藤乙彦
衆議院議員 佐藤 勉
衆議院議員 玉木朝子
衆議院議員 富岡芳忠
衆議院議員 山内康一
参議院議員 谷 博之
参議院議員 上野通子
参議院議員 田城 郁
参議院議員 三原じゅん子
要 請 書
我が国の農業・農村は、基幹的な労働力の6割を65歳以上の高齢農家が担う中、米価の低迷と相まって担い手不足が懸念される一方、食料自給率は4割程度に低迷しております。
食料自給率の向上のため、生産性の向上と水田の汎用化に資する圃場整備は未だ4割程度が未整備であり、農業水利施設につきましても、今後10余年間は耐用年数に到達する施設のピークが続く状況にあります。
しかしながら、平成22年度農業農村整備事業費は、前年度に比べて4割を下回る大幅な削減となっております。
農地や農業水利施設は、食料生産の基礎として不可欠なものであり、農地の改良や施設の更新が円滑に推進されなければ、食料生産の減少を招くほか、転作作物への転換が滞ることによって、食料自給率の向上に支障を来たすばかりでなく、農村地帯の災害の誘発などの増加により、農業・農村に重大な影響を及ぼすものと危惧しているところであります。
そこで、我が国の農業・農村を根底から支えている農業農村整備の厳しい状況を打開するため、次の事項の実現を強く要請いたします。
記
1.戸別所得補償制度の円滑な実施に大きく貢献する農業農村整備事業の積極的な推進
2.農業農村整備事業の推進に必要な予算を確保すること
3.農業水利施設の適切な保全管理と計画的な更新整備、水田の汎用化に向けた排水対策などの農地整備を国策として推進すること
平成22年12月2日
栃木県土地改良事業団体連合会会 長 大久保 寿夫
要請者名簿
栃木県土地改良事業団体連合会農業農村整備部会長 斎藤文夫
農業農村整備を推進する会会長 岡本芳明
栃木県土地改良事業推進協議会会長 小坂利雄
栃木県ほ場整備連絡協議会会長 加藤一克
栃木県農村総合整備事業促進協議会会長 猪瀬成男
栃木県農業集落排水事業連絡協議会会長 高橋森一
針ヶ谷土地改良区理事長 福富 洋
日光市土地改良区理事長 田井 哲
深津土地改良区理事長 上田芳雄
南押原土地改良区理事長 橋本啓藏
益子町土地改良区理事長 谷口正己
小貝川沿岸土地改良区理事長 山川英男
南河内土地改良区理事長 黒川英代
小山市美田東部土地改良区理事長 植野洋生
小山市美田中部土地改良区理事長 稲葉 要
小山用水土地改良区理事長 福田洋一
江川南部土地改良区理事長 相田英幸
湯津上土地改良区理事長 礒 紘一
金田北部土地改良区理事長 荒井一夫
佐野市土地改良区理事長 寺嶋勝豊
民主党栃木県連で簗瀬進常任顧問への
要請行動
米長晴信民主党組織副委員長陳情要請対応本部 副本部長への要請行動
山岡賢次衆議院議員への要請行動
茂木敏充衆議院議員への要請行動
| 平成22年度第3回理事会を開催 |
本会は、去る12月13日、宇都宮市内のホテルにおいて、第3回理事会を開催した。会議は、福田事務局次長兼総務部長の司会進行で開会し、大久保会長の開会挨拶に続いて南斎栃木県農政部農村振興課長から来賓挨拶をいただき議事に入った。
議事は、第1号議案平成22年度事業計画の変更について、第2号議案平成22年度一般会計予算の補正について、第3号議案規約の一部改正について、第4号議案部会委員会規程の一部改正について、第5号議案職員給与規程の一部改正についての5議案について審議が行われ、全議案とも原案どおり議決された。
開会挨拶を述べる大久保会長
| 平成22年度土地改良区職員研修会を開催 |
本会は、去る11月25日、26日の両日、日光市鬼怒川温泉大原の鬼怒川グランドホテルにおいて、平成22年度土地改良区職員研修会を開催した。同研修会は、近年における会員の組織の変化や本会に対する負託の変化、さらには時代の要請が激変している中で、会員土地改良区間の情報交換や交流を促進させるとともに、会員と本会の共存共栄の発展に資する目的で開催したものであり、昨年度に続き2回目の開催となった。
研修会は石塚総務課長の司会進行で開会し、最初に篠崎事務局長が開会挨拶を述べ、本会業務の概要について説明を行った。続いて研修に入り、各研修項目について講師の方から講演をいただいた。
後半の事例発表では、初めに船生土地改良区事務局の手塚政信氏から、平作堀の隋道崩落の発生から仮取水による営農対応、復旧工事に至るまでの経過説明があり、事故の教訓として、基幹水利施設ストックマネジメント事業を積極的に導入し、施設の長寿命化が図られるような適切な保全管理を行うことが必須であり、とても重要であることを再認識したようであった。 続いて、三重県多気町の立梅用水土地改良区事務局長の高橋幸照氏から、「地域と共に歩む土地改良区の新たな役割」と題し、講演をいただいた。講演では、地域との共同活動の成果として農村コミュニティの本質である「人と人が繋がり合い協力し合う心」を取り戻したこと、用水の地域資源としての価値や多面的機能をみんなに理解していただき、それを管理する土地改良区の存在や役割が解かり易くなったこと、身近にある水や土及び歴史や文化は大切な地域資源であり、この地域資源を保全して行くためには「活用」することであり、活用することが「保全」に繋がる、という「相関関係」であること、等を強調された。
1.研修事項
(1)情勢報告(H22・23 NN予算関係)
(2)栃木県における圃場整備の状況とその効果
(3)農業水利施設の保全管理について
(4)平作堀の崩落事故復旧についての事例発表
(5)立梅用水土地改良区の取組についての事例発表
船生土地改良区手塚氏
立梅用水土地改良区高橋事務局長
意見交換テーマ検討会(企画委員)
2.意見交換テーマ検討会 2日目の意見交換会では、篠崎事務局長が座長となり、前日の当研修会企画委員によるテーマ検討会で決定した「未収金の回収方法について」をテーマとし、各土地改良区の実状や回収率を上げる手段等について活発な意見の交換が行われた。
2日目の意見交換会(企画委員)
2日目の意見交換会(土地改良区職員)
| 第33回全国土地改良大会が長崎県で開催 |
第33回を迎えた全国土地改良大会(長崎大会)は、全国水土里ネット(全国土地改良事業団体連合会)及び水土里ネット長崎(長崎県土地改良事業団体連合会)の主催、農林水産省、長崎県、島原市、雲仙市及び南島原市の後援により、去る10月26日に長崎県島原市「島原復興アリーナ」において、全国の土地改良関係者など約3,500名が参集して盛大に開催された。本県からは会員土地改良区の役職員並びに本会役職員の総勢28名が参加した。
長崎大会の開催要旨は、大会テーマに『伝えよう 水の音色、土の温もり、里の安らぎ、西に端しの風にのせて』を掲げ、農業農村整備にかかわる全国の関係者が一同に集い、より一層連携を深めることを目的に開催された。また、農業・農村の重要性とそれを支える農業農村整備事業の役割を広く国民にアピールし、21世紀を迎えた農業農村整備事業の展開について認識と決意を新たに『美しい豊かなむらづくり』を目指すもので、長崎県は本土最西端の地であり、古き昔から諸外国との交流が盛んであり、長い歴史の中で、諸外国から伝えられたものは、日本の「食と農」の発展に大きく寄与しており、本大会は『水・土・里』の素晴らしさと新たな農業・農村の役割をここ長崎から伝え、育むことを託している。
大会のオープニングは、伝統芸能継承と地域活性化のため、地元深江の若者で結成された「和道・深江太鼓」による深江太鼓の演奏が披露され、太鼓の鼓動の高鳴りを響きに託し、人々に勇気と人間の優しさ・感動が伝わった。引き続き、長崎県紹介のVTRが放映された。 大会式典は、一瀬政太水土里ネット長崎副会長の開会宣言に続き、長崎県出身のソプラノ歌手福地友子さんとともに参加者全員で国家を唱和した。これに続いて、開催県の宮本正則水土里ネット長崎会長、野中広務全国水土里ネット会長がそれぞれ主催者挨拶、中村法道長崎県知事と横田修一郎島原市長によるそれぞれの歓迎挨拶があり、来賓を代表され松木けんこう農林水産大臣政務官が祝辞を述べ、その後、登壇された来賓等が紹介された。
土地改良事業功績者表彰は、長年にわたり土地改良事業に貢献された方の表彰式が行われ、農林水産大臣表彰6名、農林水産省農村振興局長表彰13名、全国土地改良事業団体連合会長表彰48名の方々が受賞の栄に浴した。本県からは、高橋勇丞大田原市土地改良区理事長が全国土地改良事業団体連合会長表彰を受賞された。また、本大会を記念して、長崎県土地改良事業団体連合会長表彰も行われ、長崎県内の地域農業の振興に貢献している9土地改良区が表彰され、その功績が讃えられた。
続いて、第8回目となる21世紀土地改良区創造運動大賞表彰に移り、大賞に6団体、さなえ賞に7団体が受賞した後、優良活動事例が紹介された。
基調報告は、斎藤晴美農林水産省農村振興局次長より「農業農村整備事業の必要性について」講演があった。
大会宣言は、長崎県立農業大学校の野菜学科2年生前田拓也さんと同大学校果樹学科2年生早崎美紀さんによって、『本日、ここに集う私達をはじめとする水土里ネットの人々は、我が国の「環境」と「資源」を将来にわたって保全、管理、維持していくため、将来を担う若者も積極的に参画し、国民一体となって、「水」「土」「里」を守り、育み、伝えていくことを日本近代文化のさきがけとなった、ここ長崎の地から全国に向けて高らかに宣言する。』と力強く大会宣言文が読み上げられ、満場一致で採択された。
大会も終盤となり、次期開催県である宮城県の紹介VTRが放映され、大会旗が水土里ネット長崎から全国水土里ネットへ、そして水土里ネット宮城へと引き継がれ、水土里ネット宮城会長から『伊達の郷から未来へ たたえしは水の知恵 つなぐは土のちから まもるは里のきずな』をテーマに、「来年10月26日に仙台市で開催するので、皆様のお越しをお待ちする。」と時期開催県として挨拶があった。
その後、北海道の眞野弘北海土地改良区理事長から、「今のままの予算水準では、農業や水利施設への影響は計り知れない。」として緊急動議が発せられ、政府に対し、(1)平成22年度における補正予算を早期手当てすること。(2)平成23年度予算において、特別枠要望を満額確保するとともに、全体予算規模の大幅増を図ること。(3)農業水利施設の適切な保全管理、計画的な更新整備、水田の汎用化に向けた排水対策などの農地の整備を国策として推進することの3項目が提案されると、会場は大きな拍手に包まれ、野中全国水土里ネット会長が提案の賛意を求めたところ満場一致で決議された。
閉会挨拶は、吹田幌全国水土里ネット副会長、奥村慎太郎水土里ネット長崎副会長が閉会宣言を行い、滞りなく式典が終了した。
その他、同会場内においては、開催地である長崎県の農村整備事業を紹介したパネル展示や県内各地域の特産物が販売され、多くの参加者で賑わいを見せた。
大会会場にて参加者の記念撮影
全国水土里ネット会長賞
高橋勇丞氏の略歴昭和9年11月14日生まれ76歳
大田原市滝沢在住
昭和56年7月 親園西部土地改良区副理事長
平成4年4月 同土地改良区理事長、那須野ヶ原土地改良区連合理事
平成11年4月 北那須土地改良事業推進協議会副会長
平成11年12月 大田原市土地改良区庶務会計担当理事
平成16年4月 同土地改良区副理事長
平成18年4月 本会農業農村整備部会委員
平成20年4月 同土地改良区理事長現在に至る。
平成21年4月 本会理事現在に至る栃木県土地改良区統合整備推進協議会会長現在に至る。北那須土地改良事業推進協議会会長現在に至る。
他に、昭和58年12月から平成19年11月までの6期24年間大田原市議会議員その間2期4年間同市議会議長を務める。さらには、平成16年5月から大田原市農業振興協議会委員、平成17年7月から同市農業委員、平成18年11月から大田原市認定農業者などを務める。

| 県営土地改良事業の換地業務に係る感謝状贈呈式を開催 |
去る10月22日、栃木県公館において「県営土地改良事業の換地業務に係る感謝状贈呈」が栃木県知事ならびに関係者一同の出席の中、福田知事より関係土地区に贈呈されました。受賞土地改良区並びに地区委員会においては、大変おめでとうございました。
感謝状贈呈土地改良区
(1)都賀町土地改良区(県営地域開発関連総合整備事業赤津南部地区)
(2)下ケ橋河原土地改良区(県営圃場整備事業下ケ橋河原地区)
(3)小貝川西土地改良区(県営圃場整備事業小貝川西地区)
(4)寺尾北部土地改良区(県営圃場整備事業寺尾北部地区)
(5)長沼西部土地改良区(県営圃場整備事業長沼西部地区)
(6)下田原南部土地改良区(県営圃場整備事業下田原南部地区)
※採択年度の早い順(同年度の場合は事務所建制順)
県営赤津南部地区
県営下ヶ橋河原地区
県営小貝川西地区
県営寺尾北部地区
県営長沼西部地区
県営下田原南部地
| 関東地区農村総合整備推進連絡協議会第37回通常総会を開催 |
去る10月19日、全国都市会館において第37回通常総会が開催された。
総会に先立ち理事会を開催し、総会に諮る議案について慎重審議を行い承認された。その後、関東農政局整備部泉原地域整備課長を来賓に迎え、当番県である水土里ネット茨城小山専務理事を議長に通常総会が行なわれた。第1号〜第6号議案の各議案の審議が行われ、いずれも原案どおり承認・議決された。
本推進連絡協議会は、会員相互の連絡提携、事業の円滑な施工を図る目的に、昭和49年度に設立したものである。しかしながら近年、社会情勢の変化により本協議会の必要性が問われる状況となってきている。
平成21年度から農村総合整備推進事業の補助事業も公募制に移行されており、今後補助事業等も廃止されるかもしれない厳しい状況が予想されているため、本年度末を持って、解散することが承認された。
その後、国会議員・農林水産省・関東農政局へ予算要請活動を行なった。
| 県営かんがい排水事業吾妻地区・竣工祈念を開催 |
去る11月25日、佐野市下羽田地内において県営かんがい排水事業吾妻地区の吾妻排水機場竣工式を栃木県知事(代理粂川農政部次長)を始めとする多くの関係者出席のもと開催された。
本事業は、昭和31年の県営排水改良事業により整備されたが、築造後50有余年が経過し、施設の老朽化が甚だしく、排水能力が低下してきており毎年のように湛水被害を生じ営農に支障を来たしていたので、老朽化した排水機場を更新し、営農改善を図り、農業経営の安定化を図る目的としたものである。
| 長沼西部地区記念碑除幕式及び竣工祝賀会を開催 |
この度、県営担い手育成基盤整備事業長沼西部地区が竣工の運びとなり、去る11月29日、真岡市大道泉地内において記念碑除幕式、竣工祝賀会が挙行された。
記念碑除幕式では、長沼西部土地改良区の上野勝久理事長をはじめ、大塚国一参事兼芳賀農業振興事務所長、真岡市長代理の飯島眞一産業環境部長、鶴見真市議会議長による除幕の儀から始まり、今後の地域の繁栄を祈念した玉串奉奠等しめやかにとり行われた。また、竣工祝賀会についても多数の来賓、土地改良区役員が出席し盛大に挙行された。
◆事業概要◆
事業名 県営担い手育成基盤整備事業
事業区域 真岡市堀込、長沼、大道泉、鷲巣、西大島地内
事業実施年度 平成14年度〜平成19年度
事業受益面積 71.2ha
総事業費 8億9千1百万円
組合員数 234名
| 「水を見て!農を考え!恵を味わう! ふれあいウォークin佐野」を開催 |
去る11月6日、佐野市羽田〜田島地内において、佐野市土地改良区、栃木県21世紀土地改良区創造運動推進本部、栃木県、佐野市、安足土地改良事業推進協議会、三栗谷用水土地改良区、足利市わたらせ川左岸土地改良区及び足利佐野めんめん街道推進協議会との共催により、一般県民から募集した親子づれなど約80名の参加を得て「水を見て!農を考え!恵を味わう!ふれあいウォークin佐野」を開催した。
このウォーキングは、昨年度から本会が取り組んでいる「農業用水水源地域保全対策事業」の一環として、私たちの命を繋ぐ安全・安心な食料を生産するためになくてはならない農業用水と、これを育む水源林との関わりについて県民の理解を深めていただくことを目的に開催した。併せて、農業用水の管理に深く関る水土里ネットの果たす役割や活動についても知っていただくために、21世紀土地改良区創造運動としても実施した。
当日は、汗ばむほどの天候に恵まれ、青空のもと、地元地域の施設や、生態系保全や景観を維持管理する農地・水・環境保全対策事業に取り組む地域、水源の地下水を使用する第一酒造や文化財などを巡る約9.6kmのウォーキングを通じて、農業用水の役割や農産物が出来るまで、水土里ネット(土地改良区)の働きや農業農村整備事業等を紹介した。
今回のサプライは、佐野で有名な「佐野ラーメンとイモフライ」をお昼に提供し、持参したお弁当と一緒に美味しくいただいた。また、ゴール後には、足利佐野めんめん街道推進協議会が推薦する「佐野ラーメン・うどん・小麦粉・ソースなど」の販売、参加者へのお土産として地元生産の「米粉・きな粉・すりゴマ」のセットを配布するなど、豊かな実りから農業用水の大切さや水を育む水源林の大切さを感じ取っていただいた。
参加者からは、「農業用水の大切さや重要性が理解できた。」「農業、農村の重要性、大切さをもっとPRしていくべき。」「また是非参加したい。」など、沢山の感想が寄せられ、大変盛況であった。
【行程】吾妻排水機場 ===佐野西部地区水処理センター===マルウチ製麺
===第一酒造見学===大聖寺見学===椿田城見学===庭田邸見学
===雲竜寺見学===吾妻排水機場
| とちぎ“食と農”ふれあいフェア2010に出展 |
本会は、去る10月23日から24日の2日間にわたり、栃木県庁及び周辺施設を会場に、健全な食生活の実現に向けた情報発信や各地域の農産物・名産品の展示販売、農業体験や「食」の魅力と地域資源を結びつけ、県民の元気につなげる“食と農”の総合的な祭典を目的として開催した。
今年は、『美味しい食とのめぐりあい♪「とちぎ食の回廊」』をテーマとして、宇都宮ジャズコンサート、演劇、お笑い芸人ライブ、地元とちぎのシェフによる料理ショー等、多彩な催しが行われた。
オープンセレモニーでテープカットを行なう関係者の皆さん
本会は、「水」と「土」によって育まれた“食と農”の大切さ、水・土・里の恵みを感じ取っていただくことをテーマに、「地域資源を守っている水土里ネットの果たす役割」農業用水水源地域対策における農業用水と水源林の役割について「ジオラマの展示」、農地・水・環境保全向上対策における「県内活動組織の取組の紹介」、水田周辺の水辺に生息する「身近な魚や昆虫」等を展示した。
水はどこから来て、どこへ行くのか?また、どのように使われているのか?などが解るジオラマと、現在ではあまり見ることが少なくなった生きものに、大人たちから子供たちまで興味を引くことができ、命を育む豊かな農村環境を守り受け継ぐ大切さを伝えた。
田んぼ周りの生きものたちに興味津々
ジオラマで、水の流れを勉強する子供たち
| 第10回花と農産物の清南大地食の祭典を開催 |
水土里ネット清南(清原南部土地改良区)、清原南部明るいむらづくり推進会議及びチーム清南夢畑主催、水土里ネットとちぎ、水土里ネット鬼怒中央、清原地域振興協議会及び清原地区市民センター後援による「花と農産物の清南大地食の祭典」は、去る10月16日、宇都宮市上籠谷町地内の農地において、関係者や周辺住民の家族約1,200名の参加を得て盛大に開催された。
主催者を代表して水土里ネット清南の岡本芳明理事長が、「このように大勢の方にご参加いただき大変嬉しく思っています。県営畑地帯総合整備事業を契機に生産性の高い畑作農業と活力ある地域づくりを目指して様々な活動に取組んでまいりましたが、この祭典もその一つであります。皆様に対する感謝の念を忘れずに、後継となる若い世代が地域を盛り上げ、清南大地が更なる発展を遂げていくことを願っています。」と開会の挨拶を述べ、来賓祝辞の後、いっせいに炭に着火し、バーベキュー大会が始まった。
開会挨拶をする岡本芳明理事長
この祭典は、清南大地の活力ある農業農村を築くため、充実した人間味あふれる地域づくりを目指し、花に囲まれたなかでのバーベキューを通して都市と農村との相互の語らいと交流を図って、清南大地のなお一層の理解と愛着を深めてもらうことを目的として開催しており、今年で10回目を数える。 参加者は、バーベキューのほか、清原南小学校金管バンド演奏、お囃子、カラオケ、地元清南大地産の農産物が当たるお楽しみ抽選会等のイベントを楽しむとともに、各種模擬店では新鮮な野菜や果樹を買い求めていた。
また、会場周辺に育てられたお花畑では、咲誇るコスモスの花を親子で楽しむ姿も見られた。 祭典の最後に、会場に隣接した農地で組合員がこの日のために丹精こめて育成したさつまいもの無料収穫体験が行われ、参加者は収穫の喜びを全身で味わっていた。
バーベキューを楽しむ参加者の皆さん
収穫の喜びを全身で味わう子供たち
| 農業基盤整備資金のご案内 |
農業基盤整備資金は、農業生産力の増大、生産性の向上を図るための生産基盤の整備や農村環境基盤の整備などに係る費用に対して長期・低利な融資を行う、株式会社日本政策金融公庫(農林水産事業)及び沖縄振興開発金融公庫の制度資金です。
なお、借入時の金利は、金融情勢により変動しますので、最新の利率は最寄の(株)日本政策金融公庫(農林水産事業)に確認ください。
【平成22年11月18日現在の利率】
区 分 融資期間にかかわらず 補助事業 県 営 1.65% 団体営 1.50% 非 補 助 一 般 1.50%
| ◆ 非補助農業基盤整備資金の案内 ◆ |
国の補助を受けない土地改良事業・生活基盤整備事業等に対して、低利の融資が受けられます。
◆非補助農業基盤整備資金とは 地域の特性に応じた農業生産基盤の整備・保全を図り、食料の安定供給の確保等政策目的を実現してゆくためには、国の直轄事業や補助事業と関連した非補助事業の推進が重要になっています。
非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国からの補助を受けないで、かんがい排水やほ場整備、客土などの事業に取り組み、農業生産基盤の整備・保全の推進を図る場合、農林漁業金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対して低利で融資する資金です。
なお、国の補助対象でない県又は市町村単独による補助事業についても、融資の対象となります。
◆融資の条件
■貸付対象者
〇土地改良区
〇土地改良区連合(事業主体となる場合に限る)
〇農業協同組合
〇農業協同組合連合会
〇農業を営む人
〇農業振興法人
〇5割法人・団体(農業集落排水事業の実施に限る)
■貸付限度額
複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区等が当該年度に負担する額までとなっています。(ただし、融資1件当たりの最低額は50万円となっています。)
なお、農業集落排水事業では、一部施設ごとに限度額を設定しています。
■貸付利率
固定金利であり、償還が終わるまで適用される金利は変更ありません。
最新の金利は、最寄の日本政策金融公庫にご確認下さい。
■償還期限
最長25年(据置期間10年以内を含む)になっており、事業内容に応じて設定できます。
■償還方法
元利均等償還、元金均等償還のいずれかを選択できます。
■融資対象事業種類
かんがい排水、畑地かんがい、ほ場整備、客土、農道、索道、畦畔整備、農地造成、農地保全、防災、維持管理、農業集落排水、飲雑用水施設などとなっています。
| 落ち葉を想う 総務部会員支援課 高橋伸拓 |
里山の生物多様性をめぐる追い風は「SATOYAMA イニシアティブ(Initiatives)」という用語で「21世紀環境立国戦略」に示された8つの戦略のうちの「生物多様性の保全による自然の恵みの享受と継承」の中で、示されました。その中では「我が国の自然観や社会・行政のシステムなどを自然共生の智慧と伝統を活かしつつ、現代の智慧や技術を統合した自然共生社会作りを、里地里山を例に世界に発信する。〜(中略)〜 世界各地にも存在する自然共生の智慧と伝統を現代社会において再興し、さらに発展させて活用することを『SATOYAMAイニシアティブ』と名づけて世界に提案し、世界各地の自然条件と社会条件に適した自然共生社会を実現する」としています。また、生物多様性条約(CBD)第10回締約国会議(COP10)では、「SATOYAMAイニシアティブ」について特記した決定が採択されました。決定では、締約国は「SATOYAMAイニシアティブ」を生物多様性及び人間の福利のために人為的影響を受けた自然環境をより理解・支援する有用なツールとなりうると認識すること、そして、締約国その他政府及び関連機関に対しイニシアティブのさらなる進展のためパートナーシップに参加することを奨励することが記載されました。
では、私たちの身近にある「SATOYAMA」では、どのような状況にあるのでしょうか。簡単には、農業の方式や生活様式が近代化され、昔ながらの雑木林の管理や資源循環が行われなくなり、元来多くの生物多様性を誇っていた環境が劣化しつつあるということです。県内でも多くの里山に生息する種が“絶滅危惧種”として指定されるようになっています。また、八溝地域を中心としてイノシシが里に下り、農作物を荒らす被害が急増しています。これらは、営農状況と雑木林の利用の変化に起因していると思われます。農地の整備に際しては、土地改良法の改正に伴って「環境との調和への配慮」が導入され、その場の環境を保全するようになりました。しかし、林地の対策は進んでいないのが現状です。そのようななか、近年注目されているのが「落ち葉」です。里山の雑木を構成する多くがクヌギなどの落葉広葉樹で、秋にはドングリとともに葉が落ちます。ドングリ自体も多くの生きものの食料になりますが、落ち葉は分解者の餌資源・植物の肥料となります。また、両生類や昆虫類など小さな生物の世界からみると、落ち葉の堆積層は厳しい冬越しの環境として重要な資源でもあります。こういった里山の生産者(植物)による一次資源の代謝を、ヒトの活動で活性化させてきた「先人の叡智」を現代の形で復元するには、どのようなことが必要なのでしょうか。里山の森はほとんどが二次林で、スギやヒノキの植林が進んできたものの、林業の衰退で代謝が滞っています。その状況を憂いた有志により「ドングリの木」を復元する落葉広葉樹植林プロジェクトや下草刈り・間伐といった管理活動を実践する活動も活発になってきています。一方、栃木県では、森林環境を維持管理・改善するための森林環境税の導入や里山の生態系を重要視した「生物多様性とちぎ戦略」の策定といった対策を実施しています。豊かな里山の雑木林を形成することが多様な生物の生息・生育を実現するばかりでなく、農地への獣害の減少や水源の涵養など、多くの恩恵が得られることを念頭に、二次的な自然とヒトとのかかわり方を真剣に考える時がきているのではないでしょうか。
写真 イノシシのヌタ場となってしまった中山間地の水田
| 平成22年10・11・12月主要行事報告 |
10月
日 行 事 5 第2回通常総会並びに調査研究会 7 第2回田んぼまわりの生きもの調査インストラクター養成講座 7〜8 平成22年度関東一都九県土連協議会秋季総会 16 第10回花と農産物の清南大地食の祭典 19 関東地区農村総合整備推進連絡協議会理事会及び第37回通常総会 19 平成22年度農地・水・環境保全向上対策関東9県活動組織発表会 21 推進協議会担当者会議 22 県営土地改良事業の換地業務に係る感謝状贈呈式 23〜24 とちぎ“食と農”ふれあいフェア2010 26 第33回全国土地改良大会in長崎 28〜29 平成22年度農業農村整備技術強化対策事業施工技術研修会
11月
日 行 事 4 平成22年度農業集落排水事業推進研修会 5 土地改良施設診断・管理指導等事例ブロック検討会 6 ふれあいウォークin佐野 10 平成22年度栃木県小水力発電推進協議会(第1回) 11〜12 平成22年度塩谷地方土地改良事業推進協議会先進地研修会 11〜12 関東地区農村総合整備推進事業研修会並びに農業集落排水事業研修会 16〜17 平成22年度栃木県農業集落排水事業連絡協議会視察研修 17 平成22年度利根川水系農業水利協議会現地研修会 24 平成22年度小山市グレードアップ推進対策講演会 25 吾妻排水機場竣功式 25〜26 会員の職員研修会 26 第46回農地集団化事業推進全国研究会 26 農業農村整備事業予算に関する要請活動 29 長沼西部地区記念碑除幕式及び竣工祝賀会 30〜1 安足土地改良事業推進協議会役職員視察研修
12月
日 行 事 2 平成23年度農業農村整備事業予算拡大陳情 2 農業農村整備の集い 9 第3回田んぼまわりの生きもの調査インストラクター養成講座 13 第3回理事会 16 財政的援助団体等に対する監査(予備監査) 21 平成22年度農業農村整備技術強化対策事業一般研修会 28 仕事納め式
| 表紙写真説明 |
表紙の写真『みのり』
○撮影者
那須拓陽高等学校 3年 森 麻菜美 さん
○コ メ ン ト
平成21年度「美しいとちぎのむら写真コンテスト」農業部門で見事優秀賞に輝いた作品です。
審査講評は、「写真を撮る角度がよく、奥行きがある。生徒たちの様子、表情がおもしろい。学校の実習風景をよく表現している。」というものでした。